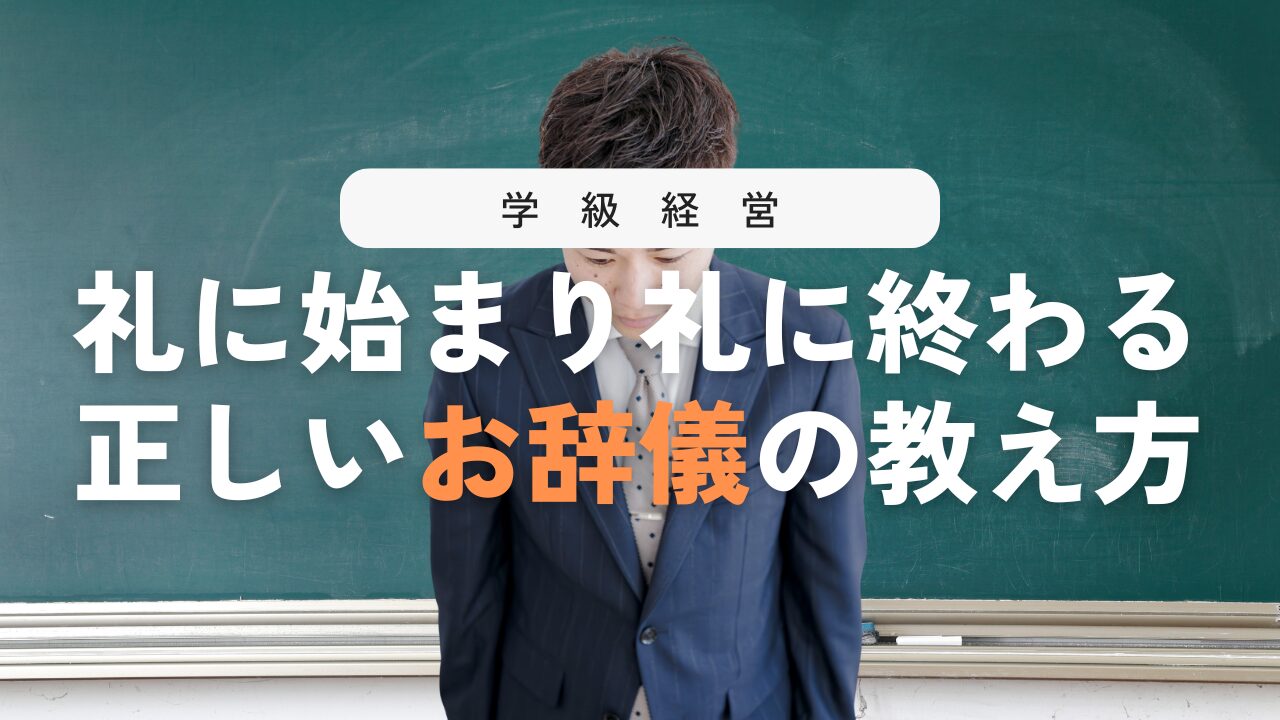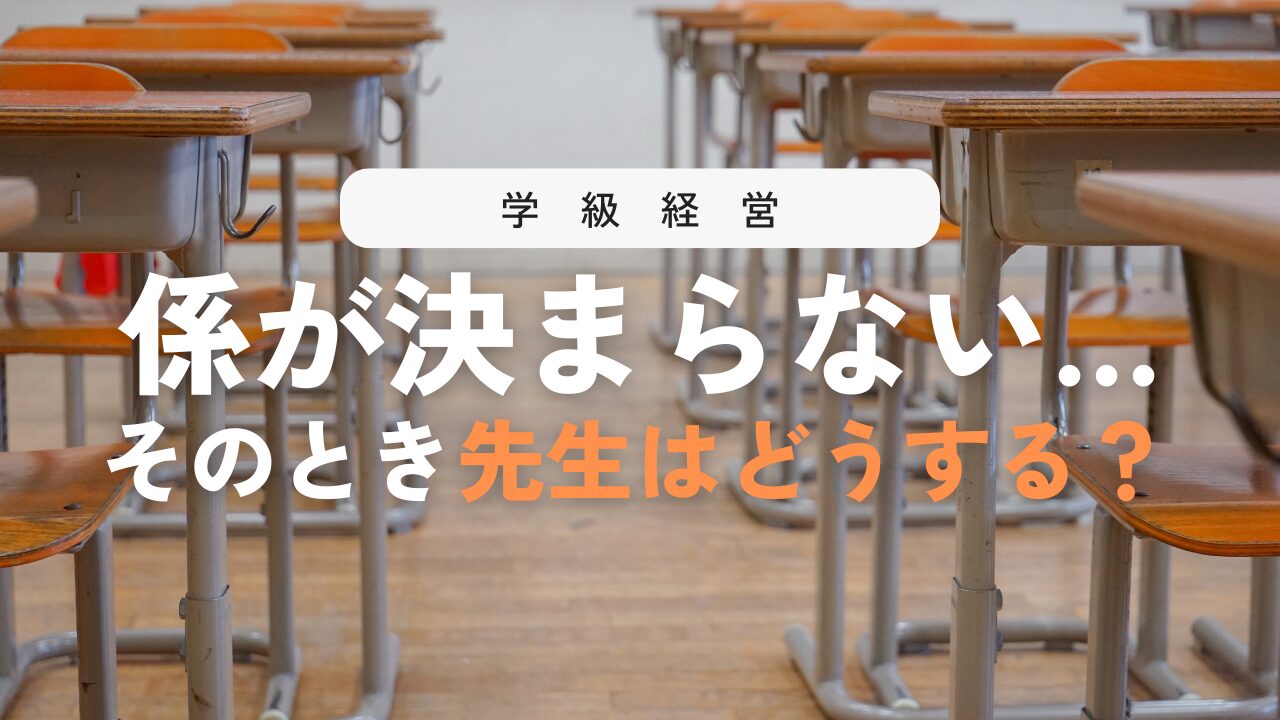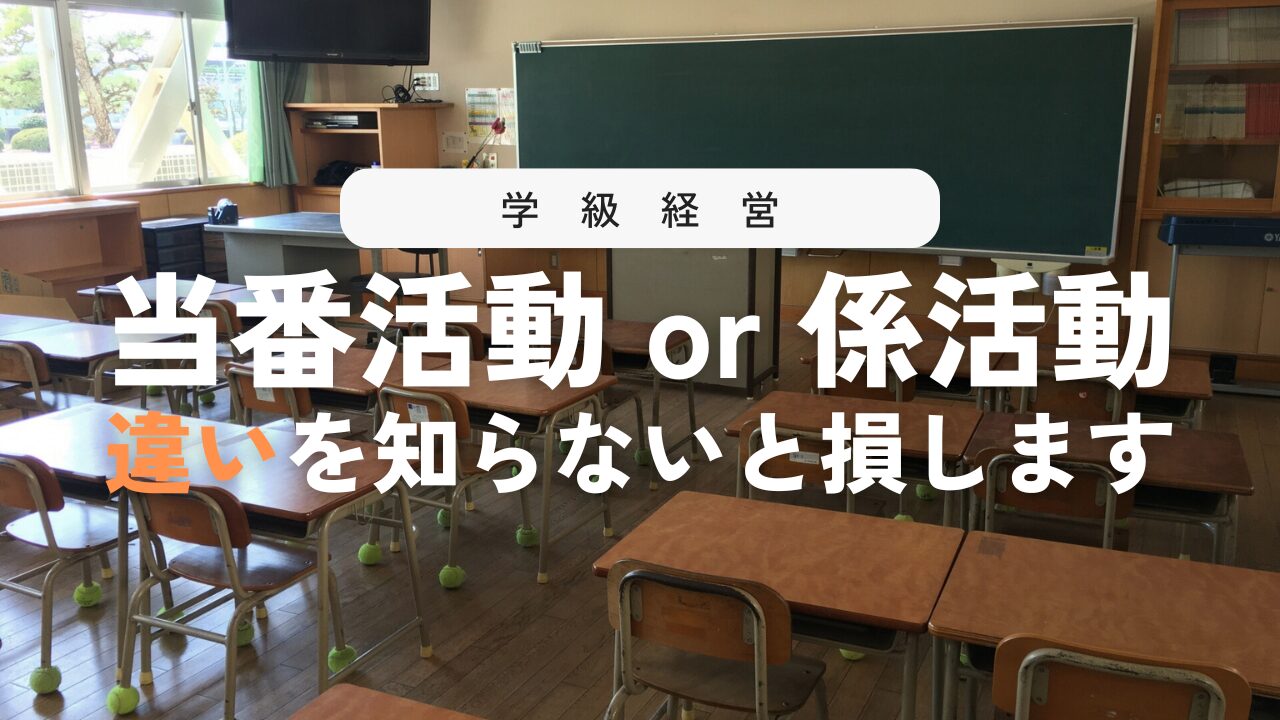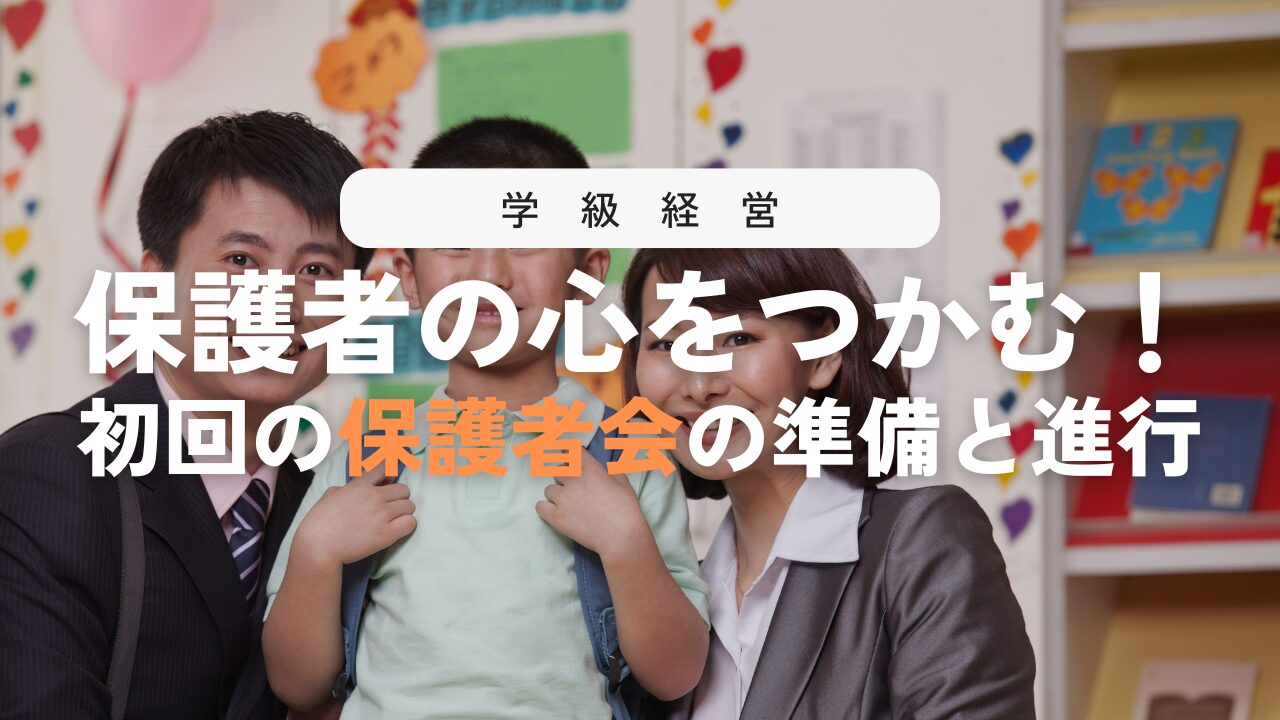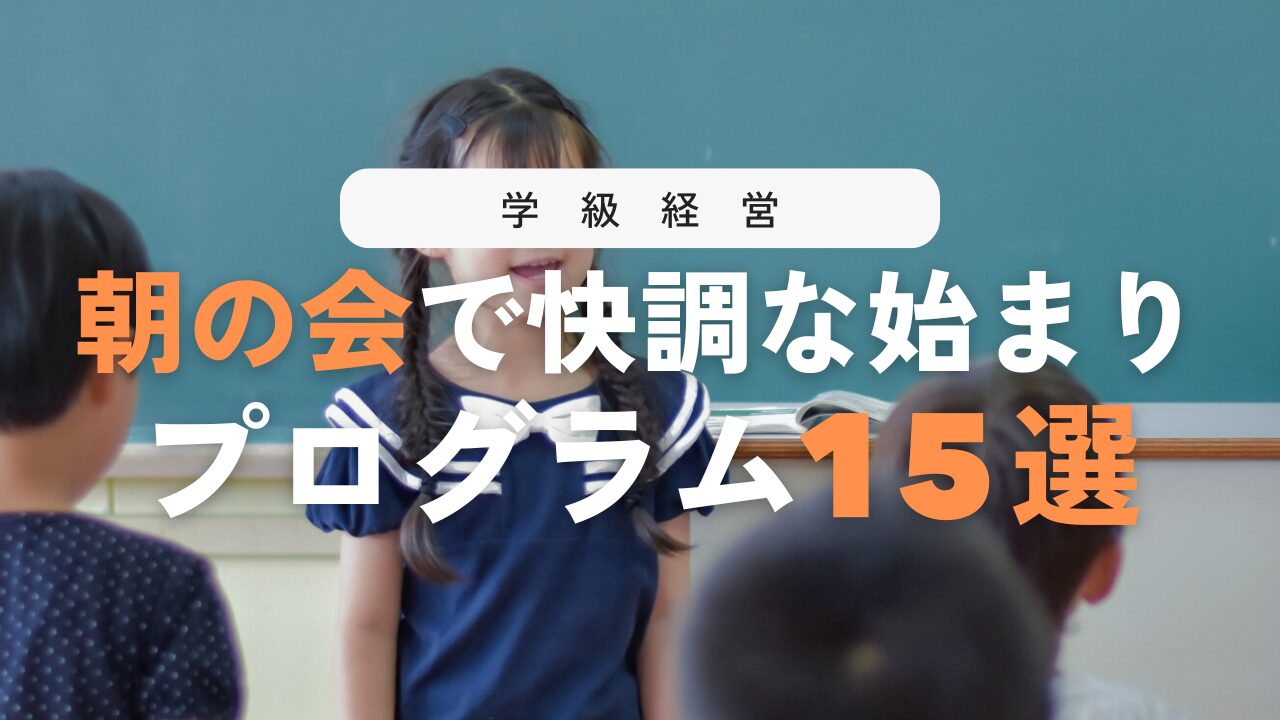【完全版】係活動の指導を丸ごと全部紹介!
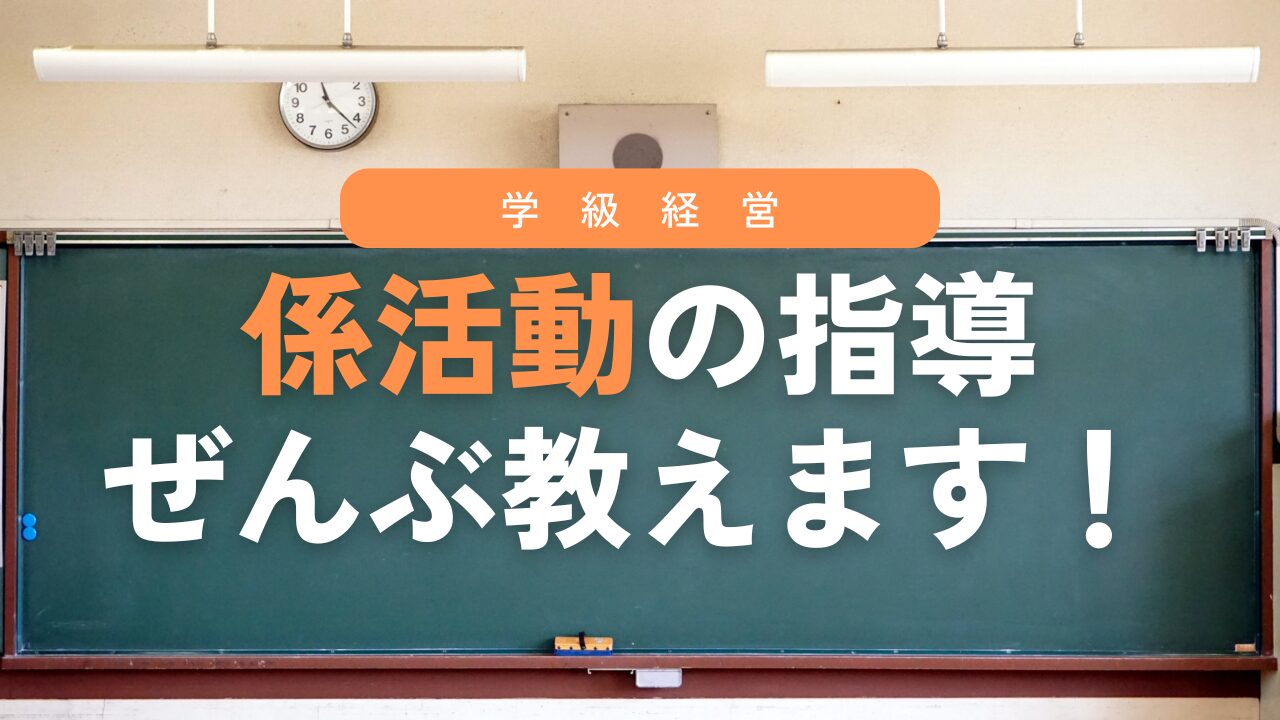
どうも、まっつーです。
学級で係活動をしていても、「子どもたちが自主的に動かない…」「自分(先生)の指示が増えてしまっている…」とお悩みではないでしょうか?
また、初めて担任を持つ先生や、これから先生になりたいと考えている人の中には、「どうのように係活動の指導をしたらいいんだろう?」と困っているかもしれません。
今回の記事は、子どもたちの自主性がぐんぐん育つ係活動の指導法を丸ごと全部ていねいに解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 子どもたちの係活動に取り組む姿勢が受け身で、やる気をあまり感じられない
- 特定の子ばかりが頑張っていて、他の子は進んで動かない
- 係を自主的にやらせたいけど、結局「〇〇やってね」と声をかけないと難しい
この記事を読めば、指導を通じて係活動を“ただの仕事”から“夢中になれる活動”へと進化させることができるようになります。
この記事を書いた人↓

係活動の意味とねらい
係活動とは、学級生活を共に楽しく豊かにするために児童が仕事を見いだし、創意工夫して自主的、実践的に取り組む活動のことです。
係活動は、先生から仕事を与えられるのではなく、子ども自身が「こんなことがあったらいいな」と感じたことを形にしていくのが特徴です。
たとえば、友達の誕生日を祝いたいと考え「誕生日係」を作るなど、学級をより良くする視点で役割を見いだすことが大切です。
活動中には、やり方を工夫し、自分たちで改善していく力が求められます。
また、「こうしたい」と思う気持ちを行動に移し、自分たちの手で実現していく実行力も育まれます。
係活動を子どもたちに説明するときは、

このクラスをもっと楽しく、過ごしやすくするために、自分のやりたい仕事をみんなで決めて、工夫しながら進めていく活動だよ。
と伝えるとわかりやすいでしょう。
係活動のねらい
係活動のねらいは、子どもたちが学級内の仕事を分担して自分たちの力で学級生活を楽しく豊かにすることにあります。
教室の飾り付けやイベントの準備、クイズの出題など、学級がより快適で楽しい場所になるような活動を、やりたい人・得意な人が集まって担当し、自主的に行うのが係活動です。
このような活動を通して、子どもたちは「毎日が楽しみになる」「安心して過ごせる」学級づくりに貢献し、一人ひとりが学級の主役として活躍することが目的となります。
また、「学級生活を豊かにする」とは、次の4つのことです。
こうした係活動の経験は、子どもたちにとって「自分の存在が役に立っている」という実感につながり、責任感・思いやり・学ぶ意欲など、生きる力の基礎を育てていくのです。
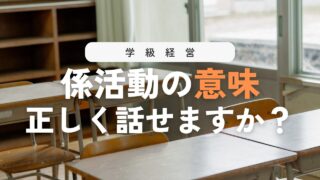
当番活動と係活動の違い
当番活動と係活動は、どちらも学級生活に欠かせない活動ですが、目的や進め方に明確な違いがあります。
当番活動の特徴
当番活動は、学級生活を円滑に運営するための「やらなければならない仕事」であり、日直・給食・掃除などの役割を全員で公平に分担し、決まった手順で行います。
短期間で交代することが多く、学級の基本的な機能を支える“縁の下の力持ち”のような存在です。
やりたい・やりたくないに関係なく、全員が責任をもって取り組む必要があります。
係活動の特徴
係活動は、学級生活を楽しく豊かにするための「やりたい仕事」で、新聞係や誕生日係、レクリエーション係など、子どもたちのアイデアから生まれる活動です。
「やりたい人」「好きな人」「得意な人」が集まって、自分たちで計画を立て、工夫を凝らしながら継続的に取り組みます。
内容や方法は子どもたちが自由に決められ、自分の良さを生かせることが特徴です。
- 当番活動…公平性と責任を学ぶ場
- 係活動…主体性と創意工夫を育む場
どちらか一方ではなく、両方をバランスよく取り入れることが、より良い学級づくりには欠かせません。
子どもたちにとって、「学級の一員として役に立っている」という実感を持てるような環境づくりが大切です。
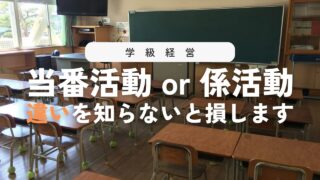
係活動を決める学級会の流れ5ステップ
係活動は、子どもたちが学級をより楽しく、豊かにするために行う「やりたい仕事」です。
この活動の決定には、先生が一方的に決めるのではなく、学級会で子どもたち自身が主体的に話し合って決めることが基本とされています。
学級会を活用することで、子どもたちは自ら考え、意見を出し合い、納得感をもって活動に参加することができます。
係活動を決める流れは、5つのステップに分けられます。
事前準備をする
事前準備として、「どんな係があるといいか?」を考えるきっかけとなる問いを子どもたちに投げかけたり、学級会の日時をあらかじめ伝えたりします。
これにより、子どもたちはアイデアを温めておくことができ、活発な話し合いにつながります。
議題を提案する
議題として「係を決めよう」を提案するとともに、改めて「なぜ係活動が必要か?」を考える時間を持ちます。
ただ単に係を割り振るのではなく、「自分たちで学級をより良くしていくための活動」であるという本質的な意義を共有することが重要です。
意見を交換する
子どもたちは係の名称だけでなく、その活動内容や必要性も合わせて発言するようにします。
発言が浅い場合は、司会の子や先生が「どんな活動をするの?」などと問いかけ、話を深めていきます。
意見を整理・調整する
似た内容の係はまとめたり、希望者が多すぎる場合は内容を分けて係を再編成したりする工夫が求められます。
司会の子が意見を整理するのが理想ですが、難しい場合は先生がさりげなくサポートします。
担当を決定する
最後は、それぞれの係を担当する子を決めます。
子どもたちは「自分のやりたい」「得意なことが活かせる」係を選ぶことが大切であり、納得して選べるよう支援します。
担当を決める方法としては、名前マグネットを使って希望を視覚的に示す方法や、タブレットなどICT端末を活用してデジタルで集計・調整する方法があります。
学級会を通して、「自分の意志で確かに選んだ」という実感を子どもに持たせることが重要です。
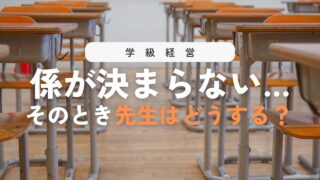
【厳選】係活動の一覧表30選
私が担任した学級の子どもたちが実際に取り組んでいたものや、他の先生方の実践事例の中から、特に厳選した「係活動30選」を一覧表にまとめました。
| 1 | 新聞係 | 学級のニュースや出来事を記事にまとめて新聞を作る。 |
| 2 | 誕生日係 | 友達の誕生日をお祝いするメッセージを用意したり、牛乳で乾杯の音頭をとったりする。 |
| 3 | レクリエーション係 | 休み時間にみんなで遊ぶものを企画したり、お楽しみ会を運営したりする。 |
| 4 | クイズ・なぞなぞ係 | クイズやなぞなぞを考えたり、みんなに出題したりする。 |
| 5 | イラスト係 | イラストを描いて教室に貼ったり、学級のキャラクターを創作したりする。 |
| 6 | ミュージック係 | 流行りの曲やおすすめの音楽を紹介する。 |
| 7 | スポーツ係 | 得意なスポーツを教えたり、ルールや歴史を紹介したりする。 |
| 8 | ブック係 | おすすめの本を紹介したり、読み聞かせをしたり、学級文庫を整理したりする。 |
| 9 | 飾り係 | 季節の行事に合わせた飾りや、教室の雰囲気が楽しくなるような飾りを作って、壁などに掲示する。 |
| 10 | マジック係 | トランプカードやコイン、カップ&ボールなどを使ってマジックを披露したり、教えたりする。 |
| 11 | ダンス係 | 動画を見ながらダンスを覚えて発表したり、みんなに教えたりする。 |
| 12 | 占い係 | 星占いやラッキーカラーなどを紹介する。 |
| 13 | 写真係 | タブレット等のカメラ機能を使って写真を撮り、教室に掲示する。 |
| 14 | お笑い係 | お笑いのコントを考えたり、モノマネを練習したりして、ネタを披露する。 |
| 15 | ゲーム係 | プログラミング系のアプリやサイトでゲームを制作し、発表する。 |
| 16 | 演奏係 | 得意な楽器(リコーダーや鍵盤ハーモニカだけでなく、習い事のピアノ、ギター、バイオリンなど)の演奏を披露する。 |
| 17 | 動画クリエイター係 | タブレット等のカメラ機能を使って動画を撮影し、編集して発表する。 |
| 18 | 演劇(ミュージカル)係 | 小道具を作ったり、演技の練習をしたりして、ミュージカルを披露する。 |
| 19 | ファッション係 | 流行のファッションや季節のコーディネートを紹介したり、服のデザインを考えたりする。 |
| 20 | 昔遊び係 | けん玉やお手玉、こま回しなど昔遊びの技を披露したり、教えたりする。 |
| 21 | 実験係 | 実験の様子を見せたり、観察した結果を写真やグラフなどで紹介したりする。 |
| 22 | 黒板係 | 【本来は当番活動】黒板を消すだけでなく、日付・日直の名前・時間割の記入、落とし物を黒板に掲示して知らせる、黒板消しクリーナーの清掃を行う。 |
| 23 | 配り係 | 【本来は当番活動】ノートやプリントを配るだけでなく、職員室から学級の荷物を運んだり、資料をまとめてホチキスでとじたり、他の係が作ったものを配ったりする。 |
| 24 | 保健係 | 【本来は当番活動】健康観察板を持ってくるだけでなく、体調が悪い友達を保健室へ連れて行ったり、欠席した友達へ明日の連絡やメッセージを書いたり、健康に関わる情報を知らせたりする。 |
| 25 | チェック係 | 【本来は先生の仕事】宿題や持ち物のチェックをするだけでなく、ロッカーや机の中が整理整頓されているか、電気が消えているか、人数が何人いるかなどをチェックする。 |
| 26 | 教室環境係 | 【本来は当番活動】カーテンや窓の開閉、電気の管理、棚の整理、当番表を回すなど、教室環境を整える。 |
| 27 | 体育係 | 【教科に関する仕事】準備運動や整理運動を先生と一緒にリードしたり、ラインカーで白線のコートを引いたり、体育館や校庭に倉庫の鍵を借りてきたりする。 |
| 28 | 生き物係 | 【本来は当番活動】教室で飼っている動物や育てている植物の世話をリードし、育てるコツを調べて紹介したり、友達にアドバイスをしたりする。 |
| 29 | 掲示係 | 【本来は当番活動】図工の授業や他の係活動で作った友達の作品を掲示したり、教室の掲示レイアウトを提案したり、オリジナルの掲示物をつくったりする。 |
| 30 | 荷物係 | 【先生の仕事】教材室から全員分の教材を運んだり、友達の荷物を運ぶ手伝いを行ったり、教室に落ちている荷物の持ち主を探したりする。 |
係活動を見る上で大切なことは、「名前がついているかどうか?」ではなく「実際にしっかり活動できているかどうか?」です。
「◯◯係」と名前がついていても、先生に言われないと動かない、仕事を放置しているようでは、意味のある係活動とは言えません。
たとえば「新聞係」の場合なら、発行予定が守られず、自主的に取りかかろうとせず、できあがった新聞も乱雑で読みづらいといった状況では、「名前だけの係」になってしまっています。
そのような状態を避けるためには、子どもたち一人ひとりが自分から考え、動こうとする姿勢が重要です。
※係活動の種類をもっとたくさん知りたい方は、次の記事がおすすめです!
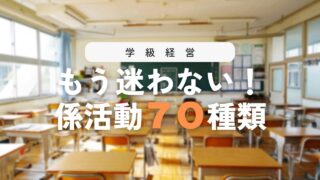
係活動と当番活動をどう見分ける?
係活動と当番活動の仕事を分ける際、【特別活動編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説では、「当番活動の仕事」や「教科に関する仕事」「先生の仕事の一部」を子どもに担わせないよう明記されています。
つまり、黒板消しや給食配膳などの当番的な役割や、先生の補助に近い仕事は、原則として係活動とは区別すべきとされています。
一方で、新聞係や誕生日係のように、学級を楽しく豊かにするために創意工夫しながら自主的に行う活動こそが本来の係活動とされます。
しかし、実際の学級では、当番活動や先生の手伝いを、子どもたちにとって「やりがい」や「楽しみ」となり、自発的・創造的に取り組んで、係活動へと発展することもあります。
そのため、過去に意欲的に取り組んでいた活動を「当番だからダメ!」「先生の仕事だから係ではありません!」と一律に否定するのではなく、子どもの思いや学級の実態に応じて柔軟に判断することが必要です。
係活動の進め方4ステップ
学級会で係が決まっても、すぐに全員が主体的に活動するとは限らず、時間が経つにつれて活動が停滞することがあるため、係活動を「オープン化」しましょう。
報告会や掲示物を活用して、係活動の様子や成果を学級全体に見える形で共有し、他の子や先生にも伝わるようにします。
また、学校全体や学年に向けても発信することで、活動の意義や達成感が深まり、意欲も高まります。
このように活動の様子を常にオープンにしながら、次の4つのステップで係活動を進めていきます。
活動計画を立てる
係が決まったからといって、すぐに活動を始めるのではなく、まずは「どんな活動をしていきたいのか?」「いつ・誰が・どのように行うのか?」「どんな準備や道具が必要か?」を、メンバーでしっかりと話し合う必要があります。
この準備の段階を丁寧に行うことで、子どもたちは自分の役割に対する責任感や主体性を持ちやすくなり、活動が形だけで終わらず、長く続く係活動へとつながっていきます。
係のポスターを作成する
係名やメンバー、目標、活動内容、予定などをわかりやすくまとめて掲示することで、活動の意義が可視化され、学級全体への発信にもつながります。
テンプレートを活用する方法と、子どもたちの創造力を生かした自由なデザインの方法があり、見た目の工夫も大切なポイントです。
実際に活動する
係活動を始めても、最初はうまくいかないこともありますが、それを学びの機会と捉え、改善していく姿勢が求められます。
新たな気づきやアイデアがあれば計画を柔軟に変更し、活動の幅を広げていきます。
また、教室や廊下に「係活動コーナー」を設けて情報を共有することで、周囲にも活動が伝わりやすくなります。
先生の役目は監視者ではなく、子どもたちを見守り応援する「サポーター」として寄り添っていきましょう。
ふり返りと改善をする
学期末に係のメンバーで話し合い、「うまくいったこと」「課題」「次にやってみたい工夫」などをまとめて共有することで、係活動の価値が高まります。
また、他の係のふり返りを聞くことで新たな学びにもなります。
さらに、「ありがとうカード」を使って感謝を伝え合うことで、子どもたちの達成感や人間関係が深まり、温かな学級づくりにもつながります。
このような4つのステップを通じて、係活動は形だけのものではなく、子どもたちが主体的に関わる意義のある活動へと育っていきます。

まとめ
今回は、子どもたちの自主性がぐんぐん育つ係活動の指導法を丸ごと全部紹介しました。
- 子どもたちが自分で「やりたい!」と思える係を見つけられるように、先生がきっかけをつくること
- ただ役割を与えるのではなく、「どうしたらもっと楽しくなるかな?」「もっと工夫できることはないかな?」と、子ども自身が考えて動けるように声かけや環境を整えること
- 係活動のふり返りや話し合いの場を取り入れて、「やって終わり」にならないようにし、次につなげる力を育てること
係活動はただの「仕事の分担」ではなく、子どもたちのやる気やアイデアが生きる、自分たちの学級をもっと楽しくするための大切な活動です。
この記事を読んだことで、子どもたちが自分から考え、自分から動き出すようになり、学級の中での役割に自信をもって取り組めるようになります。
先生の指示がなくても、子どもたちが「このクラスをもっとよくしたい」と思って工夫したり、協力したりするような、あたたかい学級が生まれるはずです。
今日からあなたも、子どもたちの自主性をぐんぐん引き出す係活動の名コーチになって、毎日の学級をもっと楽しく豊かな空間にしていきましょう!