【衝撃】学校でスポーツドリンクが禁止される理由とは?意外なリスクに注意
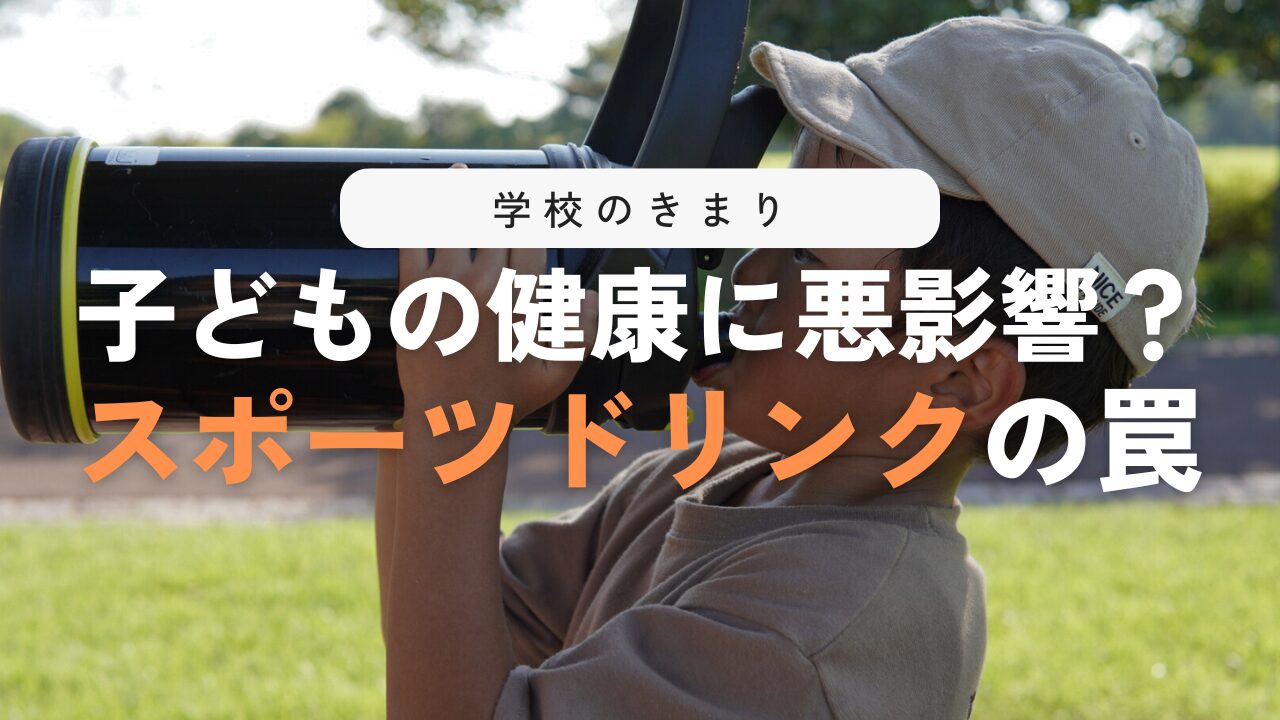
暑い日が続くと、「水筒にスポーツドリンクを入れて持たせたい!」という保護者の声をよく耳にします。
特に熱中症が心配な夏場は、「水やお茶だけでは心配…」「子どもが飲みやすいものを入れたい」という気持ちもよくわかります。
しかし、実際には多くの学校でスポーツドリンクの持ち込みが禁止されているのが現状です。

なんで?スポーツドリンクは体に良さそうなのに、どうして禁止しているのか教えてほしい。
今回の記事は、学校がスポーツドリンクを禁止している本当の理由をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 学校としてスポーツドリンクの持参を許可するか判断に迷っている
- 保護者から理由を聞かれたときに、しっかり説明したい
- 子どもの健康のためにスポーツドリンクの利用を考えたい
この記事を読めば、「なぜスポーツドリンクがダメなのか?」という理由がスッと理解できて、教育的にも医学的にも納得のいく対応ができるようになります。
この記事を書いた人↓

スポーツドリンクとは何か?

スポーツドリンクとは、運動などで汗をかいたときに、体の中から失われた水分や塩分、エネルギー(糖分)を効率よく補うために作られた飲み物のことです。
人は汗をかくと、水分だけでなく、体にとって大切な「ナトリウム(塩分)」や「カリウム」などの成分も一緒に出ていきます。
これが続くと、体の調子が悪くなったり、熱中症になるリスクが高まったりします。
そうしたときに、スポーツドリンクを飲むと、水分だけでなく、失われた塩分や糖分もすばやく体に取り入れることができるようになっています。
特に、気温の高い日に野外で長時間活動した後や、大量に汗をかいたときは、スポーツドリンクを少しずつ飲むことで、脱水症状や熱中症を予防する効果が期待できます。

やっぱりスポーツドリンクは体に良い飲み物なんだね。これからは毎日水筒に入れて、学校に持っていこうっと!

ちょっと待って!多くの学校では「水筒の中身については、水またはノンカフェインの麦茶やお茶のみで、スポーツドリンクを入れないでください」って通知を出しているはずだよ。
学校では、熱中症の心配になる夏以外にも、1年を通して水筒の持ち込みを許可をしている学校がコロナ禍をきっかけに増え、水分補給を推奨しています。
たしかに、スポーツドリンクは汗をかいたときの水分補給に効果的ですが、実は“普段から飲み続けることによるリスク”もあるのです。
これら3つのリスクについて、詳しく説明していきます。
①過剰な糖分(砂糖)の摂取

スポーツドリンクのペットボトルに書かれている100mLあたりの栄養成分表示の「炭水化物」のところに注目してみてください。
飲み物の炭水化物とは、ほとんど「砂糖(糖分)」のことです。
飲み物の炭水化物 = 砂糖(糖分)
様々なスポーツドリンクの栄養成分表示を見ると、100mLあたりの栄養成分である炭水化物が約4g〜7g程度になっています。
この炭水化物が5gだと仮定して計算すると、次のようになります。
一日の砂糖の摂取量の目安(2015年にWHOが定めた数値)は25gなので、500mLのペットボトル1本分のスポーツドリンクを飲んだだけで一日の砂糖の摂取量に達してしまいます。
500mLのスポーツドリンク=一日の砂糖の摂取量(25g)
1Lの水筒いっぱいにスポーツドリンクが入っていた場合は、一日の摂取量の2倍の50gにもなります。
スポーツドリンクのがぶ飲みも要注意
スポーツドリンクを一気にたくさん飲む“がぶ飲み”は、とても危険です。
なぜなら、大量の糖分が短時間で体に入ることで、血糖値(血液中の糖の量)が急激に上昇してしまうからです。
こうした状態が繰り返されると、体が疲れやすくなったり、集中力が落ちたり、将来的に肥満や生活習慣病のリスクが高まるリスクがあります。
ペットボトル症候群になる危険性
ペットボトル症候群(正式名:清涼飲料水ケトーシス)とは、スポーツドリンクや炭酸飲料、ジュースなど、ペットボトルに入った糖分の多い清涼飲料水を毎日のように大量に飲み続けることで起きる病気のことです。
症状としては、血糖値が異常に高くなり、強いのどの渇き、だるさ、吐き気、急激な体重減少、ひどい場合には意識障害を起こすこともあります。
スポーツドリンクは、運動後や熱中症の恐れがある場面で一時的に使うには効果的ですが、日常的に飲ませるものではありません。
特に学校生活では、水やノンカフェインのお茶を基本とし、スポーツドリンクは「必要なときだけ」にとどめることが大切です。
②歯に悪い(酸蝕症や虫歯)

スポーツドリンクが酸性の飲み物です。多くの市販のスポーツドリンクのpH値は3〜4程度であり、これは歯が溶け始めると言われるpH5.5よりもずっと低い数値です。
※※pHの値は、数字が小さいほど酸性が強くなります。
つまり、スポーツドリンクを飲むたびに、口の中が酸性に傾き、歯の表面(エナメル質)が少しずつ溶かされていく「酸蝕(さんしょく)」という現象が起きてしまうのです。
酸蝕症(さんしょくしょう)とは、すっぱい飲み物や食べ物にふくまれる“酸”で歯の表面が溶かされ、内側のやわらかい部分が出てしまい、歯がすりへったり、しみたりする病気のことです。
唾液が歯を守っているけれど…
私たちの口の中には、常に唾液が分泌されていて、食べ物や飲み物による酸を中和したり、歯を修復(再石灰化)したりする働きがあります。
しかし、スポーツドリンクをちょこちょこ飲む、あるいはダラダラ飲むと、口の中が長時間酸性の状態になり、唾液による中和や修復が間に合わなくなってしまうのです。
この状態が続くと、エナメル質がどんどん薄くなり、知覚過敏や虫歯、歯の変色などの原因になります。
特に小学生は、乳歯や生えたばかりの永久歯が多く、エナメル質がやわらかくて未成熟です。
そのため、大人以上に酸の影響を受けやすく、歯がすぐにダメージを受けてしまいます。
糖分が虫歯菌のエサになる
前述の通り、スポーツドリンクには多くの糖分が含まれています。
この糖分は、口の中にいる「ミュータンス菌(虫歯菌)」の大好物です。
糖分をエサにして、菌は酸を作り出し、それが歯を溶かして虫歯の原因になるのです。
つまり、スポーツドリンクは、
という、ダブルで歯にとって過酷な条件を作ってしまう飲み物なのです。
このような理由からも、日常的な水分補給には、糖分や酸を含まず、口の中と同じ中性の飲み物である「水」や「ノンカフェインのお茶」が適しています。
③金属製の水筒は注意!?

以前は、スポーツドリンクなどの酸性の飲み物を、ステンレス製の水筒に長時間入れておくと金属が溶け出すことがあり、中毒を起こしてしまう危険性がありました。
しかし、近年では金属製の水筒であっても内部にコーティングが施されている製品が出てきているので、スポーツドリンクを入れたからといって、金属が溶け出すことは少なくなってきています。
また、そもそもスポーツドリンクが非対応の水筒だったり、商品のWEBサイトや取扱説明書を確認せずに使用したりしている場合は、注意が必要です。
プラスチック製の水筒ならOK?

じゃあ、プラスチック製の水筒なら大丈夫だよね?
たしかに、プラスチック製の水筒なら金属が使われていないため、腐食の心配は全くありません。ただし、次のようなデメリットがあるので要注意です!
体育の授業など屋外で活動する際には、プラスチック製の水筒は保温性が低く、外気温の影響を受けやすいため、中の飲み物がすぐに熱くなってしまいます。
また、子どもたちが学校で使用する際には、落としたり、どこかにぶつけたりして壊れてしまう可能性も高くなります。
そのため、プラスチック製のボトルは推奨しません。
学校生活の大半は“座って学ぶ時間”

学校の時間割を見ると、一日のほとんどは教室内での授業、つまり座学(座って学ぶ授業)です。
文部科学省が定める標準授業時数によれば、一週間における体育の授業時間は学年によって異なりますが、おおよそ2〜3コマ(1コマ=小学校は45分、中学・高校は50分)程度です。
つまり、体育の授業による運動によって汗をかく時間は、一週間のうちわずか2〜3時間程度。それ以外の時間は教室で座って授業を受けていることがほとんどです。
また、教室や体育館にはエアコンや扇風機などの冷房設備が整えられている学校も多く、体温の上昇や過度な発汗が起きにくい環境になってきています。
このように、学校生活の中心が「座って学ぶ活動」である以上、日常的にスポーツドリンクを飲む必要はほとんどないというのが実態です。
飲みたいときは必要な場面で
学校によっては、保護者の強い要望などを受けて、スポーツドリンクの持参を一部許可しているところもあります。
しかし、そのような場合であっても、「いつでも自由に飲ませる」ではなく、「場面を選んで適切に飲む」ことがとても重要です。
たとえば、次のような状況では、一時的な対応としてスポーツドリンクを取り入れるのが効果的です。
ただし、これらの場面でも注意すべきなのは、飲ませ方や量・持たせ方の工夫です。
このように、「いつ飲むか?」「どのくらい飲むか?」「他の水分とどう使い分けるか?」といった工夫をすることで、糖分や酸による健康リスクを減らしつつ、脱水や熱中症の予防にもつなげることができます。
まとめ
今回は、学校がスポーツドリンクを禁止している本当の理由について紹介しました。
- スポーツドリンクには多くの糖分や酸が含まれており、虫歯や酸蝕症、生活習慣病のリスクがあること
- 学校生活の大半は屋内での座学中心であり、日常的にスポーツドリンクを必要とする環境ではないこと
- 金属製やプラスチック製の水筒の取り扱いに注意すること
この記事を読んだことで、学校がスポーツドリンクを禁止しているのは、ルールでしばるためではなく、子どもたちの健康を守るためだということが理解できたと思います。
「スポーツドリンク=体に良いもの」と思っている方も多いですが、それは“運動後の一時的な補給”という条件付きの話です。
学校生活では、水やノンカフェインのお茶が最も安全で安心な水分補給になります。
スポーツドリンクを完全に否定する意図は全くありません。必要な場面で、適切に使い分けることが大事なのです。
これからの季節、特に暑さが増す中での水分補給はとても重要ですから、正しい知識をもとに子どもたちを健康を守っていきましょう。

