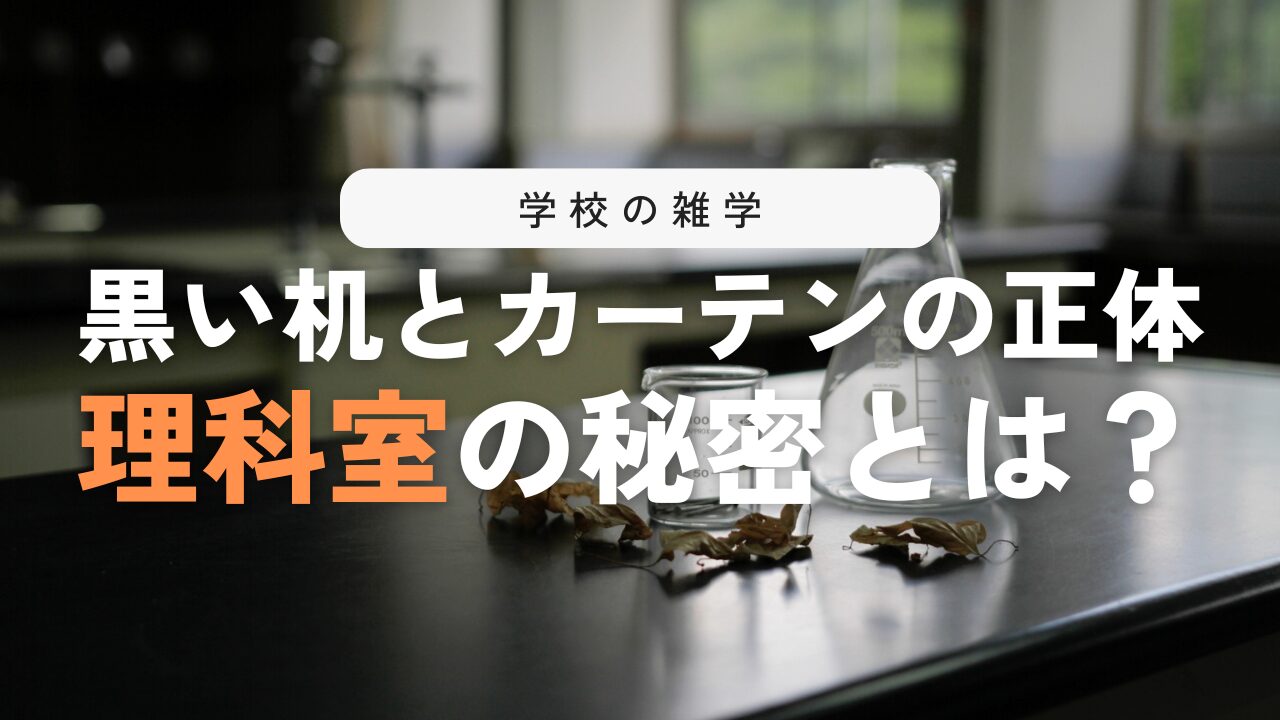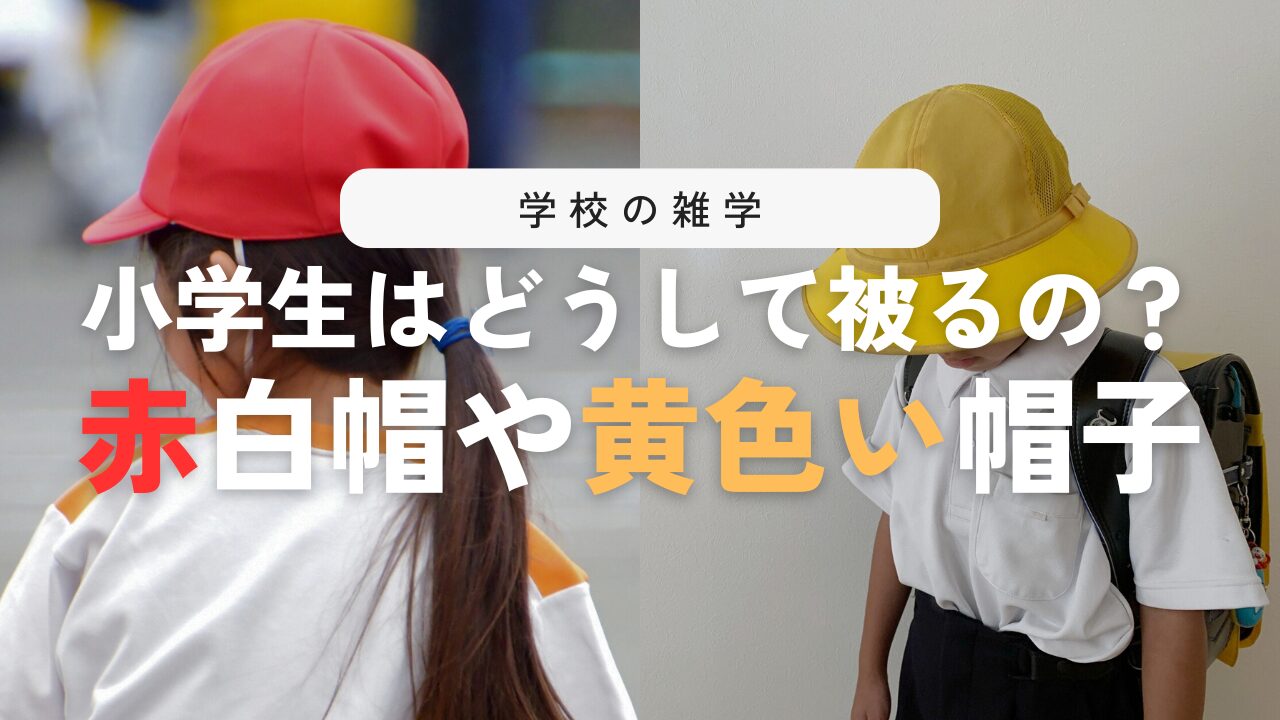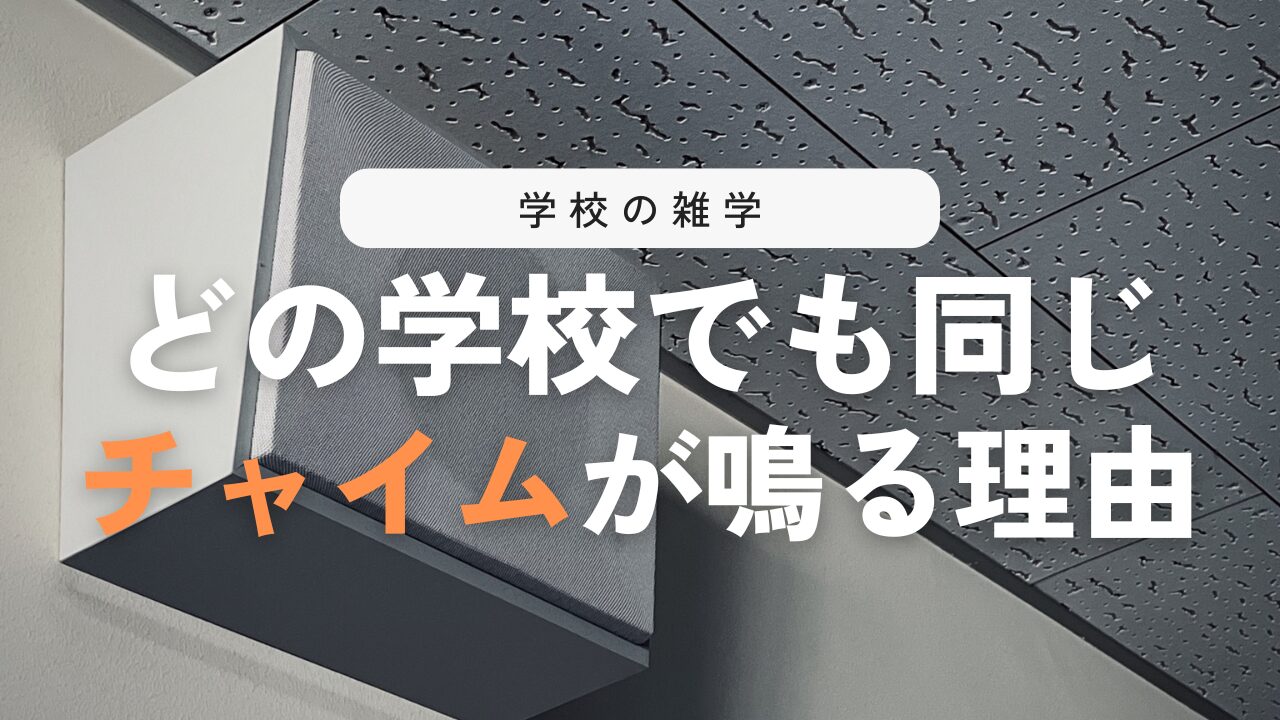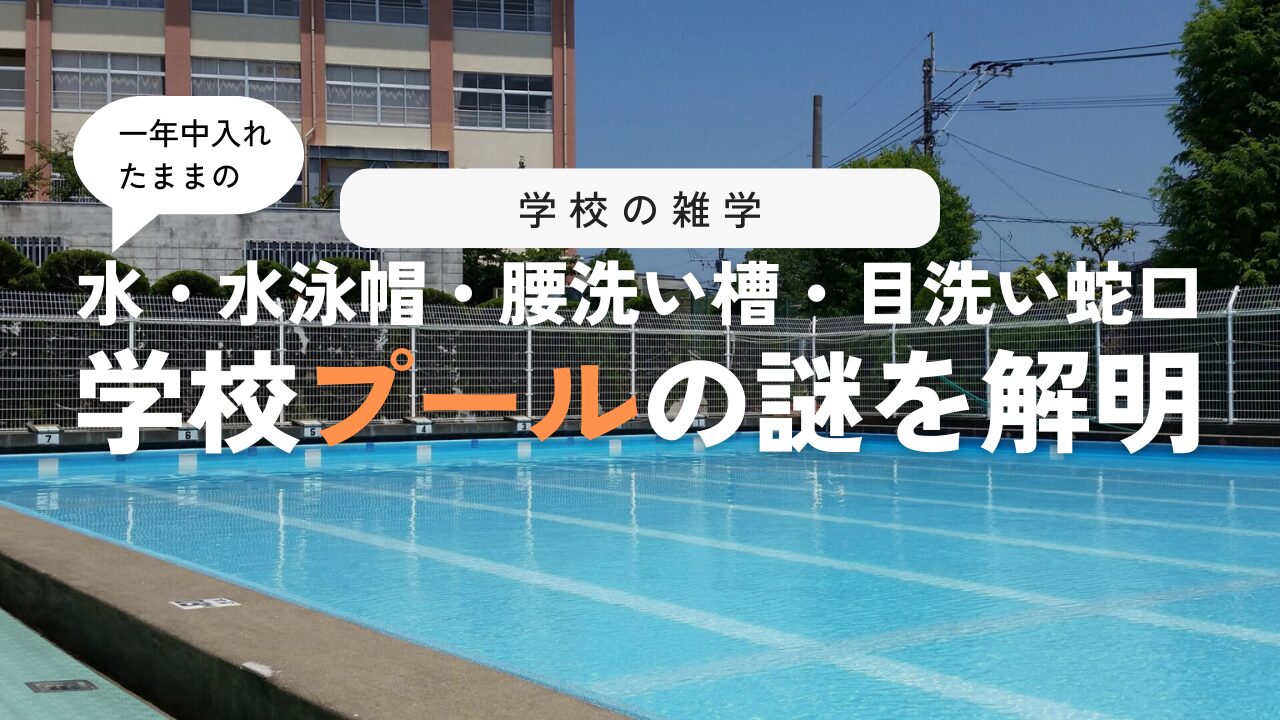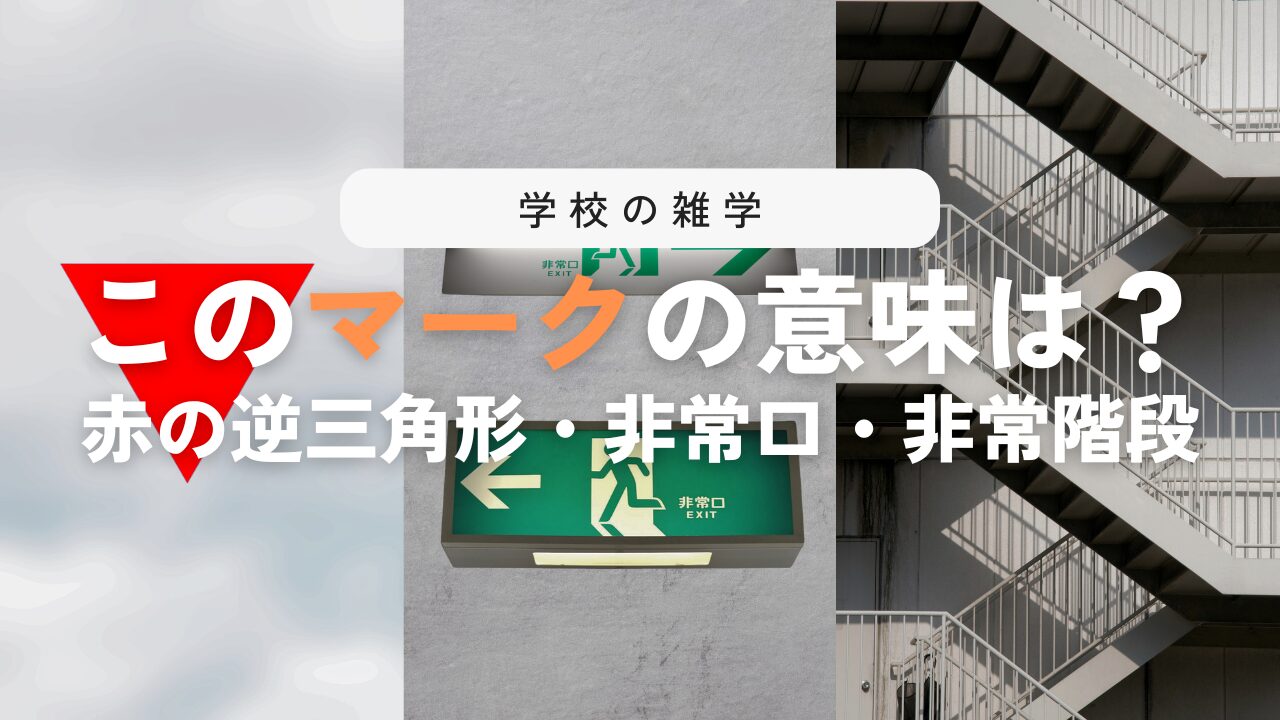【学校の雑学①】なぜ小学生の鞄はランドセルなのか?法的な義務は?

どうも、まっつーです。
あちこちで、カラフルなランドセルを背負った小学生たちの姿を見かけますが、「なぜ小学生はみんなランドセルを使うの?」と、ふと疑問に思ったことはありませんか?
今回の記事は、小学生がランドセルを使用している理由とその歴史的な背景をわかりやすく解説します!
この記事を書いた人↓

ルーツは軍隊!?ランドセルの始まり

ランドセルの原型が日本にやってきたのは、なんと江戸時代の幕末。当時、幕府は西洋式の軍隊制度を取り入れ始めていました。
兵士たちが使っていたのは、オランダから輸入された軍用の背負い袋(背のう)で、丈夫で両手が空くという便利な特徴がありました。
オランダ語でこれを「ランセル(ransel)」と呼んでいたのですが、日本ではそれがなまって「ランドセル」という言葉になったとされています。
明治時代になると、ランドセルの形は通学用にも使えるように工夫されていきます。
「平等な教育」を目指した学習院の決断

ランドセルが学校の通学かばんとして使われ始めた最初のきっかけは、明治時代に開校した学習院初等科にあります。
当時、学習院に通う子どもたちの中には、馬車や人力車で登校したり、使用人に荷物を運ばせたりする子も多く、家庭の経済格差がそのまま学校にも持ち込まれていました。
そこで学習院が大切にしたのは、「学校ではみんな平等であるべきだ」という教育の理念です。
明治18年、学校は「子どもが自分で荷物を運び、自分で登校すること」をルールとし、家庭の事情に左右されない、平等な学校生活を目指したのです。
このときに採用されたのが、軍隊で使われていた背負い袋、つまりランドセルでした。
背中に背負って両手が自由に使える、安全で機能的なカバンとして、ランドセルは通学スタイルにぴったりだったのです。
天皇のご入学が広まるきっかけに

このランドセルを一躍有名にしたのが、明治20年(1887年)、当時皇太子だった大正天皇が学習院に入学されたときのことです。
初代内閣総理大臣・伊藤博文が、お祝いとして箱型の通学かばんを贈りました。
これが、現在のランドセルに近い「しっかりとした箱型」の始まりだとされています。
その後、明治23年には素材が黒い革製に統一され、明治30年には形や大きさも細かく決められました。
こうして完成したのが「学習院型ランドセル」は、100年以上経った今でも、基本的なデザインをほとんど変えずに受け継がれているのです。
戦後、そして全国へ

戦前のランドセルは、高級品でした。革製で丈夫な分、値段も高く、地方や一般家庭ではなかなか手が出ませんでした。
そのため、風呂敷や布製のバッグ、ショルダーバッグなどが通学かばんとしてよく使われていました。
しかし、昭和30年代の高度経済成長期になると、日本の暮らしが少しずつ豊かになり、ランドセルが全国の小学校で広く使われるようになっていきます。
素材も革だけでなく、合成皮革や軽量素材が登場し、より安く、より丈夫で、より軽くなったことで、ランドセルは一般家庭にも普及していったのです。
最近では、赤やピンク、水色やラベンダーなど、さまざまな色やデザインのランドセルが登場し、子どもたちの好みに合わせた選び方もできるようになりました。
反射材がついていたり、負担が少ない肩ベルトの構造になっていたりと、安全性や使いやすさにも改良が加えられています。
ランドセルの法的な義務は?

「ランドセルって、法律で決まっているの?」「リュックじゃダメなの?」という疑問を、保護者の方からたまに受けることがあります。
結論…ランドセルの使用は法律では義務づけられていません。
文部科学省も、都道府県や市区町村の教育委員会も、各小学校も、「通学カバンは必ずランドセルでなければならない」と決めているわけではありません。
つまり、ランドセルは“選択肢のひとつ”であり、絶対条件ではないのです。
ところが、ほとんどの小学生がランドセルを使って登校しています。
なぜなら、「小学生といえばランドセル」という空気や文化が根づいていて、ランドセルを使うことが当然と感じられているからです。
そのため、結果的にほとんどの家庭がランドセルを選ぶことになるのです。
まとめ
今回は、小学生がランドセルを使用している理由とその歴史的な背景について紹介しました。
- ランドセルのルーツは軍隊にあり、安全性や機能性を重視した背負い袋(背のう)が起源であること
- 明治時代の学習院で「学校ではみんな平等であるべきだ」という理念のもとにランドセルが導入され、子どもが自分の荷物を自分で持って登校する文化が広がったこと
- ランドセルの使用は法的な義務ではないにもかかわらず、「小学生といえばランドセル」という社会的な空気や文化が今でも強く根づいていること
この記事を読んだことで、ランドセルが単なる通学かばんではなく、日本の教育文化や社会的な価値観が詰まった象徴的なアイテムであることがおわかりいただけたと思います。
このランドセルの雑学は、学級の子どもたちや疑問を持っている保護者に向けて、話のネタとしてぜひ紹介してみてください。
ちょっとした会話のきっかけにもなり、学びの幅が広がるはずです。