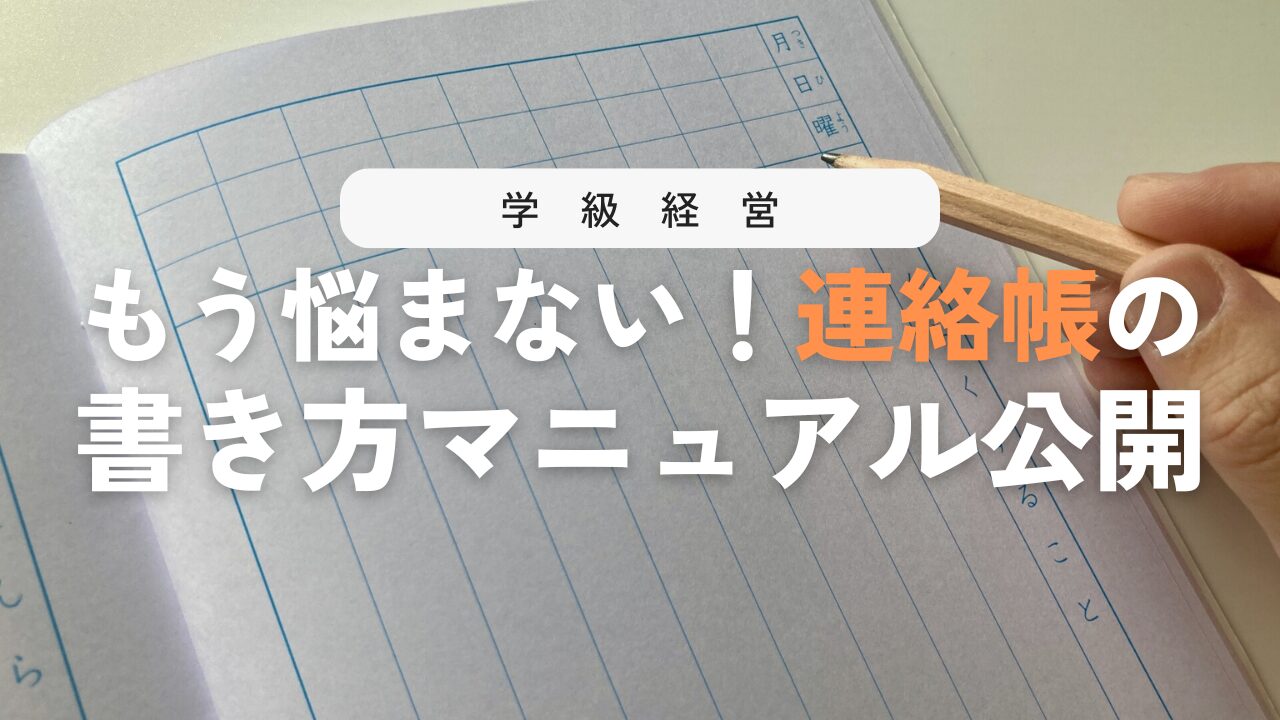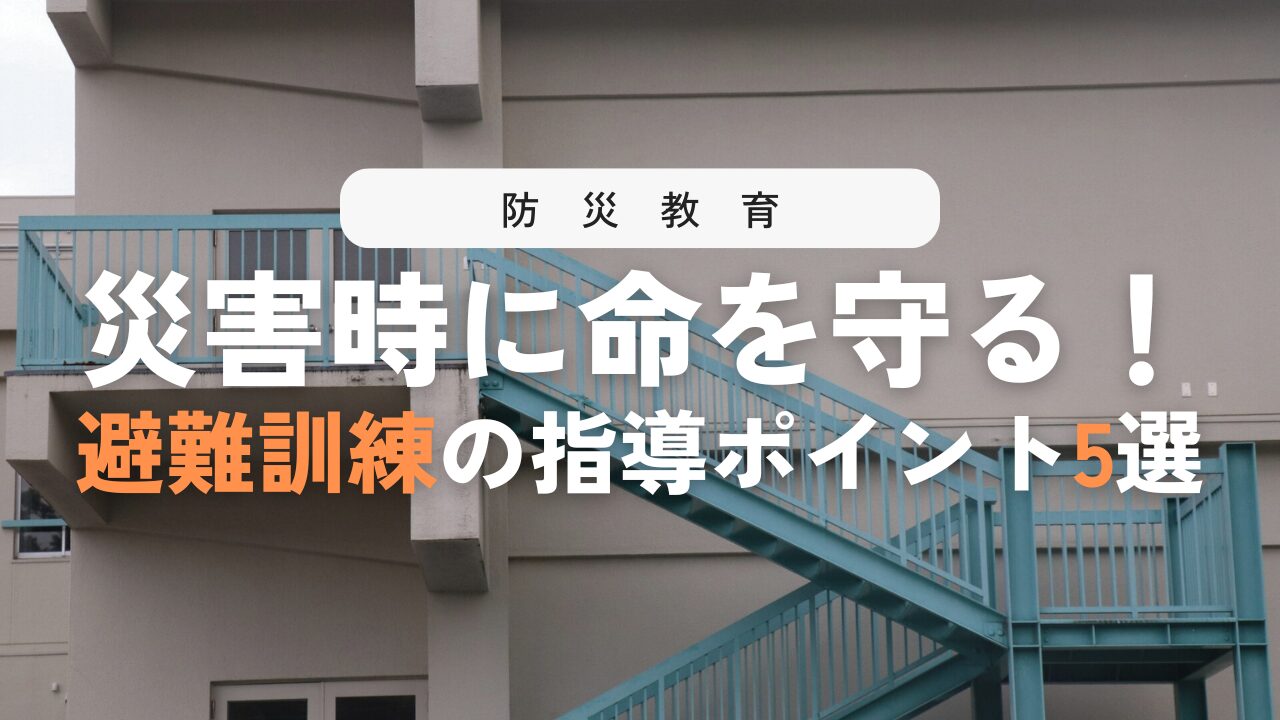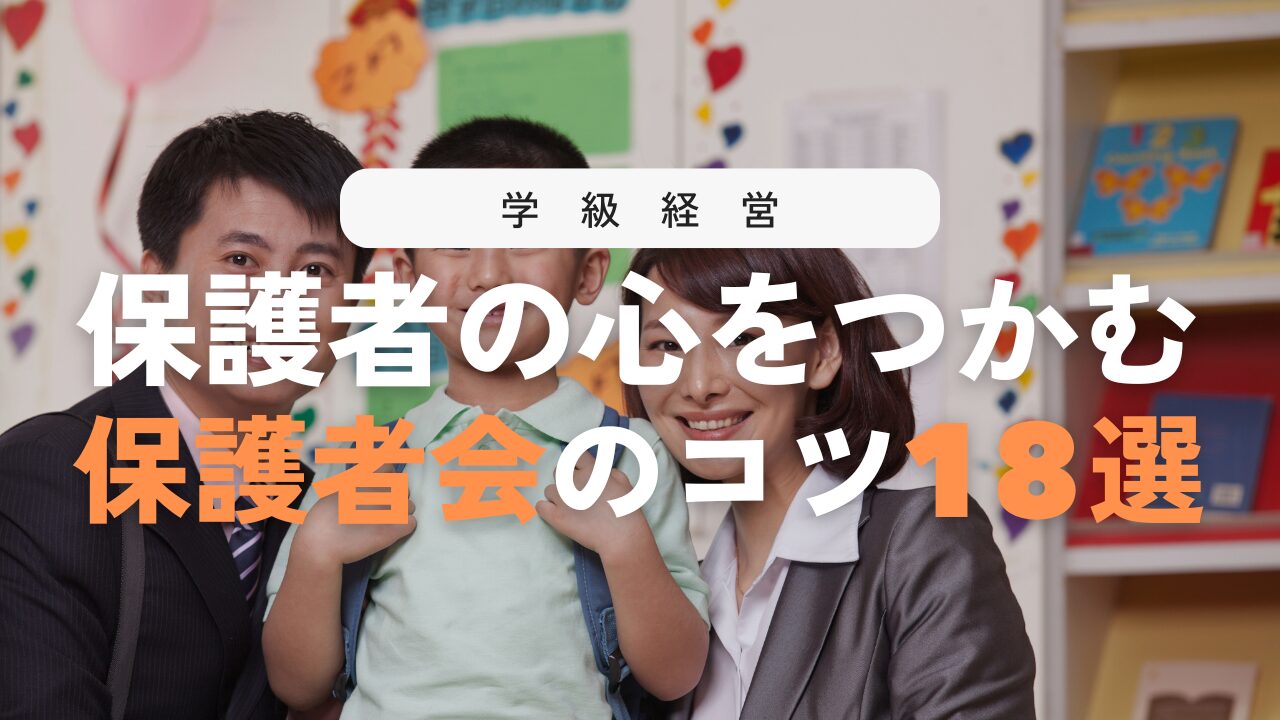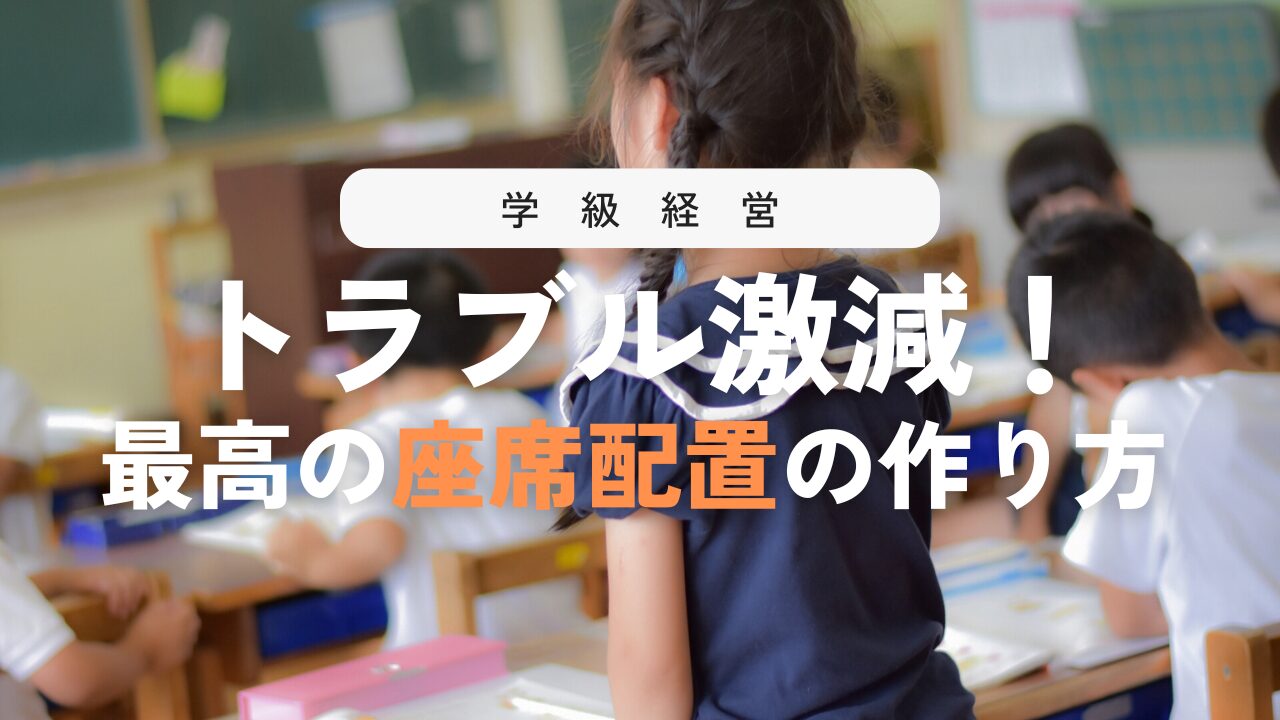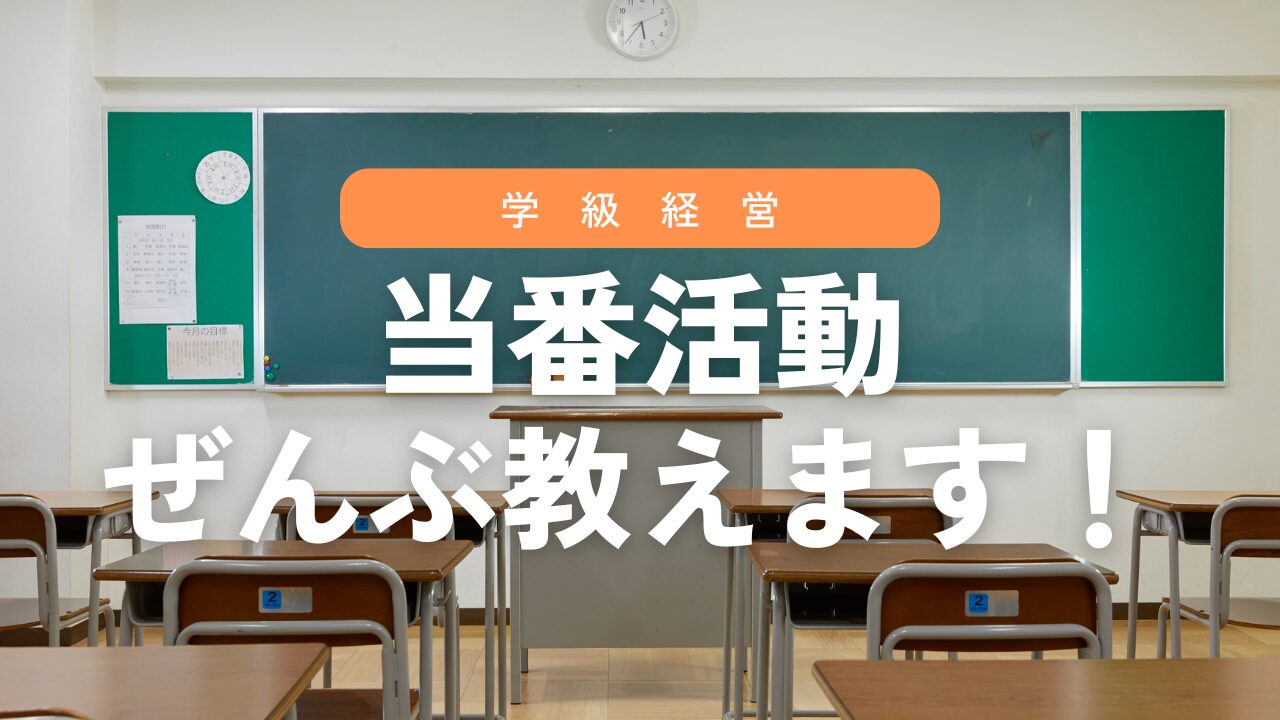【保存版】一人一役当番60選一覧表!学級が回る仕事を紹介

どうも、まっつーです。
学級経営をしている中で、「子ども全員に役割を持たせたいけど、当番がうまく回らない…」「“一人一役”ってよく聞くけど、具体的にどんな当番があるの?」と悩んでいませんか?
実は、「一人一役当番」をうまく活用すれば、子どもたちの主体性がグンと伸びて、学級の一体感も高まります。
今回の記事は、学校の現場で本当に使える一人一役当番60選を一覧表にしてまとめました!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 子どもたち全員が活躍できる学級にしたい
- 当番のネタがマンネリ化して困っている
- 一人一役当番の実践的なアイデアを学びたい
- どんな一人一役当番があるのか知りたい
この記事を読めば、一人ひとりが自分の力を発揮できる、温かくて協力的な学級づくりが実現できるようになります。
この記事を書いた人↓

一人一役当番の一覧表60選
「一人一役の当番をいくつ用意するか?」「どのような内容の当番をつくるか?」といったことは、学級の人数や、子どもたちの発達段階(年齢や学年)に応じて柔軟に考える必要があります。
そこで、私が担任した学級の子どもたちが実際に取り組んでいた当番活動に加え、他の先生方の実践事例も参考にしながら、「一人一役当番60選」として一覧表にまとめました。
当番活動を決める際のヒントとして、ぜひご活用ください。
| 当番の名前 | 主な活動内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 鉛筆削り当番 | 鉛筆削りに溜まった削りカスを捨てる。 |
| 2 | 学級文庫当番 | 学級にある本棚にすべての本が揃っているか数えたり、整理したりする。 |
| 3 | 整理整頓チェック当番 | ロッカーや棚の中を確認し、物が乱雑に置かれている場合は注意を促したり、整理したりする。 |
| 4 | 餌やり当番 | 教室で飼っている生き物の餌やりをする。 |
| 5 | 掲示当番 | 教室の壁に絵や観察カードを掲示したり、画びょうが外れそうなところがないかを確認したりする。 |
| 6 | 落し物当番 | 落とし物箱の中身を確認したり、持ち主を探したりする。 |
| 7 | 電気当番 | 教室や体育館の電気をつけたり、消したりする。 |
| 8 | 窓当番 | 窓を開閉し、教室の空気を入れ替えたり、帰りの会の後で窓を施錠したりする。 |
| 9 | ストロー配り当番 | 給食時に牛乳のストローを配ったり、ストローの袋などのゴミを回収したりする。 |
| 10 | 水やり当番 | 学級園や学級の植木鉢に水やりをする。 |
| 11 | 花びん水かえ当番 | 教室に飾ってある花瓶の水を取り替える。 |
| 12 | 日付・名前当番 | 黒板に翌日の日付や日直当番の名前を書く。 |
| 13 | 時間割当番 | 黒板に翌日の時間割を書く。 |
| 14 | ゴミ捨て当番 | 掃除後、ゴミ袋をゴミ捨て場に持っていく。 |
| 15 | 黒板1当番 | 1時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 16 | 黒板2当番 | 2時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 17 | 黒板3当番 | 3時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 18 | 黒板4当番 | 4時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 19 | 黒板5当番 | 5時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 20 | 黒板6当番 | 6時間目の授業後に黒板をきれいにする。 |
| 21 | プリント配り当番 | お便りや学習プリントを配る。 |
| 22 | ノート配り当番 | 集めた学習用のノートを配る。 |
| 23 | 宿題チェック当番 | 宿題の提出を確認する。 |
| 24 | 提出物チェック当番 | 宿題以外の提出物を確認する。 |
| 25 | 健康観察当番 | 健康観察板を取りに行ったり、元の場所に返却したりする。 |
| 26 | 給食の献立当番 | 給食の献立をみんなに知らせたり、給食室の前にある見本や献立表を見て、食器の配置を給食当番に伝えたりする。 |
| 27 | 音楽CD当番 | 朝の会や帰りの会で音楽の練習をするときは、CDを準備して音楽を流す。 |
| 28 | チョーク当番 | チョークの本数を確認し、足りない場合は事務室や保管庫まで取りに行って補充する。 |
| 29 | 遊び道具当番 | 休み時間に使うボールなどの遊び道具の数を確認し、空気が抜けていれば入れる。また、雨の日用のカードゲームやボードゲームを整理する。 |
| 30 | 配膳台当番 | 給食の配膳台を出したり、片付けたりする。 |
| 31 | 誘導当番 | 教室や廊下でみんなを整列させ、先頭に立って校庭や体育館、特別教室まで誘導する。 |
| 32 | カギ当番 | 体育館や体育倉庫、家庭科室、理科室などのカギを取りに行き、使い終わったら元の場所に戻す。 |
| 33 | 机整列当番 | 帰りの会の後、みんなの机をまっすぐ整える。 |
| 34 | イス整列当番 | 帰りの会が後、みんなのイスを机の中にきちんとしまう。 |
| 35 | 加湿器当番 | 朝、加湿器の水を取り替えて電源を入れる。※冬限定 |
| 36 | 温度管理当番 | 教室の温度を温度計で確認したり、冷暖房や扇風機の電源を入れたりする。 |
| 37 | 保健当番 | けがをした友達に絆創膏をはるなどの簡単な手当てをしたり、保健室まで付き添ったりする。 |
| 38 | 名札当番 | 名札を着用しているか声をかけたり、帰りの会で名札入れにしまっているか確認したりする。 |
| 39 | タイマー当番 | テストなどのタイマーをセットしたり、アラームが鳴ったら止めたりする。 |
| 40 | 連絡帳チェック当番 | 翌日の予定を書いた連絡帳の提出を確認する。 |
| 41 | ハンカチ・テイッシュ当番 | ハンカチとティッシュをきちんと持ってきているか確認する。 |
| 42 | 音楽当番 | 音楽の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。学期の準備や片付けの手伝いをする。 |
| 43 | 図工当番 | 図工の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材の準備や片付けの手伝いをする。 |
| 44 | 国語当番 | 国語の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |
| 45 | 社会当番 | 社会の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |
| 46 | 算数当番 | 算数の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |
| 47 | 理科当番 | 理科の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。実験準備を手伝う。 |
| 48 | 体育当番 | 体育の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。ラインカーを使って校庭に白線を引く。 |
| 49 | 家庭科当番 | 家庭科の先生(専科教員・教科担任)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。ミシンや調理道具の準備を手伝う。 |
| 50 | 外国語当番 | 外国語の先生(専科教員・教科担任・ALT)から連絡を受け取り、みんなに知らせる。教材を運ぶなどの準備を手伝う。 |
| 51 | マグネット当番 | 名前が書かれたマグネットを整理したり、集会や全校朝会がある日には、黒板に「集会」や「全校朝会」と書かれたマグネットを貼って知らせたりする。 |
| 52 | タブレット保管庫当番 | タブレットを保管庫に整然と片付けられるように、入れる順番を指示したり、電源プラグが正しく接続されて充電されているかを確認したりする。 |
| 53 | フック当番 | 教室や廊下のフックに体育着や上ばき袋がきちんとかかっているかを確認したり、金曜日には忘れずに持ち帰るよう声をかけたりする |
| 54 | お助け当番 | 欠席した人のために、当番の仕事を引き受けたり、翌日の学習予定や持ち物を連絡カードに書いたりする。 |
| 55 | 手洗い場(水道)当番 | 手洗い場(水道)のハンドソープが無くなっていたら補充したり、蛇口の向きを正しく戻したり、水が出しっぱなしになっていないかを確認したりする。 |
| 56 | 掃除用具当番 | ほうきや雑巾などの掃除用具がきちんと片付けられているか確認したり、壊れている場合は新しいものに取り替えたりする。 |
| 57 | お便り当番 | 職員室近くにある学級用の棚からお便りを取り、教室まで運んで教卓の上に置く。 |
| 58 | カーテン当番 | 天気や日差しの様子を見て、カーテンを開けたり閉めたりする。 |
| 59 | 水そう当番 | 教室で飼っているメダカなどの水生生物の水槽をきれいに洗ったり、水を入れ替えたりする。 |
| 60 | 一年生のお手伝い当番 | 一年生がスムーズに朝の準備ができるように、持ち物の整理や身支度の確認、困っている子への声かけなどを行う。※期間限定 |
まずは、係活動の担当者や役割を先に決めておきましょう。
そのうえで、一人一役当番の内容を考えていくと、役割が重複せずに分担がしやすくなります。
また、仕事内容の負担の大きさや学級の人数によっては、ひとつの当番を複数人で担当したり、交代制にしたりする工夫も必要です。
無理なく続けられる体制を整えることで、子どもたちが安心して役割を果たし、「自分も学級の大切な一員なんだ」と感じられるようになります。
一人一役当番の注意点と弊害
一人一役当番を導入することで、学級の子どもたち全員が何らかの仕事を受け持ち、日々の学級生活を支える役割を担うことができます。
この取り組みは、責任感や協力の大切さを学びながら成長できる貴重な経験になりますが、実施にあたっては次のような2つの弊害も存在します。
- “気づき”や“自発的な行動”を阻む
- 自立の芽を摘んでしまう
①“気づき”や“自発的な行動”を阻む
子どもたちの“気づき”や“自発的な行動”を阻んでしまう可能性があるということです。
こうした場面では、その場にいる子がすぐに判断して動けることが、「当番の仕事だから」という理由で止められてしまいます。
その結果、「自分で気づいて、すぐに動けることが素晴らしい」という感覚よりも、「人の役割があるなら、自分は動かずに待つべきだ」という受け身の姿勢が育ってしまう恐れがあるのです。
②自立の芽を摘んでしまう
一人一役当番の一つとして、「ロッカーの整理係」や「フックの整理係」などを設定する場面があるかもしれません。
たしかに、整理整頓を呼びかけたり、全体の環境を整える役割として考えると、こうした係も一見すると有効に思えます。
しかし注意したいのは、本来ロッカーやフックの整理は、子ども一人ひとりが自分自身の持ち物として責任をもって管理すべきことだという点です。
もしそれを他の誰かに任せることが日常になってしまうと、「自分のことは自分でやる」という自立の芽を摘んでしまうことにもなりかねません。
まとめ
今回は、学校の現場で本当に使える一人一役当番60選を一覧表にして紹介しました。
- 子ども一人ひとりに“役割”があることで、自分も学級の一員だと感じられるようになること
- 当番の内容は、学級の人数や子どもの実態に合わせてアレンジすることが大切であること
- 子どもたちの自発的な行動や自立心の育成を妨げることのないよう、柔軟に対応すること
この記事を読んだことで、子どもたち全員が自然と学級に関わり、支え合いながら生活できる一人一役当番のアイデアが、さらに広がったのではないでしょうか。
この記事で紹介した60の当番の内容は、どれも現場で実際に使われてきた実践例ばかりです。
今日からさっそく取り入れて、子どもたちが安心して、楽しみながら役割を果たせる学級づくりに役立ててください。