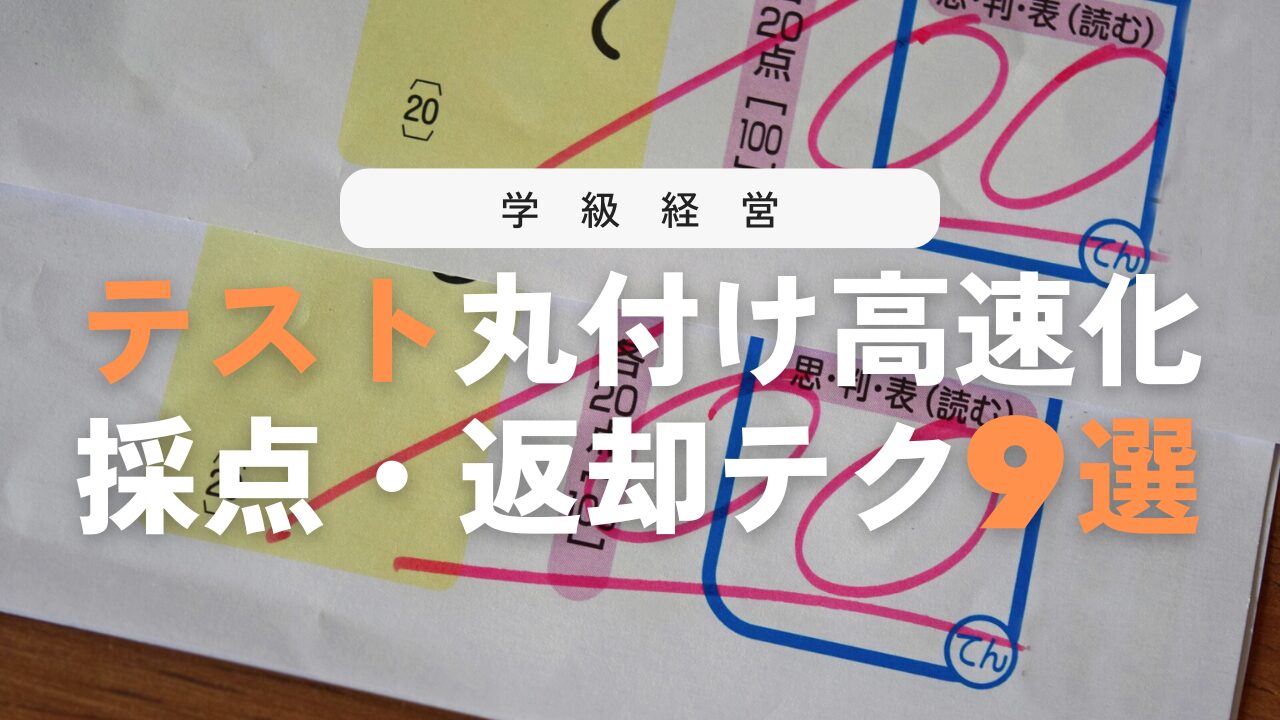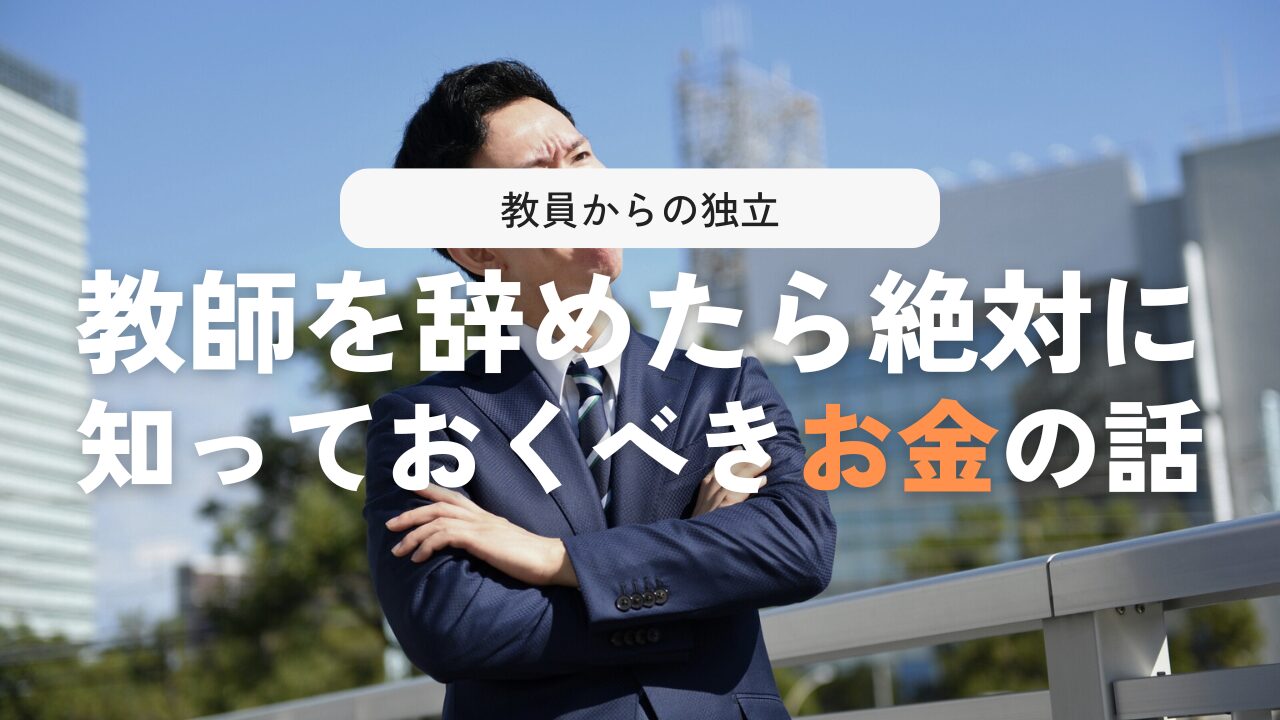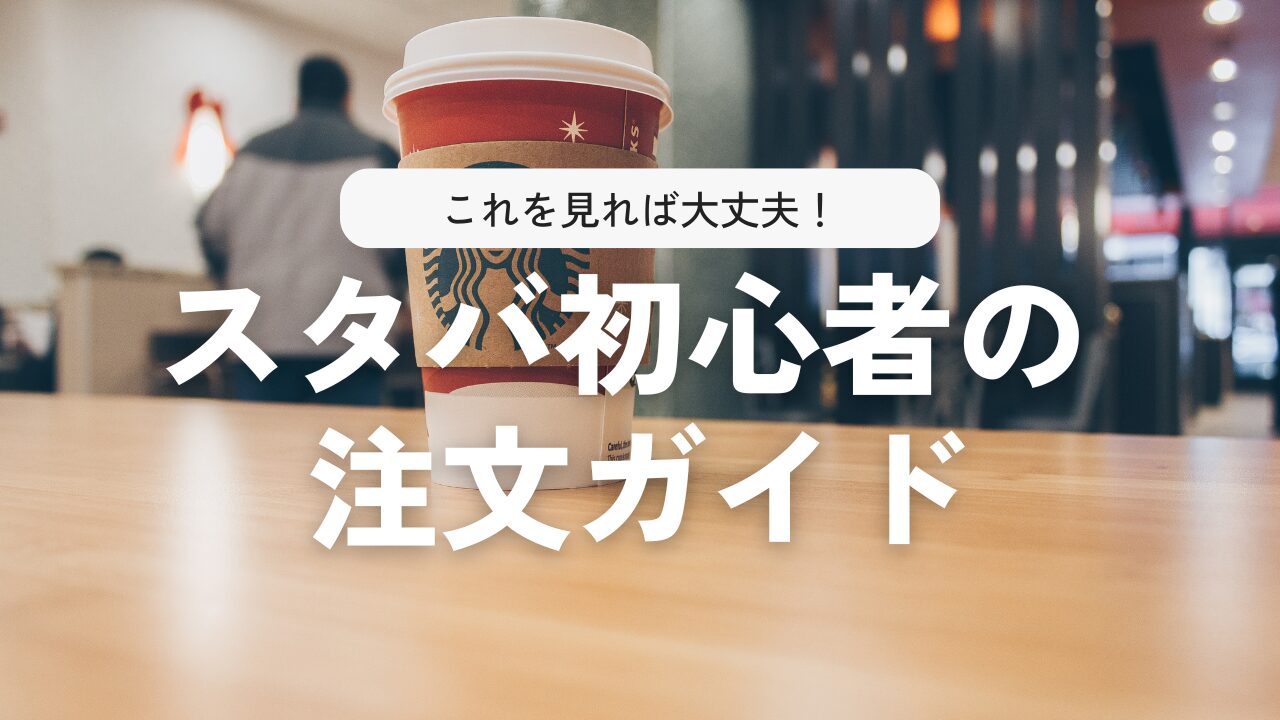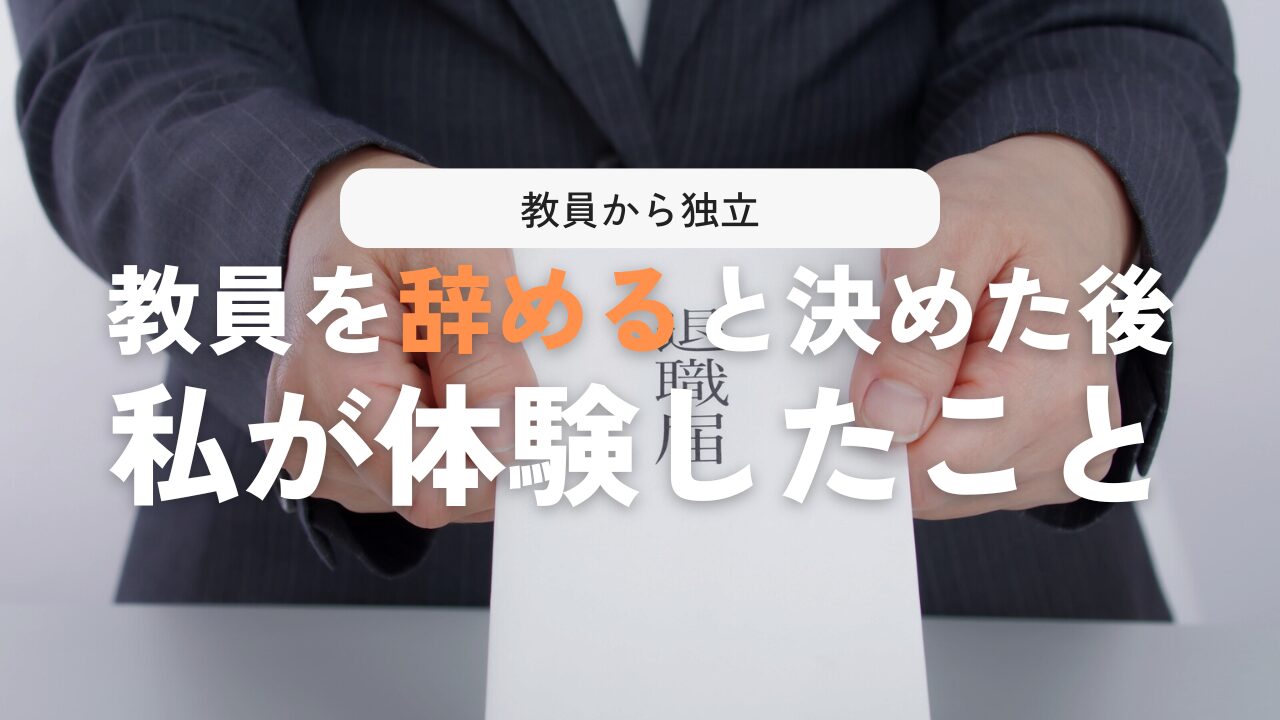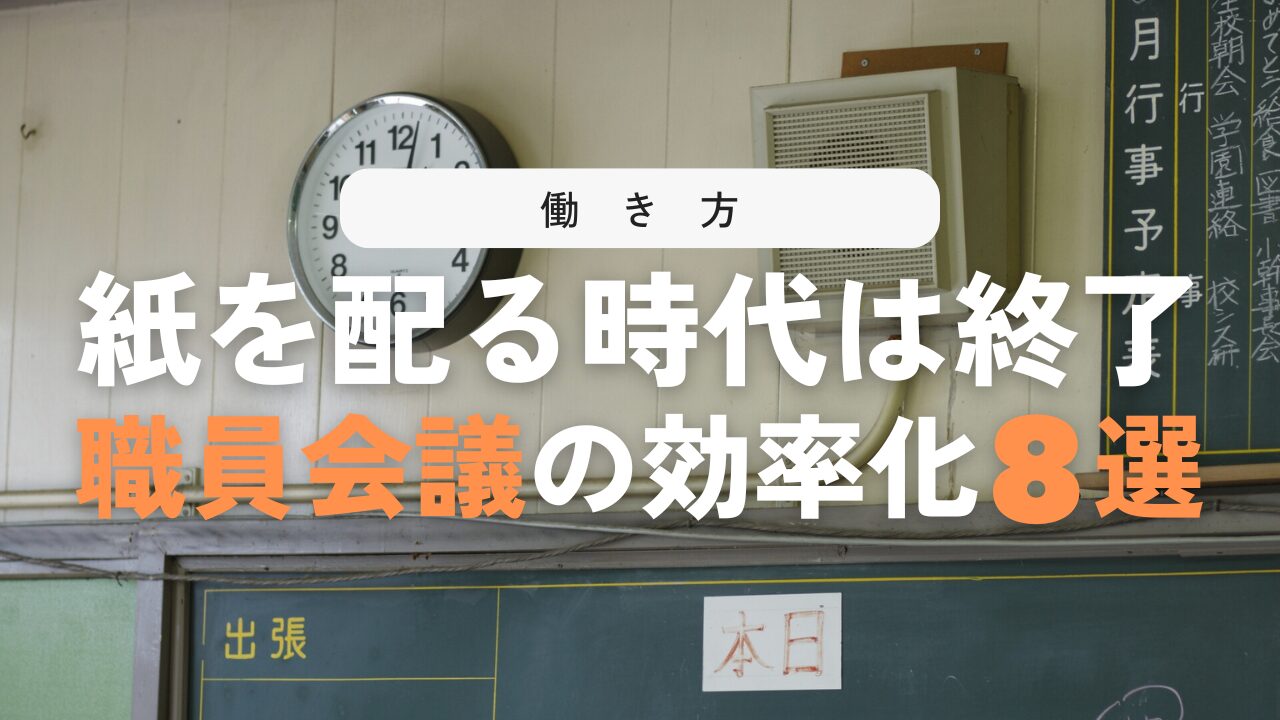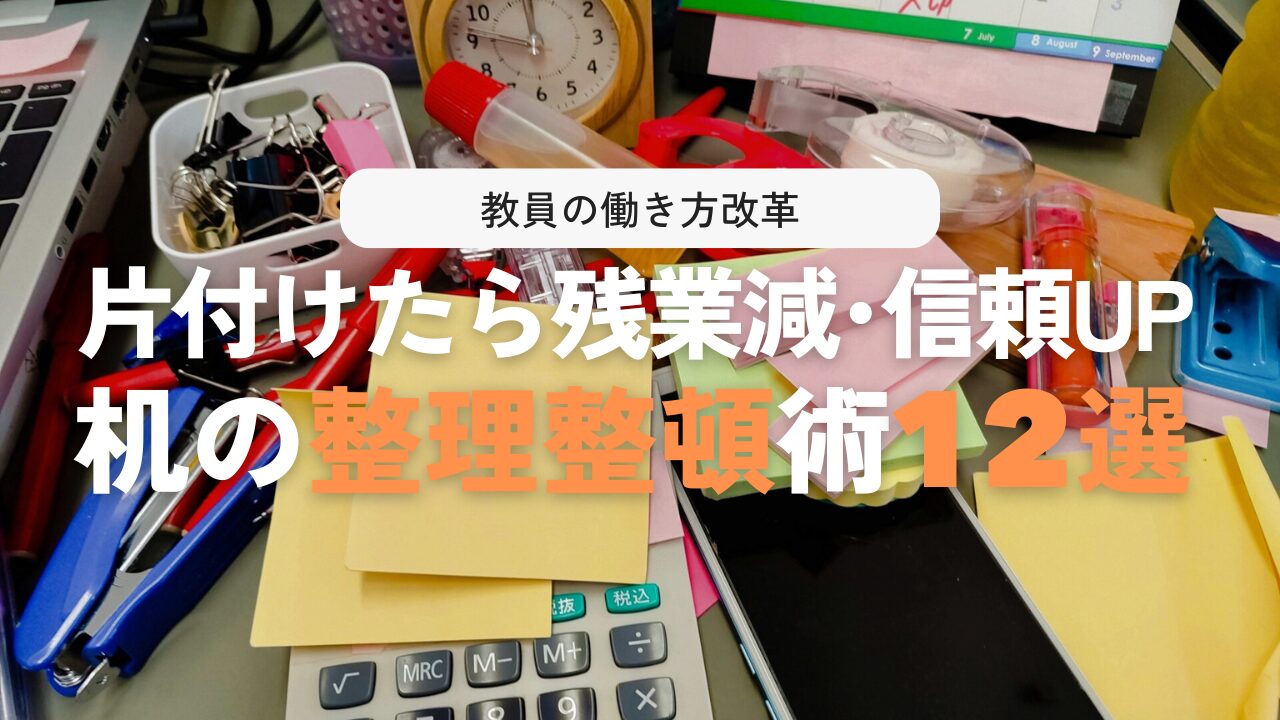【激変】職員朝会・夕会の改善策8選!振り回されない情報共有の最適化戦略
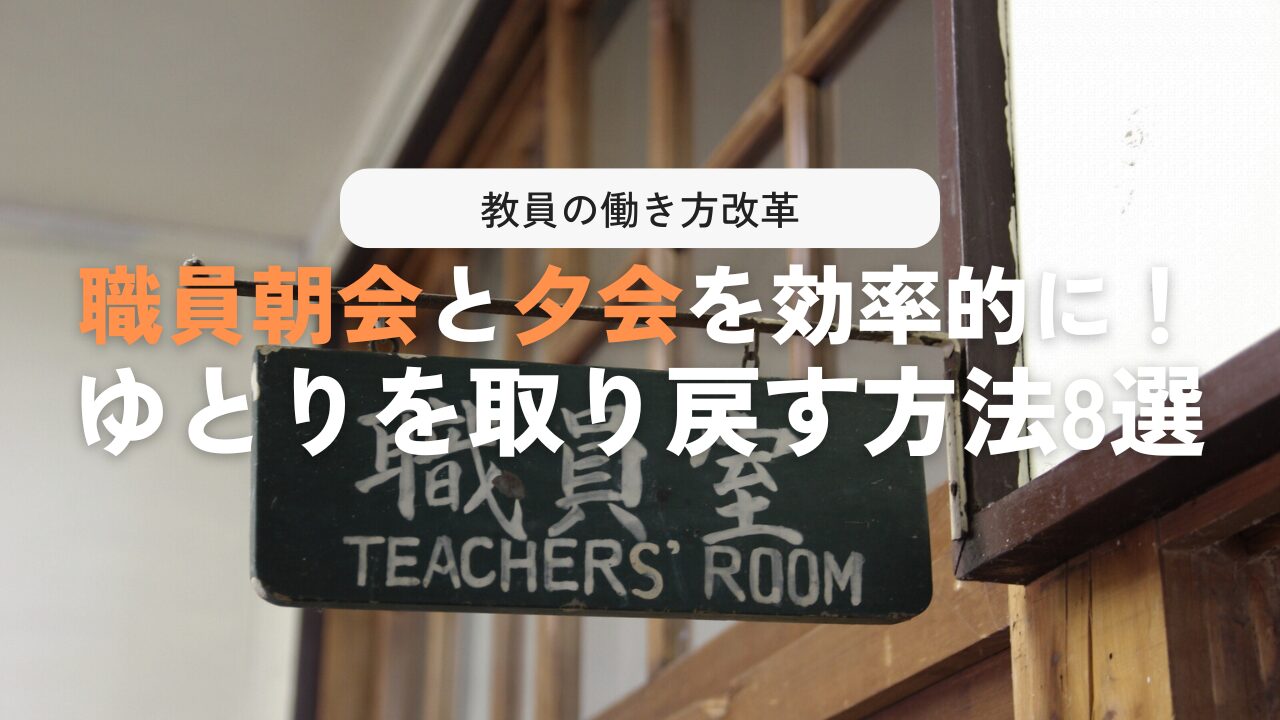
学校現場で働く中で、「職員朝会や夕会がなんだか長い…」「頻繁あるけど、本当に全部必要なの?」と感じたことはありませんか?
朝の忙しい時間や放課後の仕事がまだたくさん残っている中で、「毎回同じように繰り返されているだけ」とモヤモヤを抱えている人もいるかもしれません。
今回の記事は、職員朝会や夕会の6つの問題点を整理し、効率的で意義ある時間に変える8つの方法をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 職員朝会や職員夕会が長くて困っている
- 会議を効率よく進める方法があれば知りたい
- 学校の働き方改革を、本気で前に進めたいと考えている
この記事を読めば、職員朝会や夕会の時間がスリムになり、学校全体の働き方改革を進めることができるようになります。
この記事を書いた人↓

職員朝会・職員夕会とは何か?

学校の会議というと「職員会議」がよく知られていますが、実は「職員朝会」や「職員夕会」も定期的に行われているのです。
職員朝会とは、学校に勤務する先生が、授業が始まる前の朝の時間に職員室などに集まって行う短時間の打ち合わせのことです。
主な目的は、当日の予定や行事の確認、子どもたちの体調や特別な配慮が必要な状況の共有、各担当からの連絡事項を伝えることにあります。
職員朝会を実施している学校では、子どもたちの登校時刻の前後に、5分〜10分程度の時間を使って行われるのが一般的です。
もし子どもたちがすでに登校している場合は、一部の先生が校内や校庭で見守りを行い、他の先生たちが職員室などに集まって、短時間で会議を行います。

子どもたちが朝の支度が終わった後、教室で読書や自習をしていたり、校庭で遊んでいたりすることもあります。
職員夕会とは、学校の授業や子どもたちの下校が終わった後に、先生が職員室などに集まって行う短時間の打ち合わせのことを指します。
朝に行われる職員朝会に対して、夕方に行われることから「夕会」と呼ばれています。
主な目的は、その日の出来事のふり返りや、翌日以降の予定の確認、連絡事項の伝達、行事の日時調整や準備の打ち合わせなどを行います。
職員夕会を実施している学校では、通常は10分〜20分程度で行われますが、行事前や重要な確認事項がある場合には長引くこともあります。
- 職員朝会…一日のスタートを整えるための会
- 職員夕会…一日のまとめと次への準備のための会
いずれも学校運営を円滑にするうえで大切な場ですが、働き方改革が求められる中で、その頻度や方法を見直す動きも広がっています。
職員朝会や夕会の6つの問題点

職員朝会や夕会は、先生間で情報を共有し、学校運営を円滑に進めることを目的として実施されていますが、実際の運用においては次のような6つの問題が存在しています。
- 会議の時間が長引いてしまい、業務時間を圧迫する。
- 情報共有が非効率になりやすい。
- アナログな運用に偏っている。
- 特定の先生が会議内容をリアルタイムで把握できない。
- 時間外勤務の一因となっている。
- 「形だけの会議」になっている場合がある
①会議の時間が長引いてしまい、業務時間を圧迫する
本来、職員朝会は5〜10分、職員夕会は10〜20分程度の短時間で終えるのが理想です。
しかし、話題が多すぎたり、連絡事項が整理されていなかったり、発言が長引いたりすることで、予定時間を超えてしまうことがあります。
その結果、授業準備の時間が削られたり、子どもたちへの対応が後回しになったりしてしまい、先生の実務に支障が出るケースも少なくありません。
こうした「想定外の拘束時間」が続くことで、ストレスや疲労感が蓄積になります。
②情報共有が非効率になりやすい
職員朝会や夕会では、全体に共有すべき重要な連絡と、特定の学年や係だけに必要な情報が、明確に区別されないまま同時に伝えられることが多くあります。
そのため、自分には関係のない内容を延々と聞かされる状況が生まれ、「この話はここで共有する必要があったのか?」「わざわざ全員が集まる必要があったのか?」と疑問に感じる教員も少なくありません。
「このためだけに出席したの?」という無力感や時間損失感が積み重なることで、先生たちの間で温度差や不満も生まれやすくなるのです。
③アナログな運用に偏っている
学校現場ではいまだに、連絡事項を紙で配布したり、口頭で全員に伝えたりといったアナログな情報共有が主流となっているケースが多く見られます。
そのため、簡単な確認事項であっても毎回人を集めて説明する必要があり、先生全員の時間を奪ってしまうという非効率さが残っています。
本来なら、ICTツールを活用すれば、各自の空き時間に確認できる情報も、わざわざ集合して共有しなければならないという構造が、業務の柔軟性を妨げています。
④特定の先生が会議内容をリアルタイムで把握できない
子どもたちが登校している時間帯に職員朝会が行われる場合、教室や校庭で子どもたちの安全を見守っている先生は、当然その場に参加することができません。
そのため、朝会が終わった後に別の先生から内容を聞き取ったり、朝会記録を読み返したりする必要が生じます。
しかし、そこに書かれていない緊急事項や急な変更があった場合、聞き漏らしや誤解が生じる可能性もあります。
また、他の先生に確認が必要な場合でも、すでに相手も朝の会や授業に入っていてタイミングが合わず、確認が後回しになってしまうことがあります。
その結果、必要な対応がギリギリになってしまうことも少なくありません。
⑤時間外勤務の一因となっている
職員夕会が長引くことは、教員の退勤時刻に直接的な影響を与えます。
夕方の短い時間に集中して済ませたいと思っていても、連絡や打ち合わせが長引くと、それだけで予定していた仕事が後ろ倒しになります。
結果として「夕会がある日は早く帰れない」「夕会があると子育てとの両立ができない」といった、働き方の柔軟性が失われる要因にもなっています。
これは、教員個人の負担にとどまらず、職場全体の勤務環境やチームとしての生産性にも悪影響を及ぼす深刻な問題です。
⑥「形だけの会議」になっている場合がある
連絡事項が特にない日でも、「習慣だから」「毎日やっているから」といった理由で形式的に会議が開催されてしまうことがあります。
そういった会議では、必要性の薄い情報が惰性で読み上げられたり、「無理に話す内容をひねり出している」ような雰囲気になることも少なくありません。
このような形骸化した会議は、先生にとって「ただ立って聞いているだけの時間」になりやすく、集中力やモチベーションの低下を招きます。
実質的な価値が薄い会議を続けることは、教員の意欲を削ぎ、職場全体の活気にも影を落とす結果になりかねません。
職員朝会・夕会を効率化する8つの改善策

本来、情報を共有し、学校全体の連携を深めるための大切な時間であるはずの職員朝会や夕会が、「話を聞くだけ」「時間の割に得るものが少ない」と感じられてしまうと、その会議自体の価値が揺らいでしまいます。

職員会議や夕会の6つの問題点を解決するには、どうしたらいいだろう?

そのためには、次のような8つの改善策を図ると会議の質を高めるだけでなく、効率的に進められて時間を短縮できます。
- 必要に応じて開催する。
- 伝達事項をオンライン共有(校内共有)する。
- 全体連絡と個別連絡を明確に分ける。
- 連絡事項を「黙読する前提」にする。
- 会議の冒頭に終了時刻(会議時間)を宣言する。
- 出席は「該当者のみ」にする選択肢も入れる。
- ノー会議デーを設定する。
- 定期的なふり返りアンケートで見直す。
①必要に応じて開催する
これまで多くの学校で、職員朝会や夕会は「毎日行うもの」「毎週◯回実施すること」として定着してきました。
しかし、すべての会で重要な情報が共有されているとは限らず、「ただの習慣で開催されている」「出席する意味が感じられない」といった声も少なくありません。
そこで、「連絡事項があるときだけ実施する」「週1〜2回に開催頻度を見直す」といった、柔軟な運用に切り替えていくのです。
まずは試験的に回数を減らし、「会議を減らして何か支障は出たか?」「むしろ、どんな良い効果があったか?」といった視点でふり返りながら、自校にとっての最適な開催頻度を探っていくことが大切です。
たとえ、会議の回数を減らしたとしても、必要に応じて臨時開催する体制を整えておけば、緊急時や重要事項の伝達には十分対応できます。
②伝達事項をオンライン共有(校内共有)する
口頭での連絡にこだわるのではなく、チャットやGoogleドライブ・OneDrivemの共有ファイル、校務支援システムの掲示板などを活用して情報を共有することで、先生は自分のタイミングで内容を確認できるようになります。

オンライン共有が難しい環境にある場合は、職員室パソコンの共有フォルダを活用することで、同様の効果を得ることができます。
これにより、全員が一斉に集まって話を聞く必要がなくなり、会議に出席する時間そのものを削減することが可能になります。
口頭による伝達よりも、文字情報で伝えるほうが正確で見返しもしやすく、記録にも残るため、利便性も高まります。
一方で、その場での質疑応答や意見交換、共通理解の形成が必要な内容については、会議を開いて話し合うことが適しています。
③全体連絡と個別連絡を明確に分ける
職員朝会や夕会が非効率になりやすい理由の一つに、「全員に共有すべき情報」と「特定の人だけに必要な情報」が混在して一括で伝えられてしまうという問題があります
そのため、話を聞いていても「自分には関係のない内容だ」と感じる場面が多くなり、会議そのものに対するモチベーションの低下や時間の浪費につながってしまいます。
この状況を改善するためには、情報の種類を“全体向け”と“個別向け”に明確に分類し、それぞれに適した方法で伝えることが重要です。
たとえば、学校全体に関わる安全指導や行事の確認などの全体連絡は、職員朝会や夕会などの対面で共有し、全員で認識をそろえることが効果的です。
一方で、ある学年だけに関係する業務連絡や、特定の係・担当者に関わる話題などの個別連絡は、そのメンバーだけが参加する小規模な打ち合わせで共有したり、チャット・掲示板・共有フォルダなどで伝えるようにするとよいでしょう。
④連絡事項を「黙読する前提」にする
会議の効率を下げる要因のひとつに、担当の先生が連絡事項を全て音読して説明するケースがあります。
たしかに、声に出して丁寧に読み上げることは「優しさ」や「親切心」の表れであり、情報共有のミスを防ぎたいという意図も理解できますが、そのたびに時間がかかってしまい、結果として会議全体が長引いてしまいます。
そこで提案したいのが、全員が自分の目で確認する「黙読を前提とした共有の文化」をつくることです。
配布や共有している情報をもとに、「◯◯の件については◯◯に記載していますので、ご確認ください。(間を置いて)この内容でよろしいでしょうか?」「◯◯についてはご一読ください」などと、要点を一言で済ませるスタイルへ切り替えるのです。
こうすることで、無駄な音読時間を省きながらも、確認の場としての会議の意味はしっかり保たれます。
⑤会議の冒頭に終了時刻(会議時間)を宣言する
職員朝会や夕会を効率的に進めるためには、会議の終了時刻あるいは会議時間を宣言することが重要です。
たとえば、会議の冒頭で「◯時◯分までに終わらせます」「本日の会議は10分で終了します」とあらかじめ伝えておくことで、話す側・聞く側の双方に時間に対する意識が生まれ、内容が自然とコンパクトにまとまりやすくなります。
また、「あと◯分しかない」という感覚が働くことで、脱線や雑談が入りにくくなり、予定通りに会議が終わる安心感にもつながります。

司会を担当する先生が「あと5分です」などと途中で時間をカウントすることで、会議の進行にメリハリが生まれ、だらだらと長引くのを防ぐことができます。
⑥出席は「該当者のみ」にする選択肢も入れる
職員朝会や夕会の中には、特定の教員(学年主任や校務分掌主任など)にしか関係しない内容だけで構成されている場合があります。
そのようなケースでは、無理に全教員を集める必要はありません。
「この連絡は該当者のみ出席」という形式にすることで、関係のない教員が“ただ参加して聞いているだけ”という状況を避けられます。
参加者の数=質ではありません。必要な人に、必要な情報が、適切に伝わることが大切なのです。この見直しだけでも、全体の時間と労力を大幅に削減できます。
⑦ノー会議デーを設定する
毎日のように会議があると、「今日も会議…」と気持ちが重くなってしまうことがあります。
そこで効果的なのが、「毎週〇曜日は朝会(または夕会)を実施しない」と決める“ノー会議デー”の設定です。
原則としてこの日は連絡がないことを前提にすると、その分、他の日に連絡内容を集中させる意識が高まり、情報の精選も進みます。
また、心理的なゆとりや、授業準備・子ども対応に使える時間が増えることで、教員の満足度向上にもつながります。
⑧定期的なふり返りアンケートで見直す
職員朝会や夕会が「形骸化している」「だらだら長引いてしまう」といった声が出る前に、定期的なふり返りアンケートを実施することが効果的です。
たとえば次のような設問を設けて、全体で共有・改善に活用しましょう。
こうした問いかけを通じて、先生一人ひとりの意識を高めるだけでなく、“会議の在り方そのもの”を定期的に見直す文化をつくることができます。
まとめ
今回は、職員朝会や夕会の6つの問題点を整理し、効率的で意義ある時間に変える8つの方法について紹介しました。
- 職員朝会や夕会は「ただ情報を聞くだけの場」ではなく、チームとして動くために必要なことを共有する大切な場であること
- 「毎日やるのが当たり前」「とりあえず全員参加」から脱却し、必要な内容を、必要な人に、効率よく伝える工夫が必要であること
- ICTの活用や、開催頻度の見直し、連絡の分類・共有方法を工夫することで、時間の短縮と会議の質の向上が両立できること
この記事を読んだことで、職員朝会や夕会の見直し方がわかり、明日からの会議を「短く・濃く・価値ある時間」に変えるための第一歩を踏み出すことができるようになります。
会議が短くなると、そのぶん教材研究や授業準備などの仕事や、自分自身の心と体のリズムにも、ゆとりが生まれます。
そして何より、「この時間には意味がある」「この会議は出てよかった」と先生たちが感じられる“納得できる学校づくり”につながります。
この記事の内容を参考に、校内でも共有しながら、できるところから取り組んでいきましょう。