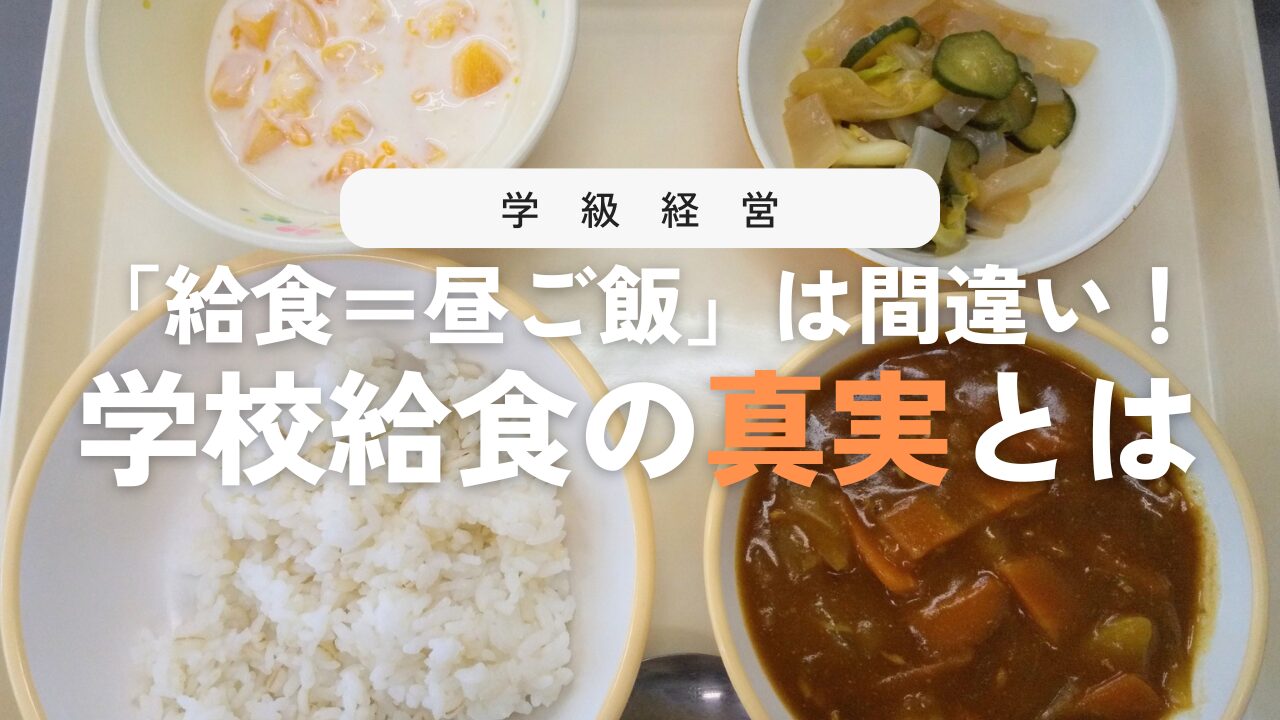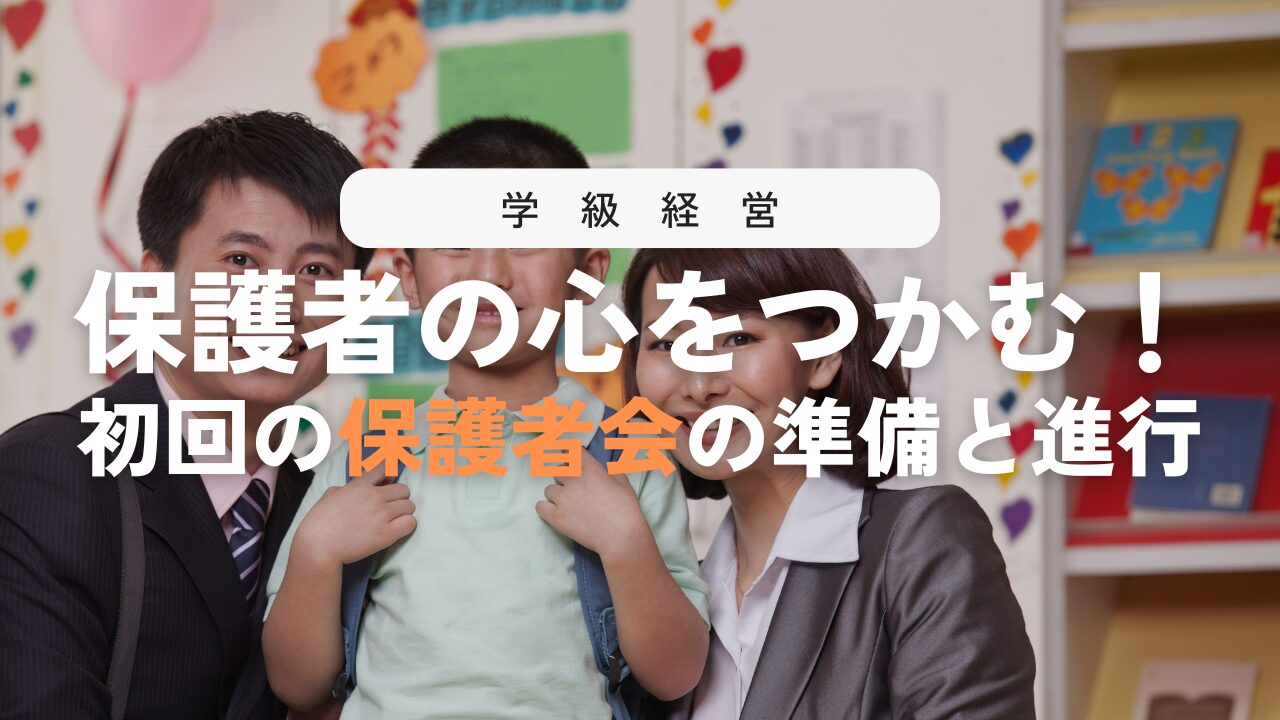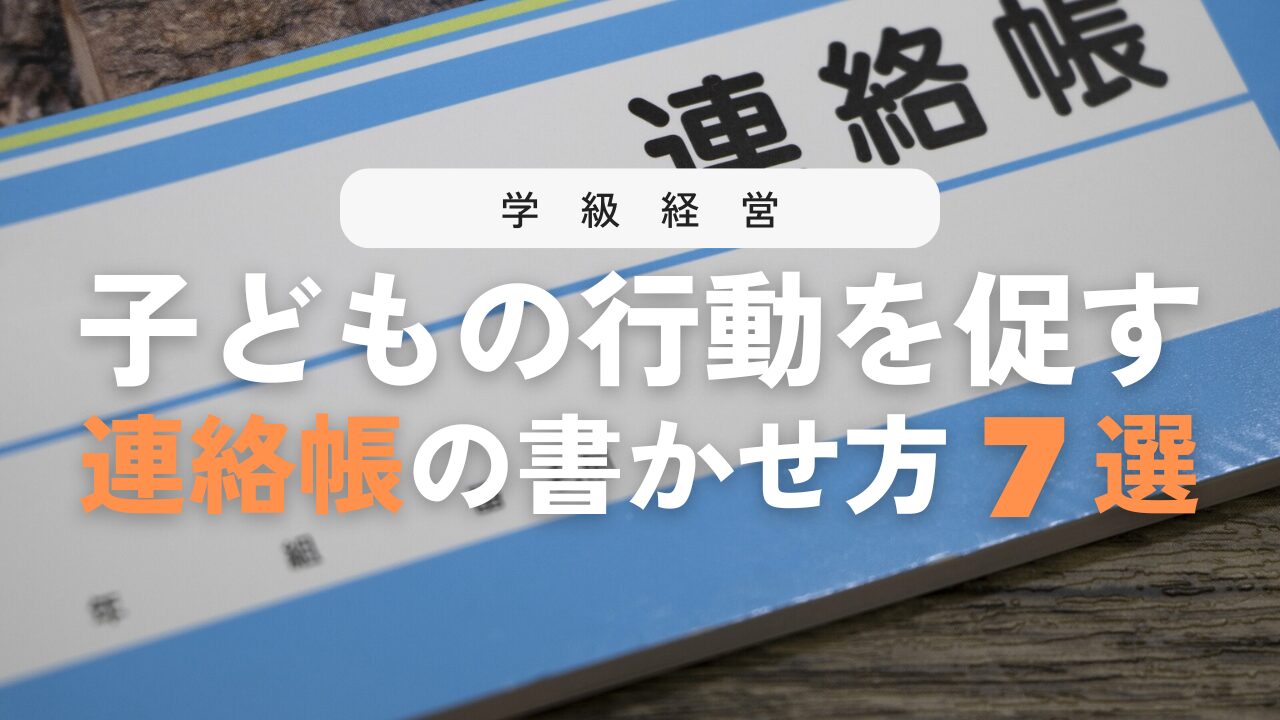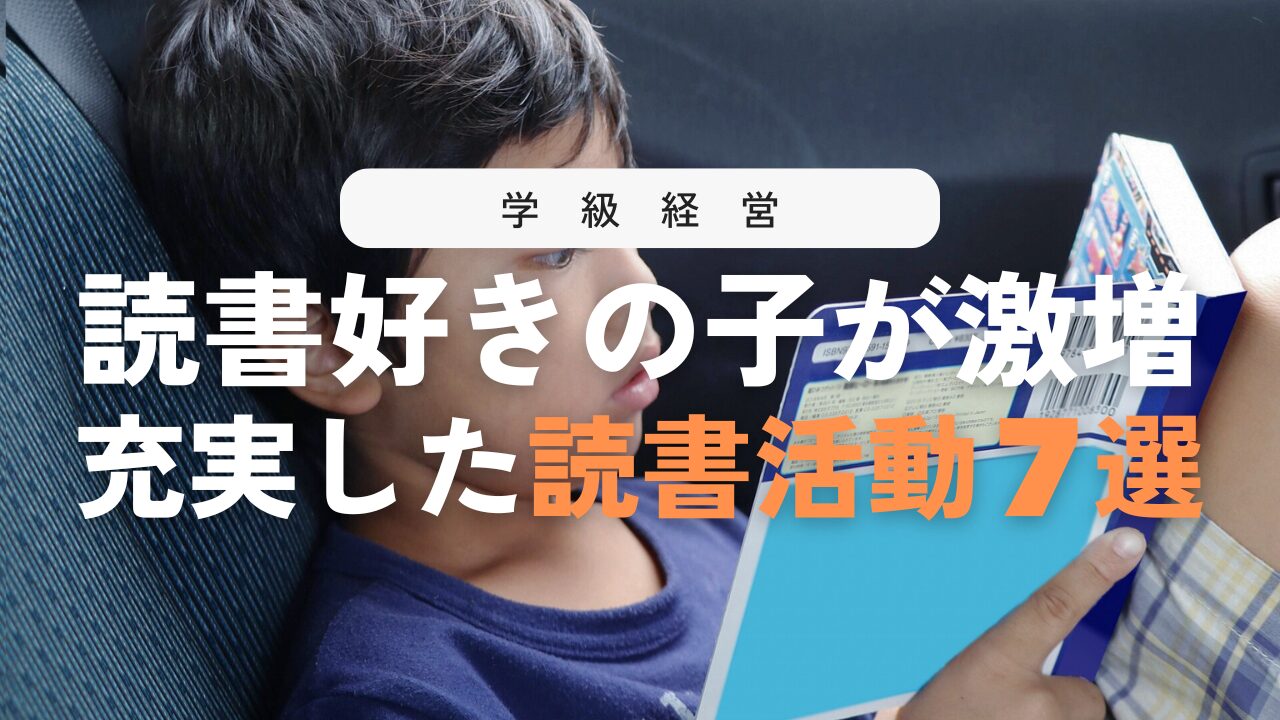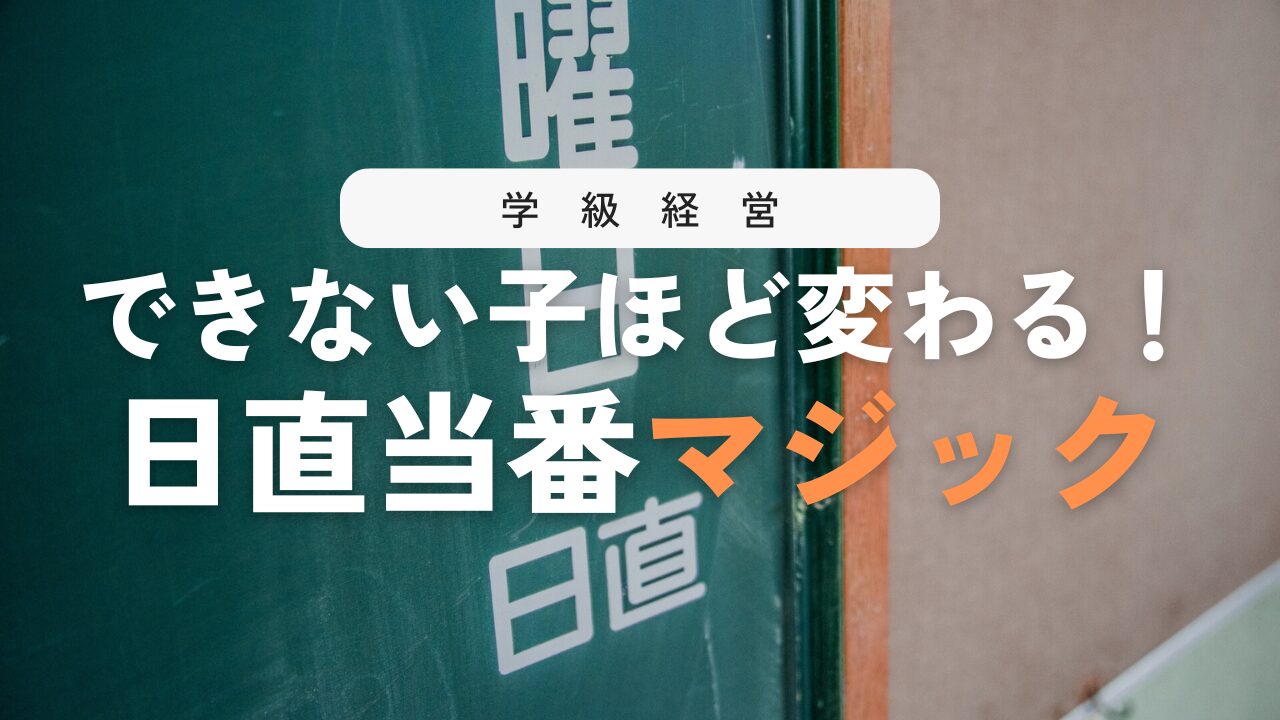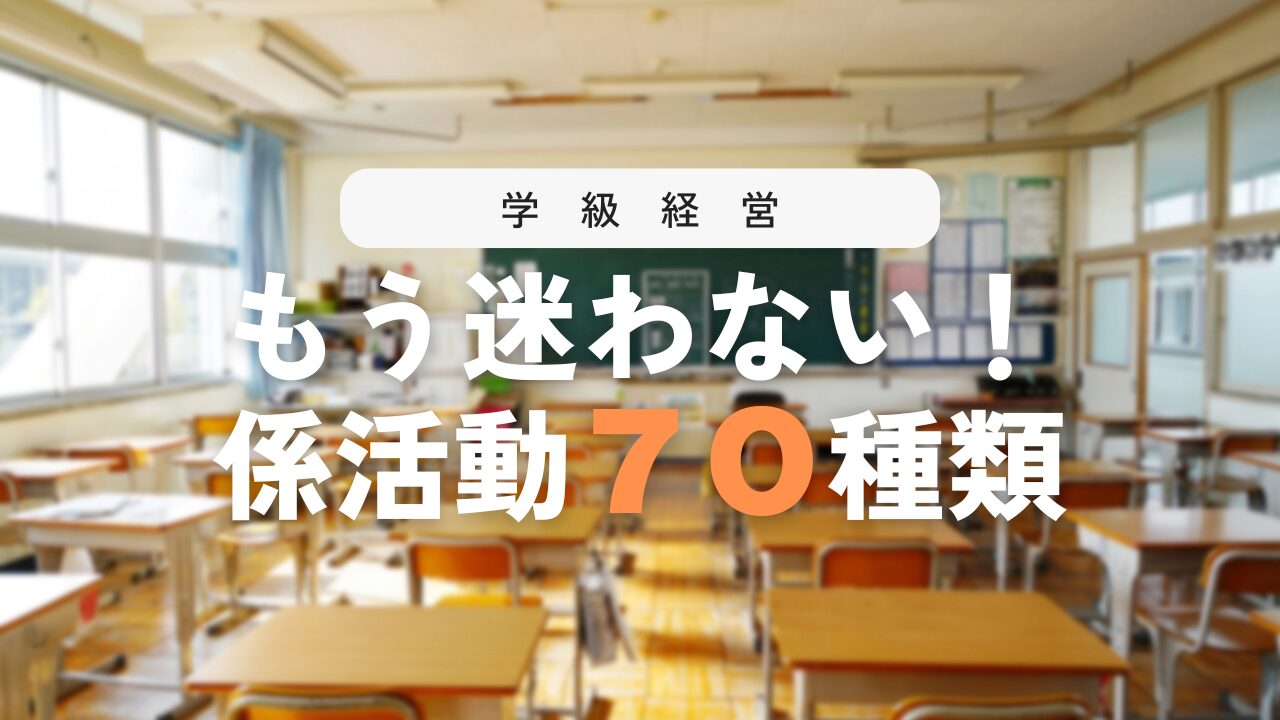【伝授】整列の指導10選!自主的に並ぶ子が増える工夫とは
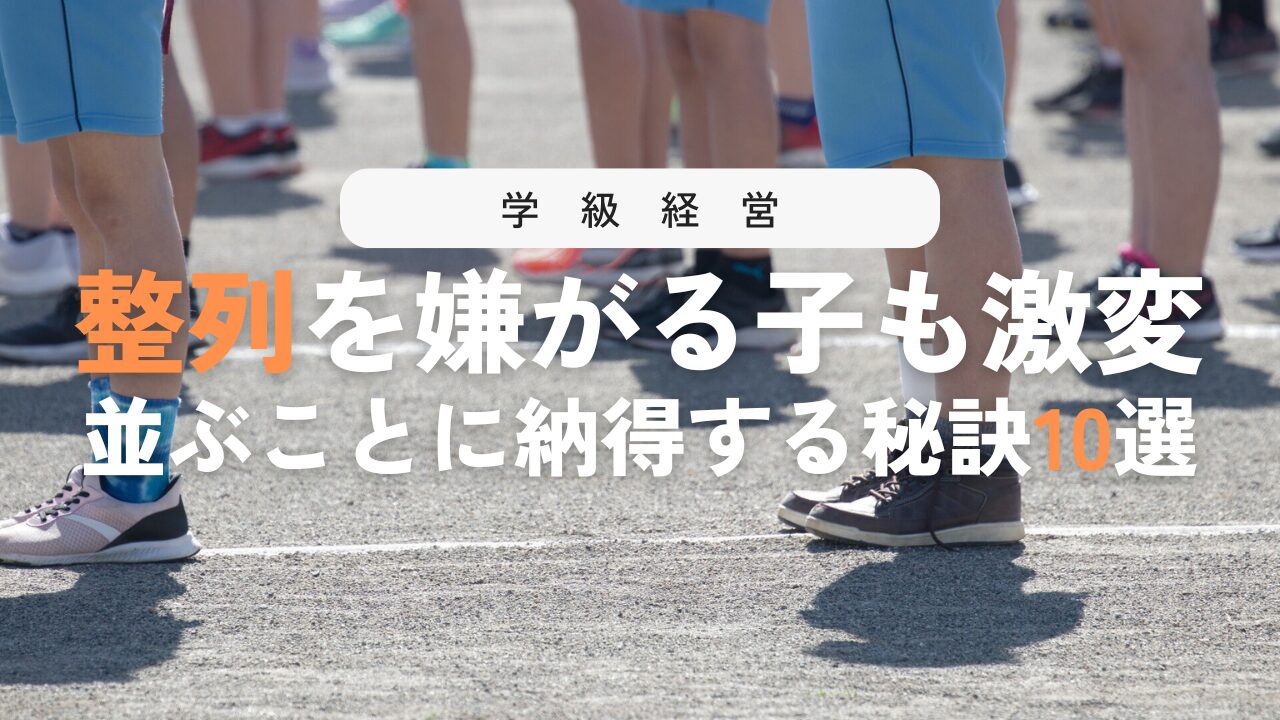
どうも、まっつーです。
子どもたちが学校で整列する場面は意外と多いものですが、実際には「なんだか並ぶのに時間がかかる」「並んだ後も騒がしくて落ち着かない」「整列が崩れやすい」など、困ることがあるのではないでしょうか?
その整列の指導がうまくいかない原因に、「整列する目的が子どもに伝わっていない」「子どもが意味がわからないまま、腕を伸ばして“前へ習え”をしている」という点が挙げられます。
今回の記事は、学級で整列する5つの目的を理解させ、子どもたちが自主的に並べるようになる指導法10選(6つのポイント+4つのステップ)をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 整列のたびに子どもたちがバラバラになって悩んでいる
- 子どもたちが「整列は面倒」と感じている
- 体育の授業や集会の場面で、スムーズに整列させたい
- 並んでいる間に静かにできるようにしたい
この記事を読めば、整列がただの「並ぶ作業」から集団生活を安全に送るための意味があるものだという認識に変わり、子どもたちが納得して動ける整列指導ができるようになります。
この記事を書いた人↓

整列する目的とは何か?

整列とは、一定のルールに従って、子どもたちが真っ直ぐに順序よく並ぶことをいいます。学校では、次のような場面で整列が求められます。
- 登下校(登校班)
- 全校朝会・集会
- 教室から特別教室などへ移動する時
- 体育の授業
- 運動会
- 健康診断
- 遠足
- 社会科見学(生活科見学)
- 宿泊行事(修学旅行) など
また、次のような整列の仕方があります。
他にも、給食の配膳や図書室での本の貸出・返却、先生にプリントを採点してもらう時、ノートやワークシートなどを提出する時、トイレが混雑している時など、さまざまな場面で1列に並ぶことがあります。

学校では整列する場面やその仕方がこんなに多いんだね。そもそも何のために整列をする必要があるの?

学校では子どもたちが集団生活を送っているからこそ、整列が必要なんだ。整列には次の5つの大切な目的があるんだよ。
- 安全確保のため
- 人数確認のため
- 他者への配慮のため
- 混乱を防いで秩序を保つため
- 礼儀とマナーを身につけるため
①安全確保のため
整列はただの形式的な動きではなく、子どもたちが安全かつ安心して活動できる環境を整えるために必要な行動なのです。
たとえば、避難訓練では、すばやく安全に避難することが最も重要な目標です。そのためには、子どもたちが混乱せずに整然と並ぶことが必要です。
もしバラバラに走り出してしまうと、転倒や衝突のリスクが高まり、かえって危険です。
また、校外学習などで車や自転車が通る道を歩く場合も、広がって歩いてしまうと交通事故の危険が増します。
整列することで、先生は子どもたち全員の位置や状態を一目で把握でき、安全を確保しやすくなります。
②人数確認のため
整列することは、先生にとって子どもたちの人数を迅速かつ的確に把握するための手段になります。
たとえば、避難訓練の際には、先生が全員が避難できたかを瞬時に確認する必要があります。
もし一人でも欠けている場合、その子が教室に取り残されていないか迅速に判断し、救出に向かわなければなりません。
また、校外学習などでは、子どもたちが迷子になっていないか確認するために、全員の人数を把握することが求められます。
整列していれば、先生は一目で全体を見渡し、人数や安全を確認しながら移動や活動をスムーズに進めることができます。
③他人への配慮のため
整列は、自分の安全を守るだけでなく、周りの人への思いやりや配慮を育てる大切な習慣です。
たとえば、廊下や校外の道で広がって歩くと、反対側から来る人や後ろから歩いてくる人の通行を妨げてしまいます。
こうした状況は、他の人に迷惑をかけるだけでなく、トラブルや事故の原因にもなりかねません。
整列して歩行することで、自分の立ち位置や相手との距離を意識する力が高まり、周囲の人のことを考えて行動する姿勢が身につくようになります。
④混乱を防いで秩序を保つため
学校など多くの人が集まる場所や限られたスペースでの行動には、整然とした動きが求められます。
無秩序な状態では、衝突や行き違いが発生しやすく、活動が遅れたり、安全が確保できなくなったりするリスクがあるからです。
たとえば、全校朝会や集会、避難訓練、給食の配膳など、多数の子どもたちが一斉に動く場面では、整列ができていないと誰がどこの位置にいるべきかがわからず、混乱が生じやすくなります。
整列することで、動く順番や進む方向が明確になり、子どもたちは安心して行動できるようになります。
⑤礼儀とマナーを身につけるため
整列の経験を通して、他人を押さない、割り込まない、大声で騒がないといった基本的な心構えが自然と身につきます。
これは、学校生活だけでなく、社会生活でも必要なコミュニケーションスキルあり、他人への礼儀や集団でのルールを守る態度を育む基盤となります。
たとえば、遊園地でアトラクションに乗る時や、人気の飲食店で順番待ちをする時、駅のホームで電車を待つ時など、並ぶ場面は日常生活のさまざまな場面で見られます。
こうした場面でも順番を守り、きちんと列を作って静か待つという行動は、公共の場でのマナーとして非常に大切です。
自主的に整列するようになる6つの指導ポイント

学校では、集団生活を送る上で整列が必要な場面が数多くあります。
しかし、その都度「整列するのが面倒だ」「何のために整列するのかわからない」と感じてしまう子どもたちが多いと、混乱やトラブルの原因となり、学級経営が難しくなってしまいます。
これを防ぐためには、整列指導で行うべき6つのポイントがおさえることが大切です。
- 整列する目的を伝える。
- 避難訓練での整列の仕方から教える。
- 真っ直ぐのラインを活用する。
- 整列の基本姿勢を教える。
- できているところを褒める。
- さまざまな場面で評価を伝える。
①整列する目的を伝える
整列を教える際は、「何のために整列する必要があるのか?」という目的を最初にしっかりと伝えることが大切です。
これは、子どもたちが「先生に言われたからやる」から「目的を理解して自分から動く」という意識に変わるために欠かせない指導です。
前述した整列する5つの目的を丁寧に話すようにしましょう。特に、安全面への配慮や、周囲の人のことを考える行動につながるという点を強調すると、子どもたちも納得しやすくなります。
明確な目的を伝えることで、整列は単なる「形式的な指導」ではなく、子どもたちの意識を育てる教育の一環となるのです。
②避難訓練での整列の仕方から教える
整列の基本を教える際に、最初に取り入れたいのが避難訓練での整列指導です。
これは、整列の重要性を子どもたちが最も実感しやすい場面であり、命を守る行動と直結しているため、非常に効果的です。
多くの学校では、背の順で2列(男女別または男女混合)で並ぶ形式を採用していますが、この2列での整列を徹底して指導することが、他の並び方(名前順の1列や赤白2列、4列など)にも応用が利くようになります。
避難訓練は年に数回しかありませんが、日常の整列がその練習にもなっていることを強調することで、整列が自分事として真剣に捉えられるようになります。

普段から整列する習慣を身につけておくと、いざという時に慌てず素早く行動できるようになります。
③真っ直ぐのラインを活用する
真っ直ぐに並ぶ感覚を身につけるために、体育館などのラインを活用するのが効果的です。
体育館の床には、バスケットボールやバレーボールのコートラインが引かれており、これらを使うと自然に真っ直ぐに並ぶ感覚を身につけやすくなります。
このとき、「どうして真っ直ぐ並ぶ必要があるのか?」と質問して考えさせると、子どもたちから「全校朝会や集会のときに、隣のクラスとぶつかってしまう」「外を整列して歩いているときに、列が斜めになっていると反対側から来た人の迷惑になる」といった具体的な意見が出ることがあります。
真っ直ぐに並ぶことは、自分だけでなく、周囲の人の安全も守ることにつながります。
④整列の基本姿勢を教える
整列を教える際には、基本的な姿勢や動作を具体的に教えることが大切です。次の3つの基本姿勢をしっかりと指導しましょう。
⑤できているところを積極的に褒める
当然ながら、整列そのものは楽しい活動ではありません。そのため、指導の際には「できている部分を積極的に褒める」ことが大切です。
成功体験として価値づけることで、子どもたちのやる気や自信を引き出し、整列への意識が高まります。
その上で、修正すべきポイントは絞って、具体的でわかりやすいアドバイスをするように心がけましょう。
また、子どもたちが飽きずに集中力を保つために、できるだけ短時間で達成感を感じられるように配慮することで、整列に対する肯定的な態度を育むことができます。
⑥さまざまな場面で評価を伝える
全校朝会や集会、避難訓練、遠足、社会科見学などの実際の場面でも、整列がうまくできたことをたくさん褒めましょう。
「きちんと整列ができていたので、低学年のお手本になっていたよ」「すばやく整列ができたから、みんな安全に早く避難できたね」と具体的な状況に基づいて評価することで、整列が重要な行動であることを日常的に意識させることができます。
一方で、修正が必要な場合は、「前を見ずに後ろの人に気を取られていると、列が乱れてしまって他のクラスの列とぶつかってしまうことがあるよ」と、実際に起こりうる場面を示しながら指導すると効果的です。
良い点と改善点を伝えることで、子どもたちは自分の動きを振り返りやすくなり、整列の重要性をより深く理解することができます。
整列を進化させる指導の4ステップ

子どもたちを整列させる際に、先生が毎回「気をつけ」「前へ習え」「直れ」と指示を出している場面はよく見られます。
しかし、その指示が本当に必要なのでしょうか?
- 目的…子どもたちが整列すること
- 手段…「気をつけ」「前へ習え」「直れ」の動作をすること
理想は、「気をつけ」「前へ習え」「直れ」をしなくても、子どもたちが自然と整列できるようになることです。

特に「前へ習え」で腕を伸ばすのが嫌なんだ。先生が「直れ」って言うまで、ずっと手を伸ばしてなきゃいけないから、けっこう疲れるんだよね。

そもそも、整列する時にどうして腕を伸ばす必要があるのでしょうか?
行列ができているお店に並ぶ時も、駅のホームで電車を待っている時も、腕を伸ばす動作をする人を見たことがないと思います。
その答えは、「自分の腕を伸ばした時に、前の人とぶつからない間隔を空けるようにするため」です。
このことを踏まえて、子どもたちが「気をつけ」「前へ習え」「直れ」をしなくても、自分たちで整列できるように進化させる指導の4つのステップを解説します。
「気を付け」「前へ習え」「直れ」で整列できる
整列を進化させるためには、先生の指示があって整列できることが前提です。
前述の「自主的に整列するようになる6つの指導ポイント」をもとに、子どもたちを育てていきましょう。
やがて、子どもたちは「自分の腕の長さがどのくらいあるのか(量感)」がわかるようになってきます。
つまり、実際に腕を伸ばさなくても、前の人との適切な距離感を感覚的に理解し、ぶつからずに並べるようになるのです。
「気を付け」「“目”で前へ習え」「直れ」で整列できる
「“目”で前へ習え」とは、腕で前の人との距離を測るのではなく、目で見て量感を使って自分の腕の長さとほぼ同じ間隔を空けて並ぶことを意味します。つまり、目測です。
先生が「腕を伸ばして整列できるようになったね。じゃあ、次のレベル2に進んで、目で見て前の人との間隔を空けられるようにチャレンジしてみよう!」と言うと、子どもたちは意欲的に取り組んでくれます。
腕を伸ばす手間や疲れもないので、みんな大喜びです。
「並びましょう」の一言で整列できる
先生の「並びましょう」の指示で、子どもたち一人ひとりが自分のペースで「気を付け」「“目”で前へ習え」「直れ」をします。
これまでのように、一斉に「目で前へならえ」「直れ」と号令をかけていた段階から脱却するためです。
このレベルに達していれば、先生として言うことはほとんどありませんが、少し列が乱れている場合は調整を促しましょう。
子どもたちが自主的に整列できる
整列のレベルが高まってくると、先生がいちいち「並びましょう」と言わなくても、子どもたち同士で協力して、場に応じた整列ができるようになります。
これまでに名前順や背の順、赤白順など、さまざまな並び方を経験してきているため、状況に応じて臨機応変に対応する力が身についています。
また、列の先頭の子や一番後ろの子、真ん中の子など、要所要所にいる子どもたちが「少し列が曲がっているよ」「もうちょっと前に詰めて」と声をかけ合いながら、自然に修正していく場面も見られます。
自分たちで考え、動く力が備わっている状態が、整列レベルMAXです。
「レベル2にするよ」と伝えた時に、子どもたちから「レベルいくつまであるの?」と質問されることがあるかもしれません。
その際は、レベル3やレベルMAXまで具体的に説明してあげましょう。
子どもたちは、レベルが上がるごとに達成感を感じながら、より早く、より楽しく整列するようになります。
また、学級の実態に応じて、レベルをもっと細かく設定するのも効果的です。
一歩ずつ成長を実感できるような段階的な目標を立てることで、子どもたちの意欲をさらに引き出すことができます。
まとめ
今回は、学級で整列する5つの目的を理解させ、子どもたちが自主的に並べるようになる指導法10選(6つのポイント+4つのステップ)について紹介しました。
- 整列の目的を理解させることで、子どもたちが「整列させられている」から「自分で整列する」へと意識を変えられること
- 避難訓練や日常生活の中で、整列が「自分の命を守る行動」「周囲への配慮」だと意識づけること
- 整列のレベルを段階的に上げ、子どもたちの成長を実感させながら指導すること
この記事を読んだことで、子どもたちに「どうして整列するの?」と聞かれても、自信をもってわかりやすく説明できるようになったはずです。
また、整列がただの「並ぶ作業」ではなく、集団生活を安全に送るための大切な行動であることを伝えることで、子どもたちが納得して動ける学級づくりが実現できます。
整列の目的を理解し、自主的に整列できる子どもたちを育てることは、学級の団結力や集団行動力を高めるための大切なステップです。
ぜひ、今日からこの記事の内容を取り入れて、よりよい学級経営を目指していきましょう!