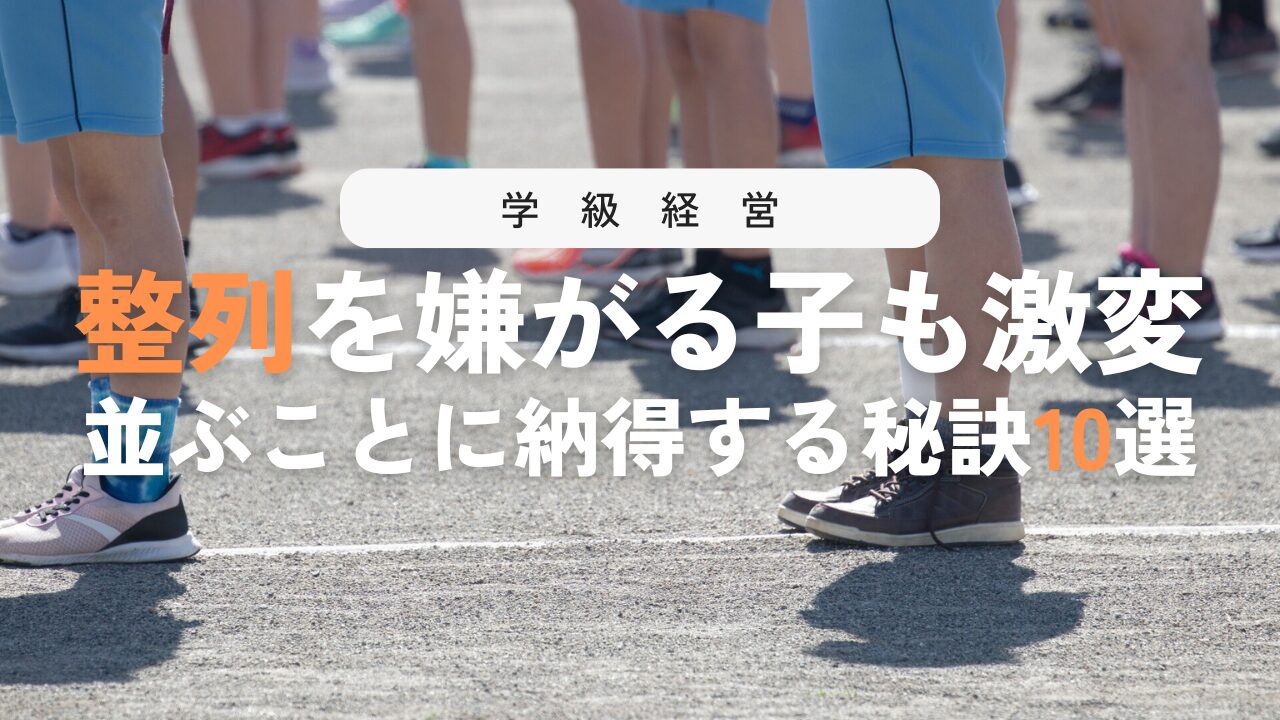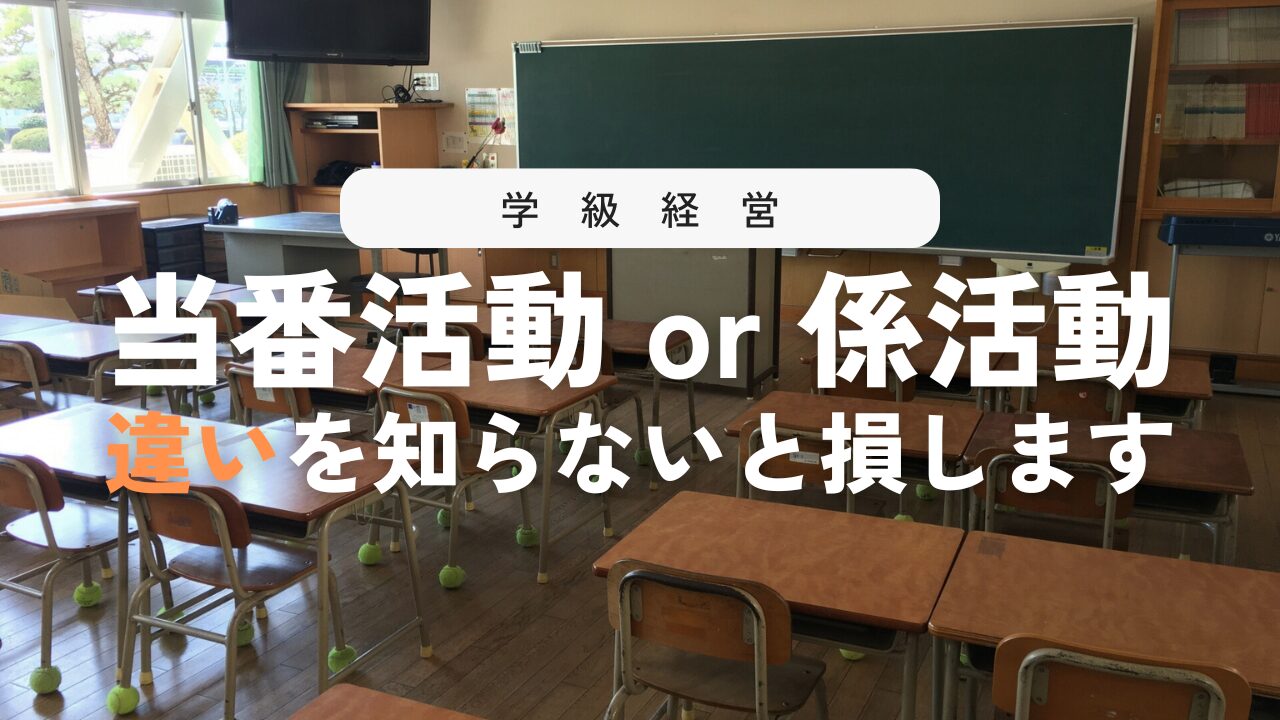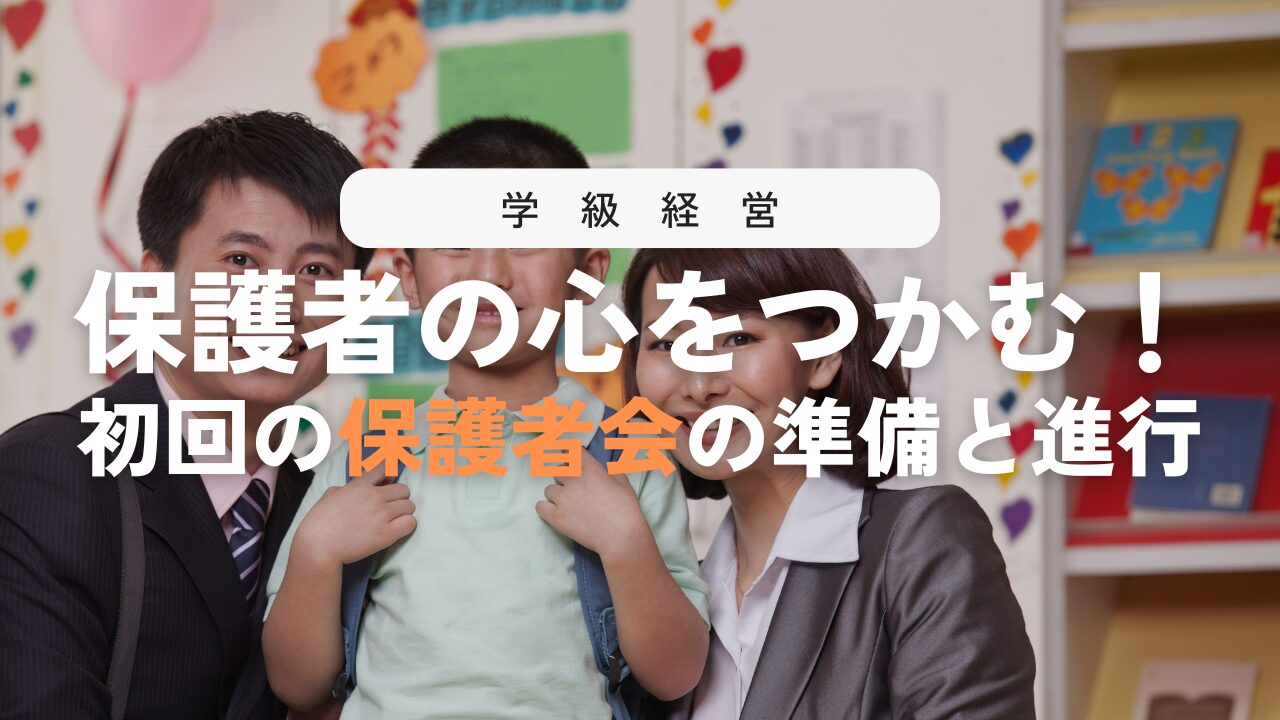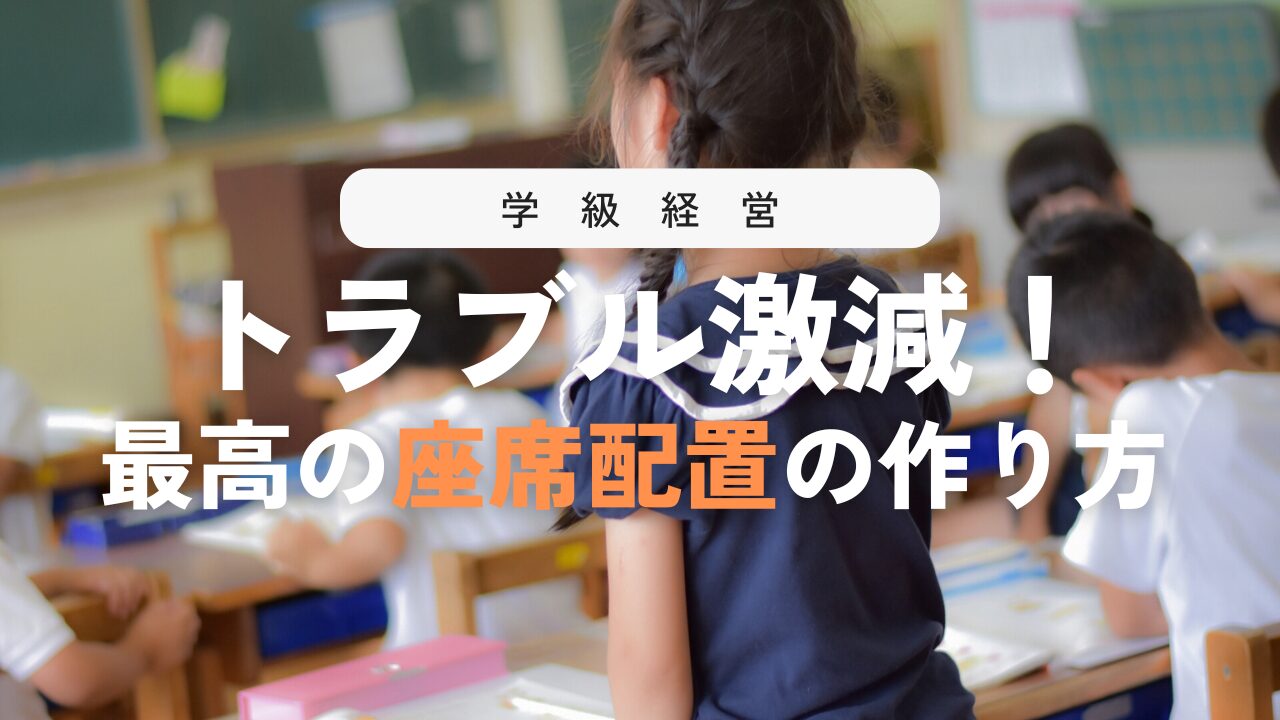【極意】子どもの叱り方13選!心に届いて納得させるコツを伝授

どうも、まっつーです。
子どもたちを指導するなかで、「どのように叱ればいいのか?」「どこまで叱っていいのかわからない…」とお悩みではないでしょうか?
あるいは、「叱り方を間違えると、保護者から連絡が来る可能性が…」「子どもに怖いと思われてしまうのではないか心配…」と躊躇してしまう方もいるかもしれません。
今回の記事は、叱ることの本当の意味や避けたいNGな叱り方、そして信頼関係を壊さずに伝えるための13のポイントをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- つい感情的に怒ってしまい、あとで後悔する
- 注意しても聞かない子への対応に困っている
- 叱ることに苦手意識がある
- 叱ったあとに子どもとの関係が気まずくなることがある
この記事を読めば、子どもの行動の背景に目を向けながら、相手の心を守りつつ、必要なメッセージを伝える叱り方ができるようになります。
この記事を書いた人↓

「叱る」とは何か?

叱るとは、子どもの行動や言葉について、何がいけなかったのか、なぜそれがよくないのかを、相手の心に届くように伝え、正しい方向に導くことです。
私たちが子どもを叱る場面の多くは、何かよくないことが起こった“事後”です。
「叱る」という行動の本当の目的は、責めることでも、恐れさせることでもなく、その子の“次の行動”を変えることにあります。
今起きたことだけを見て指摘するのではなく、その経験を通して「次はどうするか?」を考えさせる。これが叱るという行動の本質です。
叱る=「未来」に向けての声かけ

「叱る」とよく似た言葉に「怒る」という言葉があるよね。この2つには、どんな違いがあるのだろう?
「叱る」と「怒る」の違い
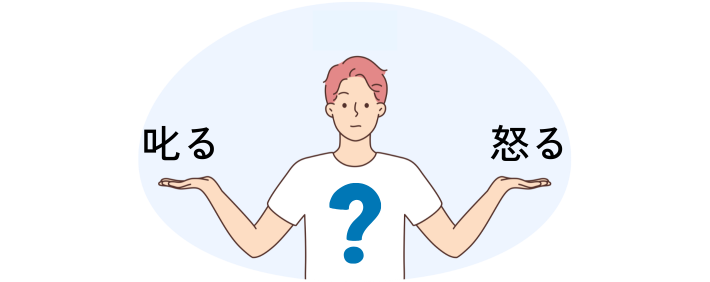
「叱る」と「怒る」の違いは、「誰のために」「どんな目的で」言葉をかけるのかという点にあります。
「叱る」とは、相手の成長を願って、必要なことを冷静に伝える行為です。
「どうしてそれが問題なのか?」など、行動の意味を考えさせたり、「どうすればよかったのか?」を一緒に考えたりして、次に生かします。
叱るときには、感情に流されず、必要なことを必要なタイミングで、必要な分だけ伝えようとします。そこには、相手を理解しようとする姿勢と、信頼が土台にあります。
一方で「怒る」は、自分のためにイライラや不満、感情を相手にぶつける行為で、相手の行動を“正す”というよりも、自分の感情を“ぶつける”かたちになります。
大きな声や厳しい言葉で押さえつけるような関わりでは、相手は「何がいけなかったのか?」を深く理解することが難しくなります。
- 叱る…相手のために冷静に伝えること
- 怒る…自分の感情をそのままぶつけること
つい怒ってしまうときの対処法
怒りの感情が出てしまいがちの場合、「アンガーマネジメント」と呼ばれる対処法が効果を発揮します。
アンガーマネジメントとは、怒りの感情とうまくつき合い、上手にコントロールするための考え方や方法のことです。
「怒りを我慢する」「怒らないようにする」ことではなく、「なぜ怒りが出てきたのか?」を理解し、「その怒りをどう扱うか?」を自分で選べるようになることを目指します。
怒りは誰にでも自然に出てくる感情です。大切なのは、その感情に振り回されるのではなく、自分の気持ちをうまく整理して、冷静に行動できるようにすることです。
アンガーマネジメントの方法としては、怒りの感情がわいてきたときに、まず「6秒間」やり過ごすことが効果的です。
その6秒の間に、深呼吸をしたり、一度その場から離れて気持ちを落ち着かせたりすることで、衝動的な言動を防ぐことができます。
叱り方の6つのNGパターン

「叱る」は子どもの成長を願って伝える大切な声かけが、その方法を間違えてしまうと、子どもは素直に受け取れなかったり、心に傷を残してしまったりすることもあります。
ここでは、やってしまいがちな叱り方のNGパターンを6つ紹介します。
- 人格を否定して叱る
- みんなの前で叱る
- 感情のままに叱る
- 長時間しつこく叱る
- その場の空気に流されて叱る
- 叱ることを言葉ではなく態度で示す
①人格を否定して叱る
これらはすべて、子どもの行動ではなく、「その子自身」を否定する言葉です。
こうした言葉をかけられると、子どもは「自分はダメな人間なんだ」と思い込んでしまい、自信や意欲を失ってしまいます。
たとえ改善を促したい気持ちがあっても、人格を否定する言い方では、相手の心に届くどころか、傷を残してしまう可能性があります。
②みんなの前で叱る
子どもにとって、教室にいる全員の前で厳しく注意されることは、とても強いストレスになります。
恥ずかしさや屈辱感から心を閉ざしてしまうこともあり、行動を見直すどころか、大人に対して反発心を強めてしまう可能性があります。
③感情のままに叱る
イライラや怒りがそのまま出てしまうと、子どもには伝えたい内容よりも、怖い雰囲気や圧力の方が強く伝わってしまいます。
感情が激しくぶつけられると、内容が届かず、子どもは萎縮してしまいます。
④長時間しつこく叱る
過去のことを何度も引き合いに出して長時間叱ると、子どもは次第に話を聞かなくなります。
頭では理解していても、感情が追いつかず、「またか」と感じてしまうと、学ぶ意欲すら失われることがあります。
⑤その場の空気に流されて叱る
実際には一部の子の行動が原因だったとしても、場の雰囲気に流されて全体を叱ってしまうと、問題の本質があいまいになり、誰にも伝わらない叱り方になってしまいます。
努力していた子まで否定されたように感じてしまい、学級全体の雰囲気が悪くなることもあります。
⑥叱ることを言葉ではなく態度で示す
一見、強い印象を与えるように思えますが、子どもにとっては「見放された」「無視された」と大きなダメージを感じることがあります。
また、「どうして出ていったのか?」「何がいけなかったのか?」が伝わらないため、子どもは自分自身でふり返ることができず、不安や混乱、不信感を残してしまう結果につながります。
叱る効果を高めるための準備3選

叱ることの効果は、叱る前の準備によって大きく変わります。
単にその場の行動を正すことを目的にするのではなく、「この子にどう育ってほしいか?」「どんな姿に近づけたいか?」を見すえながら、日頃の関わりを丁寧に重ねておくことが何よりも大切です。
ここでは、叱る効果を高めるための“土台づくり”として、大切にしたい3つの準備についてお伝えします。
- 子どもたちと信頼関係を築く。
- 普段から子どもたちを褒める。
- どんな時に叱るか明確に線引きする。
子どもたちと信頼関係を築く
信頼のないところに、叱る言葉は届きません。
たとえ正論を言ったとしても、「この先生、いつも怒ってばかり」「自分のことわかってくれていない」と思われていたら、子どもたちは耳を閉ざしてしまいます。
反対に、「この先生はちゃんと自分のことを見てくれている」「きっと自分のために言ってくれている」と思えたとき、子どもは叱られた言葉の中に愛情を感じ、素直に受け取ることができるのです。
信頼関係は、一朝一夕では築けません。日々の小さな声かけや、ちょっとした変化に気づくまなざし、困ったときにそっと寄り添う姿勢が積み重なって、ようやく育まれていきます。
普段から子どもたちを褒める
叱るためには、子どもたちをたくさん褒めましょう。
子どもたちは、「この先生は、自分のよいところもちゃんと見てくれている」と感じていると、叱られる場面でも「嫌われたわけじゃない」と安心できます。
逆に、叱られるときだけ注目されている子は、「どうせ自分は悪い子だ」と思い込んでしまいやすいので注意が必要です。
特に意識したいのは、目立つ子だけでなく、がんばっているけれど気づかれにくい子にもスポットを当てることです。
「集中して取り組んでくれていて素晴らしいよ」「自分から行動できてすごいね」という何気ない一言が、子どもたちにとっては大きな自信となります。
日常的に褒めてもらっている子は、「叱る言葉=否定」とは受け取りません。むしろ、「本当に大事に思ってくれているから、教えてくれているんだ」と前向きにとらえやすくなります。
どんな時に叱るか明確に線引きする
「何で叱るのか?」の基準があいまいだと、子どもは混乱します。
あるときは見逃されたのに、あるときは強く叱られる。相手によって、タイミングによって対応が違う。そんなことが続くと、子どもたちは「これはやっていいの?ダメなの?」と迷い、自分で考える力を育てることができません。
だからこそ、「ここだけは絶対に見過ごさない」という明確な線引きを事前に決めておくことが大切です。
- 生命に関わること…ふざけて窓から身を乗り出す、人に物を投げる、暴力など命に関わる行動
- 人権に関わること…友だちを見下す発言、悪口やからかい、仲間外しなどの人を傷つける言葉や態度
- 犯罪に類すること…器物破損、故意に物を隠す、盗むなど犯罪に関わるような行動
このような「叱るべき場面」をあらかじめ明確にしておくことで、一貫した姿勢が子どもに伝わり、日頃の指導にも信頼感が生まれます。
効果的な叱り方の13のポイント

実は、叱るという行動には“技術”が必要です。 その場の感情や雰囲気だけで叱ってしまうと、伝えたいことが届かないばかりか、関係がこじれてしまうこともあります。
ここでは、効果的に叱るための13のポイントを、詳しく解説していきます。
- 冷静な気持ちで話す。
- 子どもの高さに合わせて体の位置を低くする。
- 行動を具体的に指摘する。
- 基本的に一対一で伝える。
- 伝える内容はひとつに絞る。
- タイミングを見極める。
- 目を見てゆっくり話す。
- 改善策を一緒に考える。
- 気持ちを代弁する。
- 他の子と比較しない。
- 叱る理由をしっかり伝える。
- 前向きな言葉でフォローする。
- 自分の態度をふり返る。
すべてを一度に実践する必要はありません。少しずつ意識することで、子どもとの関わり方が大きく変わっていきます。
①冷静な気持ちで話す
叱るときに一番大切なのは、まず自分自身が落ち着いていることです。
感情に任せて怒鳴ってしまうと、子どもは「怖い」という印象ばかりが残ってしまい、本当に伝えたい内容が頭に入りません。
もし怒りの感情が込み上げてきてしまったときは、いったん深呼吸をする、一言「ちょっと待ってて」と伝えてその場を離れるなど、自分を落ち着ける工夫をしましょう。

日ごろからストレスをため込まず、心にゆとりをもって過ごすことが大切です。
先生の仕事は忙しく、気を張る場面も多いため、意識して心と体を整える時間を持つことを心がけましょう。
②子どもの高さに合わせて体の位置を低くする
誰かに叱られるときに上から見下ろされると、自然と身構えたり、委縮したりします。
子どもにとって大人は、それだけでも大きくて強い存在です。その大人が立ったまま叱りつけてくると、恐怖や反発の感情が先に立ち、内容が届かなくなってしまうのです。
叱る前に、そっとしゃがんで子どもの目線に合わせる。それだけで、子どもは「話を聞いてもらえる」「自分に向き合ってくれている」と感じ、表情が変わります。
子どもの目を見て、落ち着いた声でゆっくり話すことで、「責める」ではなく「伝える」関わりを持つことができるようになります。
③行動を具体的に指摘する
「ちゃんとしなさい」や「いい加減にして」といった曖昧な言葉では、子どもは何がいけなかったのかが分かりません。
たとえば、「廊下を走っていたね」「列に割り込んでいたよね」といったように、その場での具体的な行動をしっかりと言葉にして伝えることが大切です。
行動を明確に示されることで、子どもは「自分は何をしたのか?」「なぜそれがいけないのか?」をふり返ることができるようになります。
④基本的に一対一で伝える
人前で叱られることは、子どもにとって大きな恥ずかしさや屈辱感を伴います。
特に友達の前では、内容よりも「自分が恥をかいた」「みんなに見られている」という感情の方が強くなってしまいます。
叱るべきことがあるときほど、その子の気持ちを守る姿勢を忘れないことが信頼につながります。
「少しだけ廊下で話そうか?」と声をかけるだけで、子どもは安心して耳を傾ける準備ができます。
⑤伝える内容はひとつに絞る
「これもダメだったし、あれもできてないし…」と次々に指摘すると、子どもは混乱し、何を直せばいいのか分からなくなってしまいます。
その場で伝えるべきことは、一つに絞ってシンプルに。「今日、伝えたいのはこれだけ」と明確にすることで、子どもも理解しやすくなります。
たった一つのことに集中するだけで、子どもは受け止めやすくなり、自信を失わずにすみます。

伝えたいことが複数ある場合はどうするの?

まずは一つのことに絞って伝え、子どもがそれをきちんと理解できたことを確認してから、次の話題に進むようにしましょう。
そうすることで、子どもは混乱せず、落ち着いて一つひとつの内容を受け止めることができます。
⑥タイミングを見極める
叱るのは必ずしもその場ですぐでなくて構わない場合があります。
たとえば、子どもが気持ちを整理できていないときや、興奮しているとき、混乱しているときには、話をしても届きません。
まずは落ち着く時間をとることで、子どもは話ができる状態になります。
「今は話さない方がいいかもしれないね。」「後でゆっくり話そう」と伝えることも、立派な指導のひとつです。
⑦目を見てゆっくり話す
子どもの目をしっかり見て、落ち着いた口調でゆっくり話すだけで、言葉の伝わり方は大きく変わります。
視線を合わせながら話すことで、「あなたにきちんと伝えたい」という気持ちが自然と伝わり、子どもも話を真剣に受け止めやすくなります。
しかし、子どもの目を見ようとしたときに視線が合わなかったり、そわそわと落ち着かない様子だったりする場合は、こちらの話が十分に届いていない可能性があります。
そんなときは、いったん深呼吸を促したり、「私の目を見てくれる?」と優しく声をかけたりして、話を受け止められる状態を整えることが大切です。
⑧改善策を一緒に考える
「何が悪かったか?」だけで終わらず、「次はどうすればいいと思う?」と未来に視点を向けることで、子ども自身が考え、行動を変える力を育てることができます。
先生から提案するのもよいですが、まずは子どもからアイデアを引き出す問いかけを大事にしましょう。
「次はどう声をかけたらいいかな?」「今度、◯◯するときはどのように行動すればいいと思う?」と具体的に聞いてみると、子ども自身の中に気づきが生まれやすくなり、改善につなげることができます。
⑨気持ちを代弁する
「イライラしていたのかな?」「もしかして不安だった?」など、子どもの気持ちに寄り添う言葉を添えると、心の扉が開きやすくなります。
感情には理由があるものです。「叱る=責める」ではなく、「わかってあげよう」という姿勢が伝われば、子どもは素直に話を聞こうという気持ちになります。
気持ちを理解してもらえるだけで、子どもは落ち着きを取り戻しやすくなります。
叱る前に一度、子ども側の背景を想像してみることが、よりあたたかい関わりへの第一歩になります。
⑩他の子と比較しない
「○○さんはできてるのに、あなたはどうして?」「みんなはやっているのに…」といった比較は、自信を奪い、自己否定の気持ちを強めてしまいます。
叱るときは、「あなたの行動」だけに焦点を当てて話すことが原則です。
比較されると「認めてもらえない」という感覚が残りやすく、関係がこじれやすくなります。
「あなたのことを見て話しているよ」と伝えるだけで、子どもは安心して話を受け止めやすくなります。
⑪叱る理由をしっかり伝える
「どうしてそれがいけなかったのか?」「誰がどんな気持ちになったのか?」「何を大切にしてほしいのか?」など、納得できる理由があると、子どもは内容を理解しやすくなります。
ただの禁止ではなく、目的や背景を伝えることで、子どもは自分の行動を見直すきっかけになります。
「ルールを守る」ことの裏にある、人とのつながりや思いやりを一緒に考えられる関わりを大切にしましょう。
⑫前向きな言葉でフォローする
叱ったあとこそ、関係づくりのチャンスです。「大丈夫」「次はうまくいくよ」「信じてるよ」といった前向きな言葉を添えることで、子どもは安心し、次の行動に希望をもつことができます。
叱ることで関係が終わるのではなく、むしろそこからより良い関係を築くことができることを意識しながら、子どもに寄り添って丁寧にフォローすることが大切です。
日常のちょっとした関わりやあいさつが、「自分は見捨てられていない」と感じさせる土台になります。
⑬自分の態度をふり返る
「今日の叱り方はどうだったかな?」「落ち着いて話すことができたかな?」と、自分の関わりをふり返る習慣は、子どもと向き合う上で必須です。
うまくいった点、改善できそうな点を見直すことで、自分自身も成長することができます。
「完璧に叱ろう」と思う必要はありません。「伝わる叱り方」に近づこうとする意識が、子どもとの関係を育てていきます。
まとめ
今回は叱ることの本当の意味や避けたいNGな叱り方、そして信頼関係を壊さずに伝えるための13のポイントについて紹介しました。
- 叱ることは、責めることではなく、次の行動を育てる声かけであるということ
- 叱る前の準備や日頃の信頼関係づくりが、叱りの効果を大きく左右するということ
- 叱るときには、冷静さ・具体性・タイミング・フォローが重要であること
この記事を読んだことで、子どもの行動だけでなくその背景に目を向ける視点、そして信頼関係を守りながら必要なメッセージを届ける方法が見えてきたのではないでしょうか。
子どもを叱るというのは、先生にとって避けて通れない場面ですが、その叱り方ひとつで、子どもの表情が暗くなってしまうこともあれば、目の輝きが戻るような関わりになることもあります。
つまり、叱るという行為は「心の届け方次第」なのです。
今日から少しずつ意識を変えて、子どもとの関係を深めながら前向きな成長を支える叱り方を実践していきましょう。