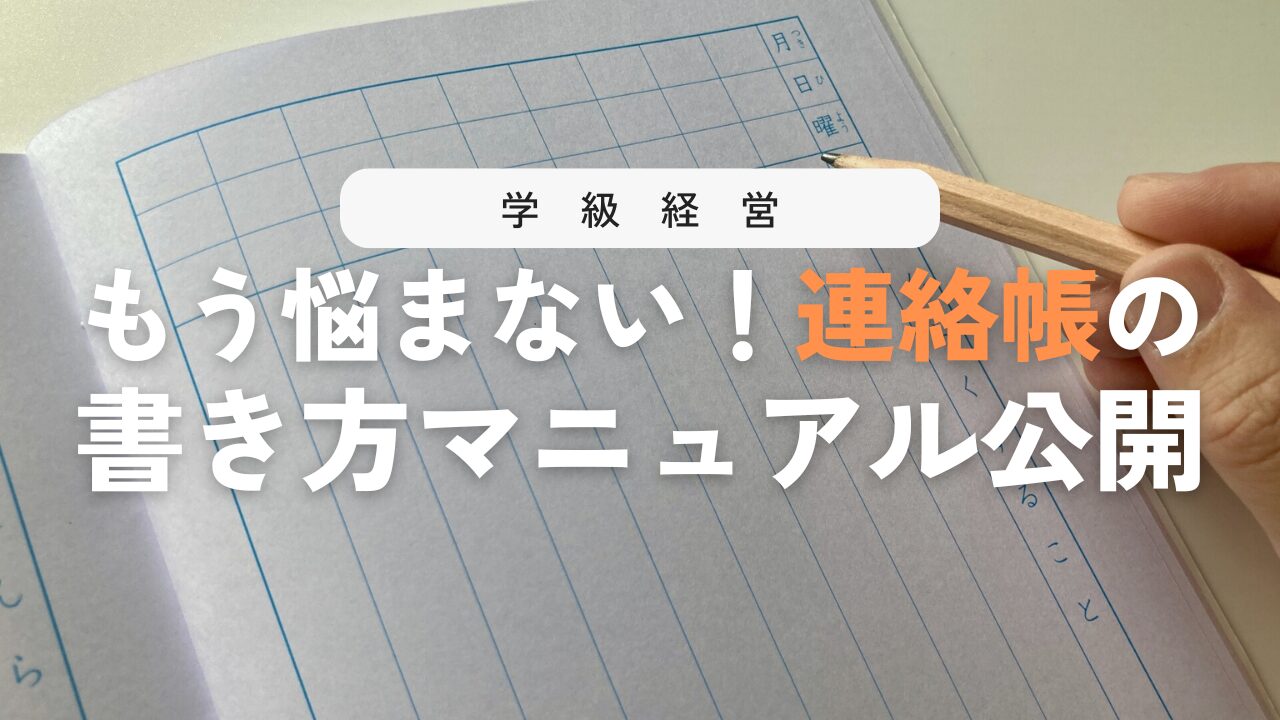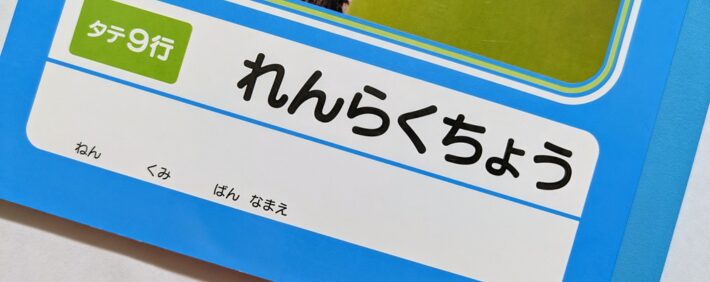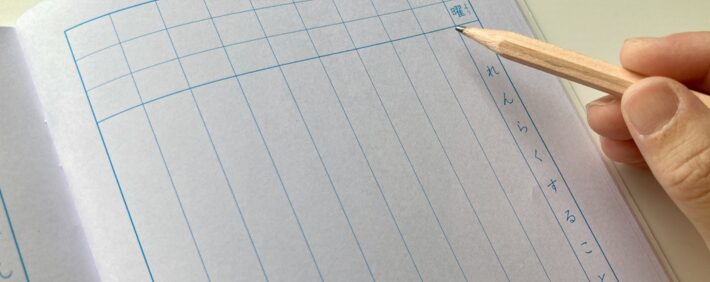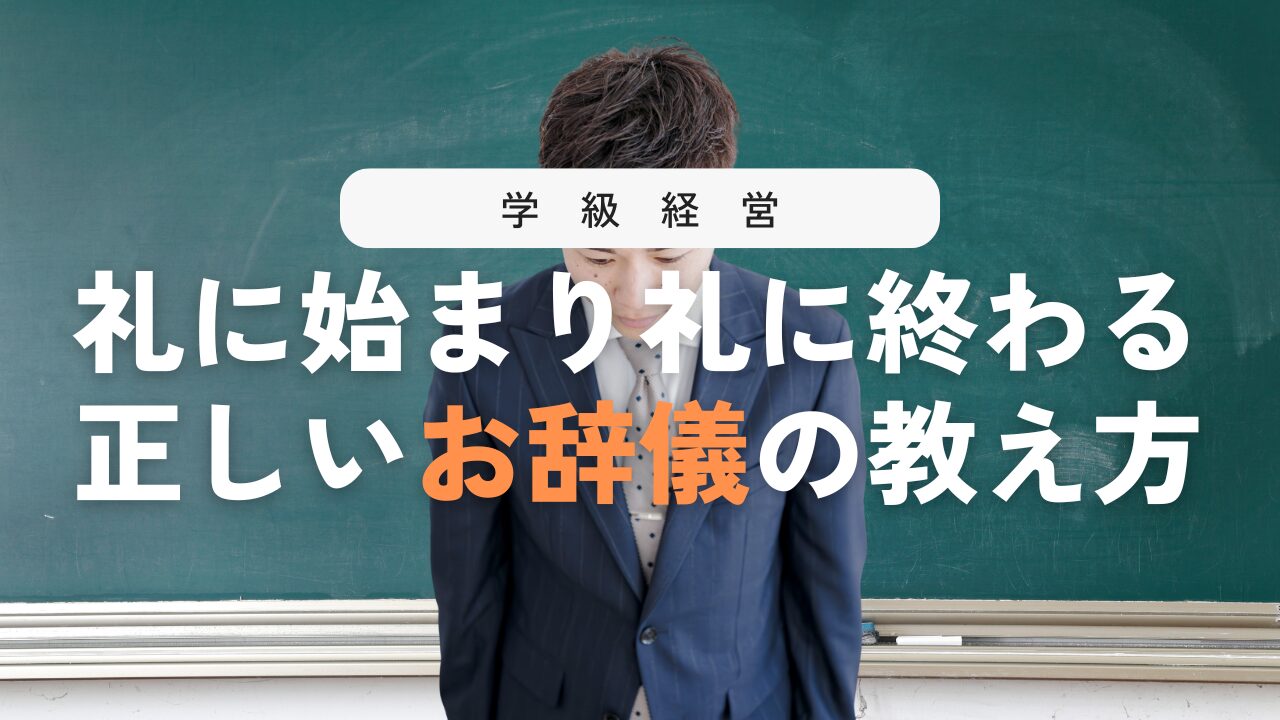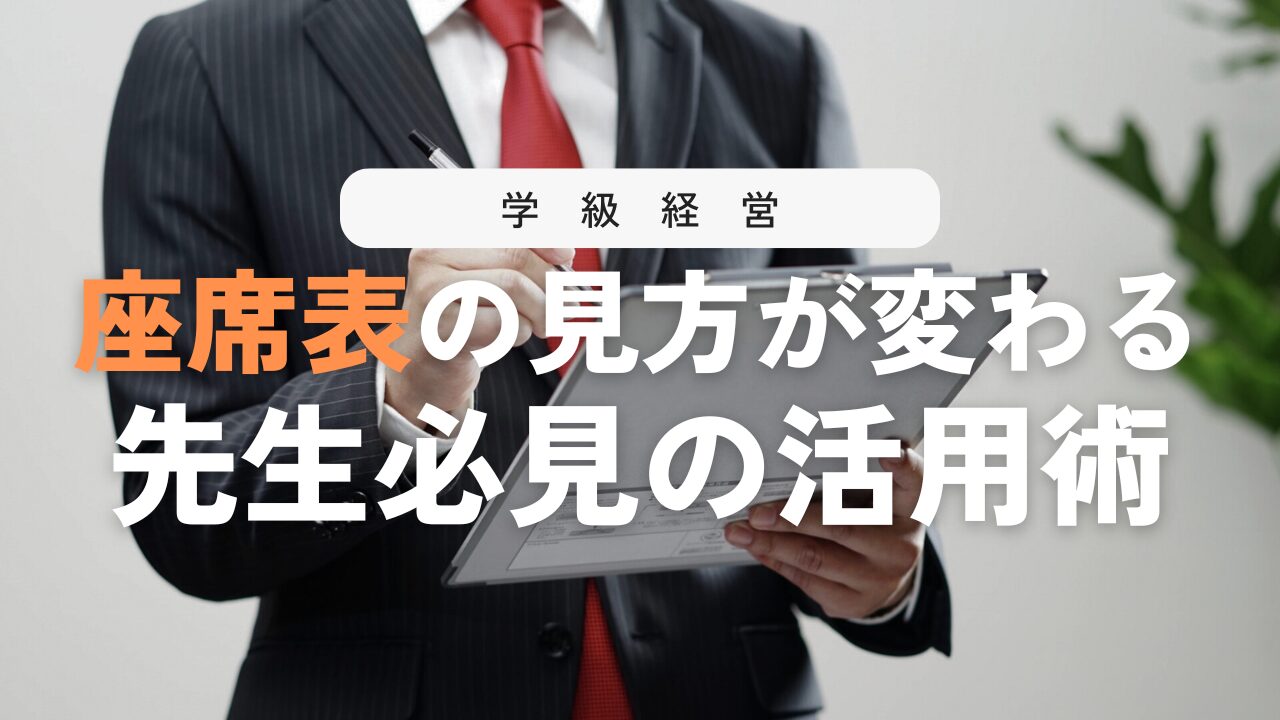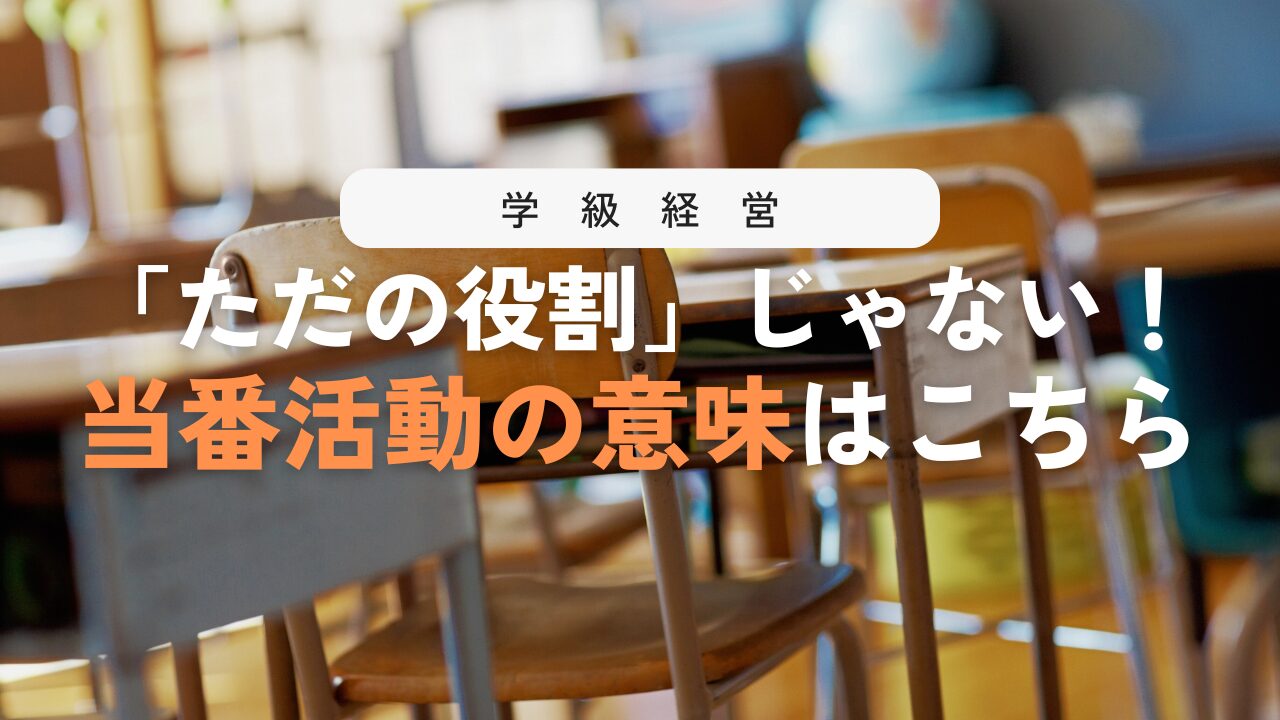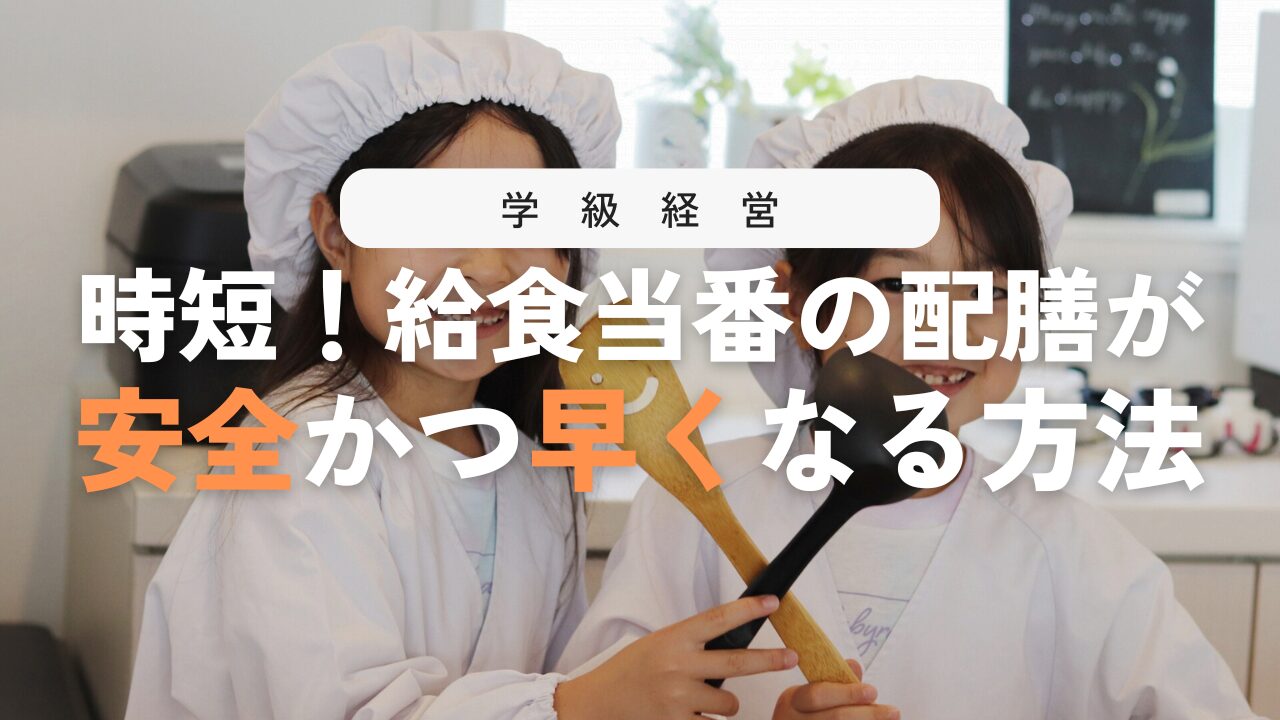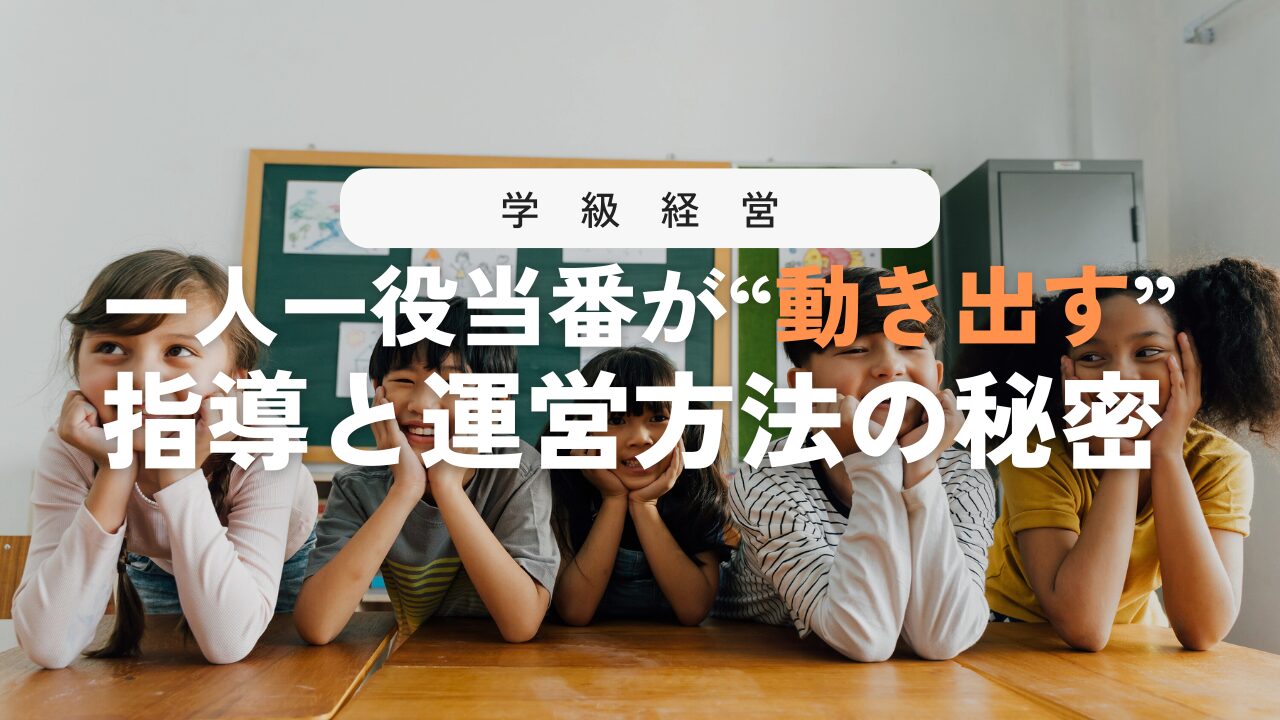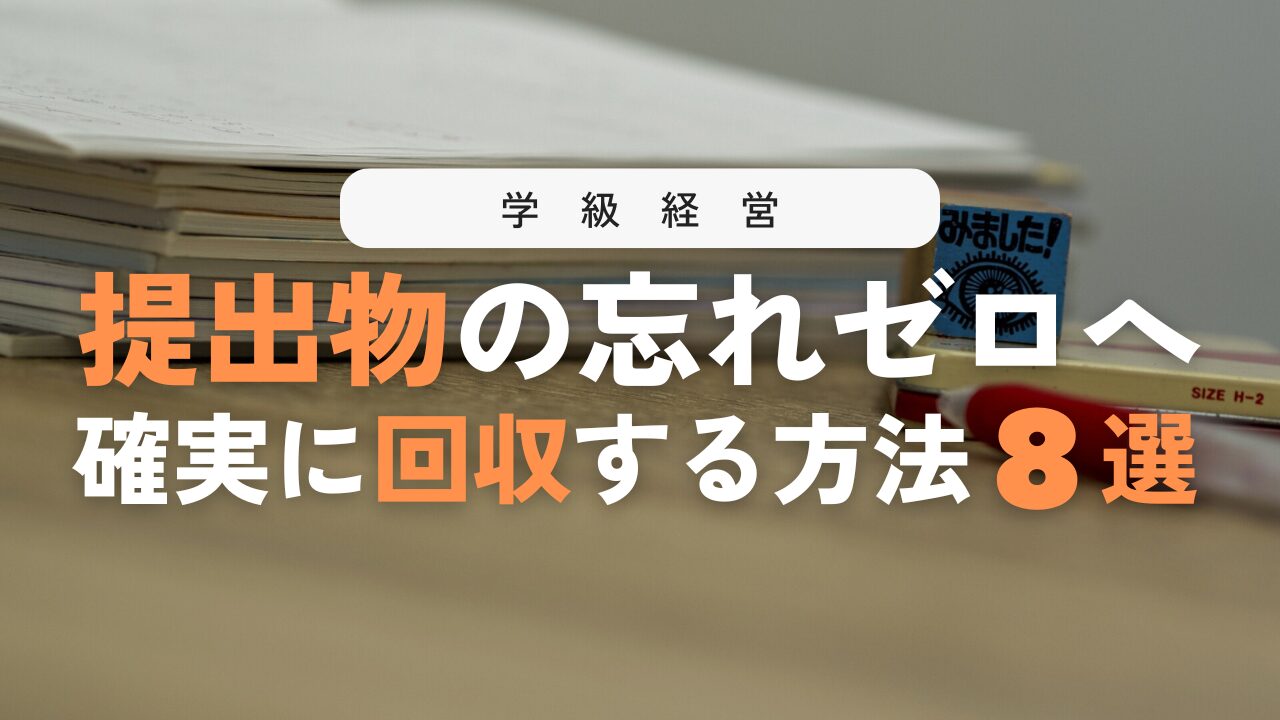どうも、まっつーです。
先生が保護者との連絡を取り合う中で、「連絡帳に何を書けばいいかわからない…」「うまく伝えたつもりなのに、保護者に誤解されてしまった…」とお悩みではありませんか?
私自身も、初任のころは連絡帳の文面に何度も苦労しましたが、ひとつひとつ経験を積んできたからこそ伝えたい、“失敗しない連絡帳の書き方”があります。
今回の記事は、先生が保護者に向けて連絡帳を書くときの基本ルールや返信用の文例25選をわかりやすく解説します!
この記事は以下のような人におすすめ!
- 連絡帳の内容に自信がない
- 連絡帳を書くときに、いつも時間がかかってしまう
- 言葉の選び方に自信がなく、毎回迷ってしまう
- 保護者との連絡帳でのやりとりをスムーズにしたい
この記事を読めば、連絡帳を書くことに迷いがなくなり、保護者との信頼関係が深まり、学級経営にも安心して取り組めるようになります。
最近では、紙の連絡帳(アナログ式)だけでなく、アプリやメール、チャット、掲示板などのデジタルツールを活用した「デジタル連絡帳」を導入する学校が増えてきています。
この記事で紹介している連絡帳の書き方は、アナログ式・デジタル式のどちらでも参考にできる内容となっています。
連絡方法が変わっても、「伝える相手への思いやり」や「わかりやすく簡潔に伝えること」の大切さは変わりません。
この記事を書いた人↓
Profile
【経歴】
・19年間小学校で正規教員として勤務
・退職→無職
・現在はサイトの記事を執筆・発信中
【資格】
・小学校教諭二種免許状(全科)
・中学校教諭一種免許状(社会)
・高等学校教諭一種免許状(地理歴史)
・高等学校教諭一種免許状(公民)
連絡帳の役割とは?

連絡帳は、子どもが毎日学校に持ってくることになっている連絡ツールです。
家庭と学校をつなぐ役割を果たし、保護者と先生の情報共有に欠かせない存在です。
この連絡帳には、子どもの学びを支え、家庭と学校をつなぐための4つの役割が込められています。
- 学習予定や持ち物の確認
- 保護者からの事務的な連絡の手段
- 心配事やトラブルの共有・解決に向けた橋渡し
- 挨拶や感謝を伝えるツール
①学習予定や持ち物の確認
連絡帳は、子どもたちが時間割や学習予定、必要な持ち物などを記入するために、毎日活用されています。
先生が黒板に書いた内容を写したり、話を聞いて自分でメモを取ったりすることで、情報を整理し、翌日の準備を主体的に行う力を養っていきます。
また、忘れ物をしてしまったときには、「明日、◯◯を持ってくる」といった内容を自分で記録しておくことで、次の日に備えて持ち物を確認できるようになります。
②保護者からの事務的な連絡の手段
「欠席します」「病院に行くために遅刻します」「給食を食べずに早退します」など、保護者からの事務的な連絡は、連絡帳を通じて受け取ることがよくあります。
こうした内容があらかじめ連絡帳に記載されていると、朝の忙しい時間帯でも保護者からの連絡をスムーズに受け取ることができ、先生としては非常に助かります。
また、事前に情報が入っていれば、「今日は遅れて登校する予定だったな」「明日は欠席する予定だから、今日のうちに配布物を渡しておこう」といったように、子どもへの対応を計画的に進めることができます。
③心配事やトラブルの共有・解決に向けた橋渡し
子どもに不安な様子が見られるときや、友達とのトラブルがあった場合などにも、連絡帳は活用されます。
早い段階で保護者から学校へ情報を届けることで、先生も必要な声かけや対応を考えることができ、問題の早期解決にもつながります。また、先生からも保護者へ伝える場合もあります。
ただし、いじめや家庭のセンシティブな内容は、連絡帳では簡潔にふれ、詳しい相談は電話や面談で伝えるのが安心です。
連絡帳は子どもの目にもふれることがあるため、伝える方法を工夫する必要があります。
④挨拶や感謝を伝えるツール
新年度や学期の始まりには、保護者の方から「今年度もよろしくお願いします」、学期の終わりには「丁寧にご指導いただきありがとうございました」といったご挨拶や感謝の言葉をいただくことがあります。
こうした言葉が連絡帳を通して届けられると、先生にとってはとても励みになり、「また明日も頑張ろう」という気持ちにつながります。
また、保護者の方が家庭でのお子さんの様子を添えて書いてくださると、学校での姿と結びつけてより深く理解することができ、指導や対応の質を高めることにもつながります。
連絡帳の書き方の基本ルール
連絡帳を保護者に書く際の基本ルールとして、次のような3つのポイントがあります。
連絡帳の3つの基本ルール
- 書き出しと結びの挨拶を入れる
- 伝えたいことは簡潔に書く
- 日時や場所は詳細かつ正確に伝える
この基本を知っておくだけで、保護者とのやりとりがスムーズになり、信頼関係も深まりやすくなります。
①書き出しと結びの挨拶を入れる
まず、連絡帳を書くうえで大切にしたいのが、書き出しと結びの挨拶です。
- いつもお世話になっております。
- 大変お世話になっております。
- ご連絡ありがとうございます。
- 突然のご連絡失礼いたします。
- 初めまして。◯年◯組担任の◯◯と申します。
- 日頃よりご配慮いただき、ありがとうございます。
- 〇〇さんのがんばっている様子をお伝えしたく、連絡帳にてご報告いたします。
- いつも〇〇さんのご家庭でのご支援に助けられております。ありがとうございます。
- このたびは、ご心配をおかけして大変申し訳ございません。
- ご連絡が遅くなってしまい、申し訳ございません。○○についてご報告いたします。
- ○○の件につきまして、ご不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。
- お手数をおかけして申し訳ございません。○○についてご説明いたします。
- よろしくお願いいたします。
- 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
- 今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
- ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
- 何かお気づきの点がありましたら、お知らせいただけますと助かります。
- お気づきのことがございましたら、どうぞご遠慮なくお知らせください。
- お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。
- ご心配をおかけして申し訳ございません。今後も丁寧に見守ってまいります。
- 不愉快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
- 不安なお気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。今後このようなことがないよう努めてまいります。
先生の立場からすると、保護者とのやりとりは文字が中心となるため、感情や意図が伝わりにくいこともあります。
だからこそ、あたたかい挨拶の言葉があるだけで、「この先生は丁寧に対応してくれているな」「きちんと見てくれているな」と感じてもらえるのです。
逆に、急ぎの内容であっても、挨拶なしでいきなり本題に入ってしまうと、事務的で冷たく見えてしまうこともあります。
忙しい日々の中でも、心を込めた“ひと言のやりとり”が、信頼の積み重ねになります。
②要件は簡潔に書く
先生が書く連絡帳には、子どもの様子、授業中の出来事、友達とのトラブルへの配慮依頼なども含まれます。そのときに心がけたいのが、「要件は簡潔に書く」です。
つい丁寧に説明しようとするあまり、文章が長くなったり、話があちこちに広がってしまったりすることがあります。
しかし、ダラダラと説明を続けてしまうと、本当に伝えたい要点がぼやけてしまい、かえって誤解を生んだり、読み手の負担になったりすることもあるのです。
保護者もお忙しい中で連絡帳を見てくださっているので、相手が読みやすい文量と構成で伝えることを意識するとよいでしょう。
どうしても連絡帳の内容が長くなってしまう場合や、文章だけでは伝えきれない思いやニュアンスがあるときは、電話で直接お伝えするのがおすすめです。
③日時や場所は詳細かつ正確に知らせる
連絡帳で意外とミスが出やすいのが、日付や時間、場所に関する情報です。
たとえば、「○月○日の食物アレルギーに関する面談の件ですが、14:30より◯年◯組の教室でお待ちしております。」といったように、具体的な数字や予定をしっかり記すことがとても大切です。
「今度の木曜」や「学校にお越しください」など、あいまいな表現は避けるようにしましょう。
とくに保護者が共働きだったり、兄弟姉妹の行事が重なっていたりするご家庭では、正確な情報が命綱になります。
連絡帳の返信内容の文例25選

保護者からの連絡に対して、先生がどのように返事を書けばよいかがイメージできるように、連絡帳に記入する際の具体的な文例25選をご紹介します。
本来であれば、時間をかけて丁寧に返信を書きたいところですが、実際には空き時間(授業がない時間)が無かったり、子どもたちのいる教室内で慌ただしく対応せざるを得なかったりする場面も少なくありません。
それでも、保護者の方と安心して連絡帳を通じたやりとりができるように、返信しやすく、なおかつ思いが伝わるような内容をお伝えしていきます。
欠席の連絡の場合
【文例01】
【保護者】
いつもお世話になっております。
◯◯(子どもの名前)が昨夜から発熱しており、本日は大事をとって欠席させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
発熱とのこと、どうぞお大事になさってください。
また元気に登校されるのをお待ちしています。
【文例02】
【保護者】
お世話になっております。
〇〇が朝から吐き気があり、体調がすぐれないため本日はお休みします。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
体調が回復されることを願っています。
どうぞお大事になさってください。
遅刻の連絡の場合
【文例03】
【保護者】
いつもお世話になっております。
今朝、◯◯が軽い頭痛を訴えたため、様子を見て遅れて登校させます。
よろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
様子を見ていましたが、体調は安定しているようです。
今日は無理せず教室で過ごせるように配慮しました。
※子どもが登校後に記入
【文例04】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇は本日、通院のため病院の診察が終わり次第、登校いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
教室に到着後、スムーズに活動に入れました。
引き続き見守ってまいります。
※子どもが登校後に記入
早退の連絡の場合
【文例05】
【保護者】
いつもお世話になっております。
本日〇〇は、午後3時に病院での診察があるため、5時間目終了後に早退させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
お迎えありがとうございました。
明日も無理のないよう、様子を見てご登校ください。
【文例06】
【保護者】
お世話になっております。
本日〇〇は家庭の用事で14時頃に早退させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
本日はご対応ありがとうございました。
〇〇さんは最後まで落ち着いて学習していました。
また明日も元気に登校してくれるのを待っています。
【文例07】
【保護者】
いつもありがとうございます。
〇〇は習い事の発表会に参加するため、5時間目の終了後に早退させていただきます。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【先生】
お迎えありがとうございました。
〇〇さんは、発表会を楽しみにしている様子でした。
良い経験になりますよう、応援しています。
忌引きの連絡の場合
【文例08】
【保護者】
いつも大変お世話になっております。
〇〇の伯父が亡くなり、通夜・葬儀に参列するため、〇月〇日まで欠席いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
大切なご親族を亡くされ、お気持ちお察しいたします。
〇〇さんの学校での対応はご安心ください。
何かあればいつでもご相談ください。
【文例09】
【保護者】
いつもお世話になっております。
本日、〇〇の祖父が急逝し、忌引きのためしばらくお休みさせていただきます。
何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
【先生】
お知らせいただき、ありがとうございます。
〇〇さんが安心して過ごせるよう、学校でも準備しておきます。
どうぞご家族との時間を大切にされてください。
感染症の連絡の場合
【文例10】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇がインフルエンザと診断されましたので、しばらくの間欠席させていただきます。
登校再開の際には、治癒証明書を提出いたします。
よろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
〇〇さんの体調が一日も早く回復されることを願っています。
ご自宅でゆっくり休まれてください。
【文例11】
【保護者】
大変お世話になっております。
〇〇のインフルエンザの熱が下がり、食欲も戻ってきました。
明日からの登校に備え、念のためもう1日お休みさせます。どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
〇〇さんが快方に向かっていて安心しました。
ご家庭でのご判断に感謝いたします。
元気な姿での登校をお待ちしています。
【文例12】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇が発熱しており、インフルエンザの検査を受ける予定です。
結果が出るまでは自宅で休ませます。どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
検査結果が出るまで、どうぞ無理なさらずにお過ごしください。
何か必要があれば、遠慮なくご相談ください。
体育の見学の場合
【文例13】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇は足の痛みが続いているため、本日の体育は見学させていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
本日の体育は無理をさせず見学対応としました。
早く良くなるといいですね。
【文例14】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇は通院先の医師より、今週いっぱいは運動を控えるよう指示を受けました。
そのため、体育を見学させていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
医師の指示とのこと、承知しました。
今週は体育を見学とし、安全に過ごせるように配慮します。
引き続き様子を見て対応します。
相談事を受けた場合
【文例15】
【保護者】
いつもお世話になっております。
最近、〇〇が「授業が難しくてわからない」と話しています。
どの教科でつまずいているのか、気にかけていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
教室でも少し自信がなさそうな場面が見られました。
算数の文章題が不安のようでしたので、サポートを強めていきます。
ご家庭の声も参考にさせていただきます。
【文例16】
【保護者】
いつもお世話になっております。
〇〇が最近、持ち物をよく忘れてしまいます。
学校ではどのような様子でしょうか?
ご指導いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【先生】
たしかに数回、忘れ物がありました。
本人も気にしている様子でしたので、優しく声をかけながら見守っています。
学校でも引き続きフォローしてまいります。
【文例17】
【保護者】
いつもお世話になっております。
最近〇〇が「給食が食べきれない」と言うようになりました。
給食の時間や様子について、気になる点があれば教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ご連絡ありがとうございます。
給食では、食べる量を少し調整しています。
苦手なものは残して良いことを伝えています。
今後も、◯◯さんが安心して給食の時間を過ごせるように配慮してきます。
トラブルの報告を受けた場合
【文例18】
【保護者】
いつもお世話になっております。
友達と遊んだ際に、〇〇が少し怖い思いをしたようです。
どのような様子か見ていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【先生】
ご心配の点、承知しました。
休み時間などの様子を見守っていきます。
必要に応じてフォローいたしますのでご安心ください。
【文例19】
【保護者】
いつもお世話になっております。
最近〇〇が、「休み時間に友達とけんかした」と話していました。
様子を見ていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
【先生】
〇〇さんのこと、知らせていただきありがとうございます。
けんかの背景を探るために、お友達にも聞いてみました。
少し行き違いがあったようですが、話し合いで気持ちを伝え合うことができました。
今後も見守っていきます。
【文例20】
【保護者】
お世話になっております。
昨日、〇〇が友達に強い言葉を言われて落ち込んでいました。
どのような状況だったのか、学校でも様子を見ていただけるとありがたいです。
【先生】
ご心配をおかけしております。
対応についてお電話で詳しくご説明させていただきます。
本日中にご連絡いたします。
特に学校で起こったトラブルについては、保護者の多くが「どのような対応をしてもらえたのかを早く知りたい」と感じています。
連絡帳の場合、保護者が内容を確認するのは子どもが下校した後になるため、対応が遅い印象を与えてしまうこともあります。
そのため、トラブル対応後はできるだけ早く電話で保護者に直接連絡し、対応内容や現状を丁寧に伝えるとよいでしょう。
感謝の言葉をいただいた場合
【文例21】
【保護者】
いつも温かくご指導いただきありがとうございます。
〇〇が「授業が楽しい」と話しており、毎日いきいきと登校しています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
【先生】
ありがとうございます。
〇〇さんが楽しそうに学ぶ姿は、こちらも嬉しくなります。
これからも安心して過ごせるよう見守っていきます。
【文例22】
【保護者】
先日は個人面談で〇〇の様子を丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
家庭でも引き続き支えていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
【先生】
こちらこそ、面談で貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。
ご家庭と連携しながら支援していければと思います。
【文例23】
【保護者】
学校での困りごとにすぐ対応してくださり、ありがとうございました。
おかげさまで〇〇も安心して学校生活を送れているようです。
【先生】
ご丁寧にありがとうございます。
〇〇さんが安心して過ごせるよう、引き続きサポートしてまいります。
質問を受けた場合
【文例24】
【保護者】
いつもありがとうございます。
〇〇が「国語のテストがある」と話していましたが、日程が分かりません。
教えていただけますでしょうか?
【先生】
ご質問ありがとうございます。
国語のテストは〇月〇日の◯時間目を予定しています。
よろしくお願いいたします。
【文例25】
【保護者】
お世話になっております。
明日、雨が降った場合の遠足は中止になりますか。
予備日はありますでしょうか。
【先生】
ご確認いただきありがとうございます。
明日の遠足につきましては、当日の天候を見て最終的に判断いたします。
万が一中止となる場合は、◯月〇日に延期を予定しておりますので、ご安心ください。
実施の有無については、明日の◯時までに配信メールにてお知らせいたします。
まとめ
今回は、先生が保護者に向けて連絡帳を書くときの基本ルールや返信用の文例25選について紹介しました。
3つのポイント
- 書き出しと結びの挨拶を入れることで、丁寧な印象と信頼感が伝わること
- 伝えたいことは簡潔に、誤解のない表現で書くこと
- 日時や場所などの情報は、できるだけ具体的に正確に伝えること
この記事を読んだことで、「何を書けばいいかわからない」「うまく伝わっているか不安」といった悩みが少しでも軽くなり、自信をもって連絡帳を書けるようになったら嬉しいです。
連絡帳は、小さなノート1冊に見えて、実は先生と保護者が子どもの育ちを支える“かけ橋”のような存在です。
書き方ひとつで、不安を安心に変えたり、誤解を防いだり、子どもにとって嬉しいつながりを感じてもらえたりもします。
大切なのは、「型」よりも「心」です。文例はあくまでヒントとして受け取り、あなた自身の言葉で、保護者の気持ちに寄り添いながら丁寧に想いを届けていきましょう。
この記事を読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。以下のバナーをポチッとクリックして応援していただけると励みになります。よろしくお願いいたします。