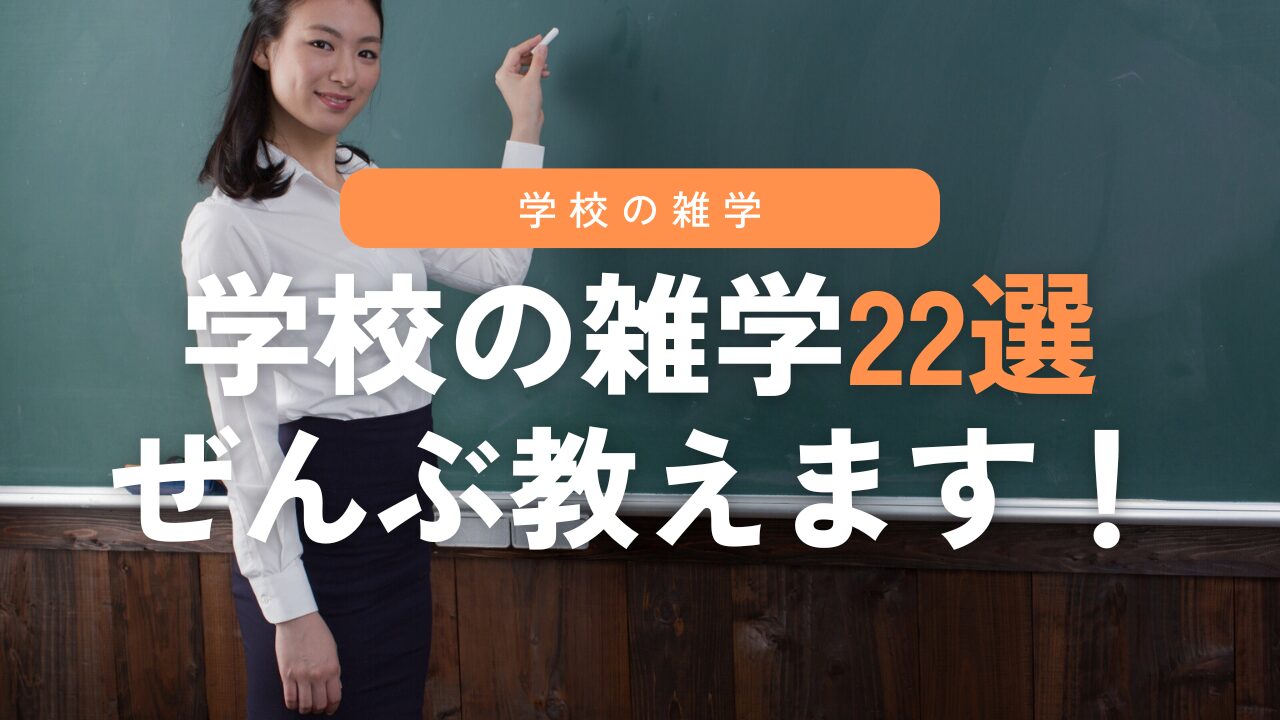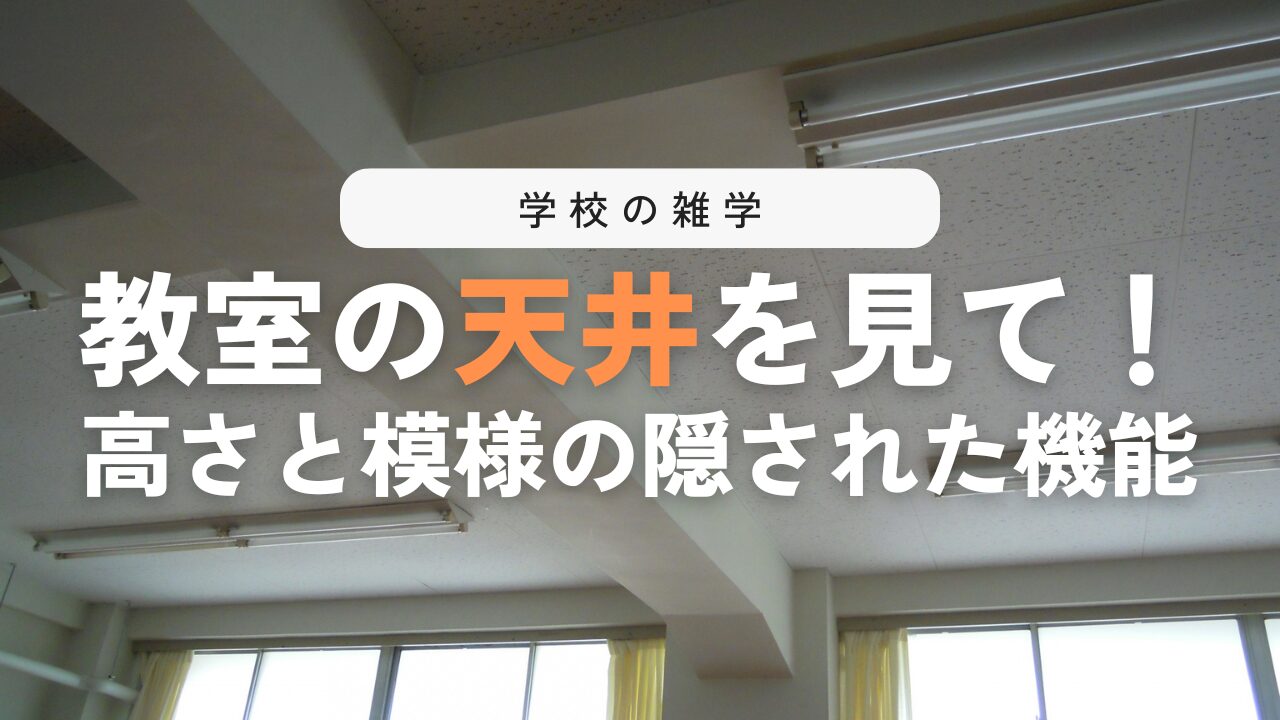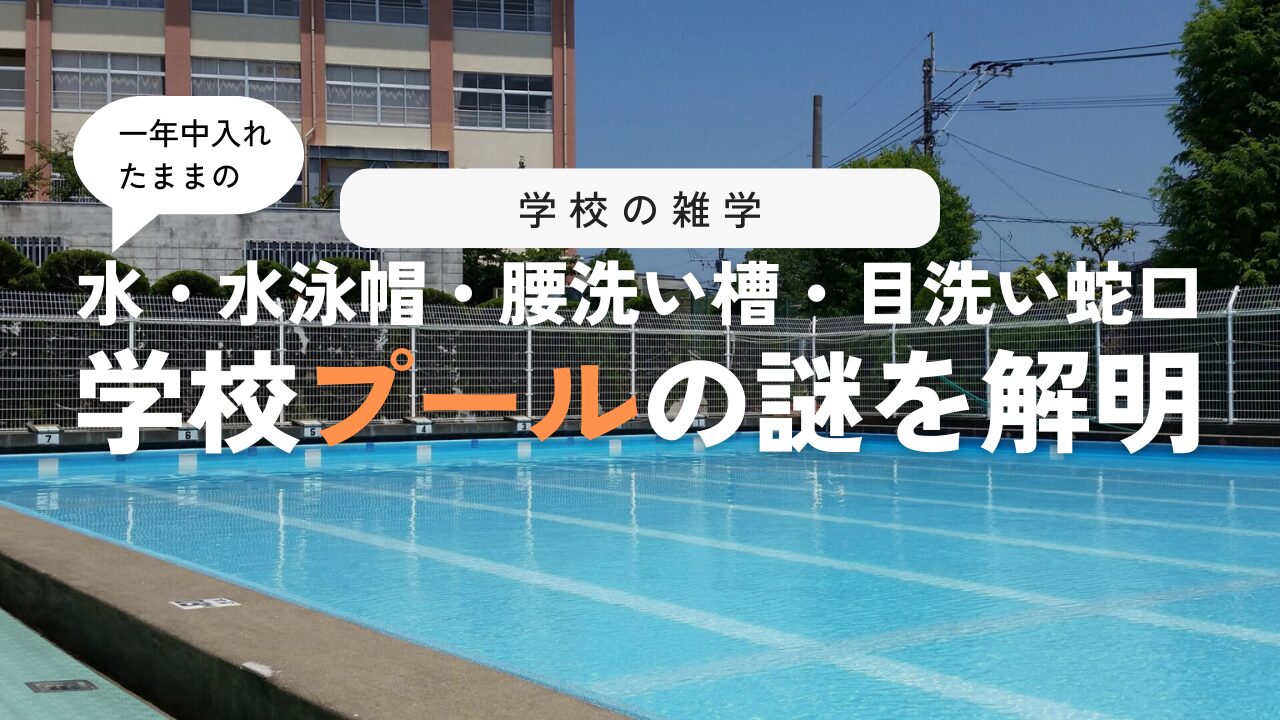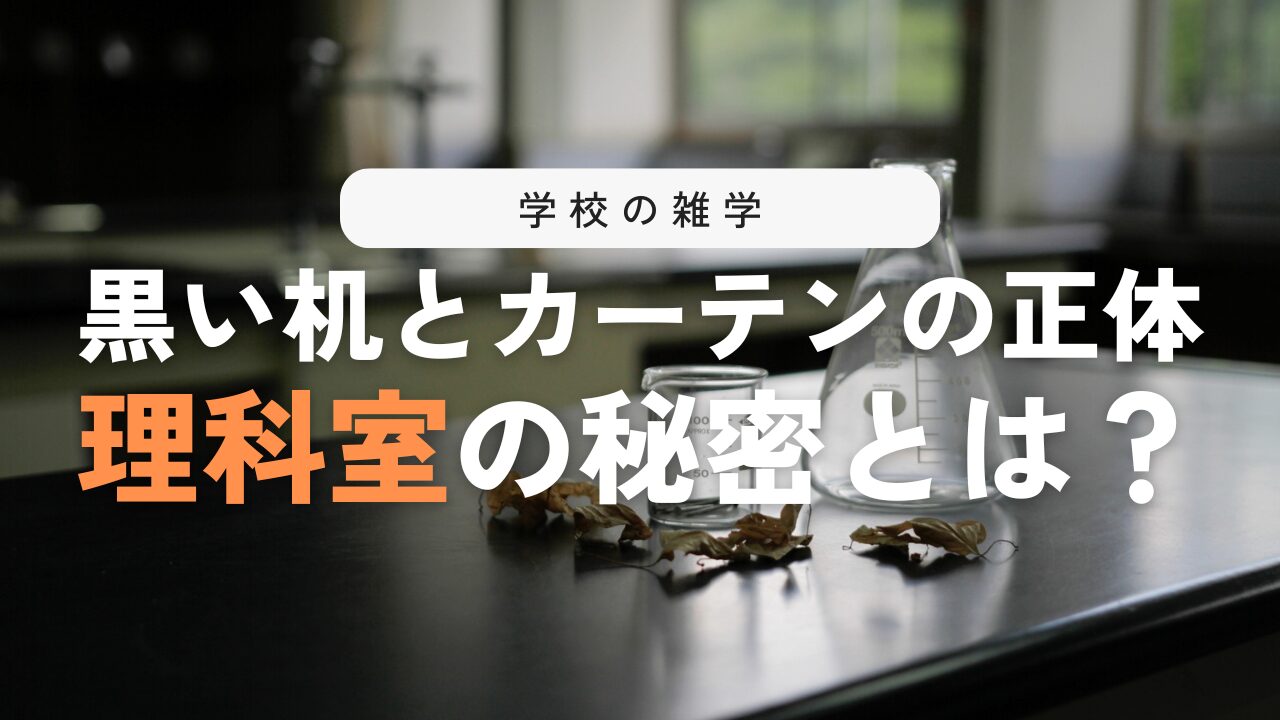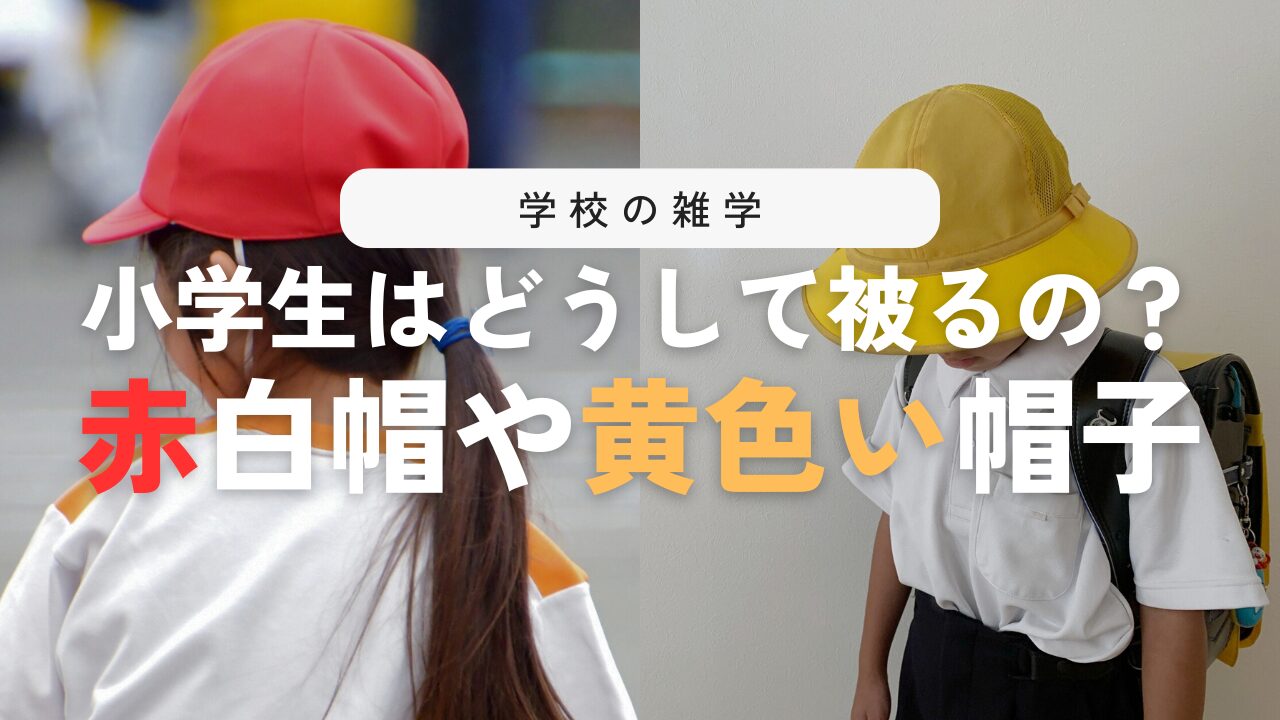【学校の雑学③】なぜ教室の窓は左側にあるのか?出入り口が2つあるのか?

どうも、まっつーです。
教室に入ったとき、ふと「なんで窓はいつも左側にあるんだろう?」と思ったことはありませんか?
また、「教室に出入り口が2つあるのはどうして?」と子どもに聞かれて、どう答えていいのか困った経験がある人もいるかもしれません。
今回の記事は、教室の窓が左側にある理由と、出入り口が2つ設置されている理由をわかりやすく解説します!
この記事を書いた人↓

窓が「左側」にある理由

「黒板に向かって座ると、左に窓、右に廊下」という教室の配置は、たまたまそうなっているわけではありません。その起源は明治時代にさかのぼります。
1895年(明治28年)、文部省が発行した「学校建築図説明及設計大要」という文書の中で、教室の設計に関する具体的な指針が示されました。
- 教室は長方形とする
- 窓は南または東南・西南を向ける
- 外からの自然光が、子どもたちの「左側」から入るように設計する
では、なぜ左側から光を入れる必要があったのでしょうか?
答え…日本人の多くが右利きだから
右利きの子が右側から光を受けると、自分の手でノートや教科書に影をつくってしまい、手元が暗くて書きにくくなるのです。
当時の教室には、今のような明るい照明はなく、自然光が唯一の明かり。だからこそ、子どもが文字を書きやすく、読みやすい環境をつくることが最優先だったのです。
そしてもうひとつの理由が、「南向きの窓」です。南側は一年を通して太陽の光が入りやすく、特に冬でも明るい光が差し込むため、安定した採光が期待できるのです。
このように、窓の位置には視覚の負担を減らし、集中力を高めるための深い配慮があるのです。
図工室や美術室だけ窓の向きが違う?

例外もあります。それが図工室や美術室です。図工室や美術室の窓は、多くの場合「北側」に設置されています。
それはなぜかというと、図工や美術の授業では影の向きが変わらない安定した光が必要だからです。
南向きの窓からは直射日光が入り、時間帯によって光の角度や強さが変わってしまいます。
これでは、デッサンなどで使うモデルの影の形が刻々と変わってしまい、正確に描くことが難しくなってしまうのです。
その点、北側の窓から入る光は柔らかく、影の変化も少ないため、作品制作に集中できる環境が整いやすいのです。

学校によっては、図工室や美術室を校舎の北側に配置することで、自然と北向きの窓が確保されるように設計されている場合もあります。
教室の出入り口が2つある理由

次に、「教室の出入り口が2つある理由」にも触れてみましょう。
教室の出入り口は、一般的に「前方(教壇近く)」と「後方(教室の後ろ側)」の2か所に設けられていることが多いです。
この構造にも、2つの理由があります。
- 非常時の避難経路としての配慮
- 動線の分離で教室運営がスムーズになる
非常時の避難経路としての配慮
災害が起きたとき、出入り口が1つしかないと、避難が集中してしまい混雑やパニックが起こりやすくなります。
また、その1つのドアが煙や火、がれきなどでふさがれてしまった場合や、地震によってドアがゆがんで開かなくなったりした場合は、逃げ道がなくなるというリスクも考えられます。
そこで、教室に2つのドアを設けることで、前方・後方どちらからでも安全に避難できる経路を確保することができ、命を守るための重要な安全設計になっているのです。
動線の分離で教室運営がスムーズになる
教室前方の出入り口は、先生が出入りしたり、教材を運び入れたりするときに便利な位置にあります。
一方、後方の出入り口は、子どもがトイレや保健室へ行くときに、授業の妨げにならずに静かに出入りできるように工夫されています。
このように、出入り口を2か所に設けることで、「先生や授業のための動線」と「子どもたちの生活の動線」を分けることができるのです。
また、出入り口が2か所あることで、一方を「入口」、もう一方を「出口」として使い分けることができ、教室内の人の流れを一方向に整えることができます。

新年度の準備で机やイスを移動する際は、一方のドアから不要な机やイスを廊下に出し、もう一方のドアから他の教室から運ばれてきた机やイスを入れると、作業がとてもスムーズに進むよ。
まとめ
今回は教室の窓が左側にある理由と、出入り口が2つ設置されている理由について紹介しました。
- 窓が左側にあるのは、右利きの子どもが文字を書きやすく、手元が影にならないようにするための工夫であること
- 北向きの窓は、図工室や美術室などで採用されることが多く、時間帯によって影の向きが変わりにくい安定した自然光を取り入れることで、作品制作に集中できるようにするための工夫であること
- 出入り口が2か所あるのは、非常時の安全な避難経路の確保と、授業と生活の動線を分けて学習環境を保つための設計であること
この記事を読んだことで、「教室のつくりは、なぜこうなっているのか?」という子どもや保護者の素朴な疑問に、歴史的背景を交えながら自信を持って答えることができるのではないでしょうか?
教室という空間は、単に「授業を受ける場所」ではなく、子どもたちが安心して学び、集中し、成長していくための舞台です。
そして、この舞台は明治時代から今に至るまで、多くの工夫や配慮によってつくられてきました。
今回の記事の内容を、教室での会話や保護者会でのちょっとした雑談に使っていただけると嬉しいです。