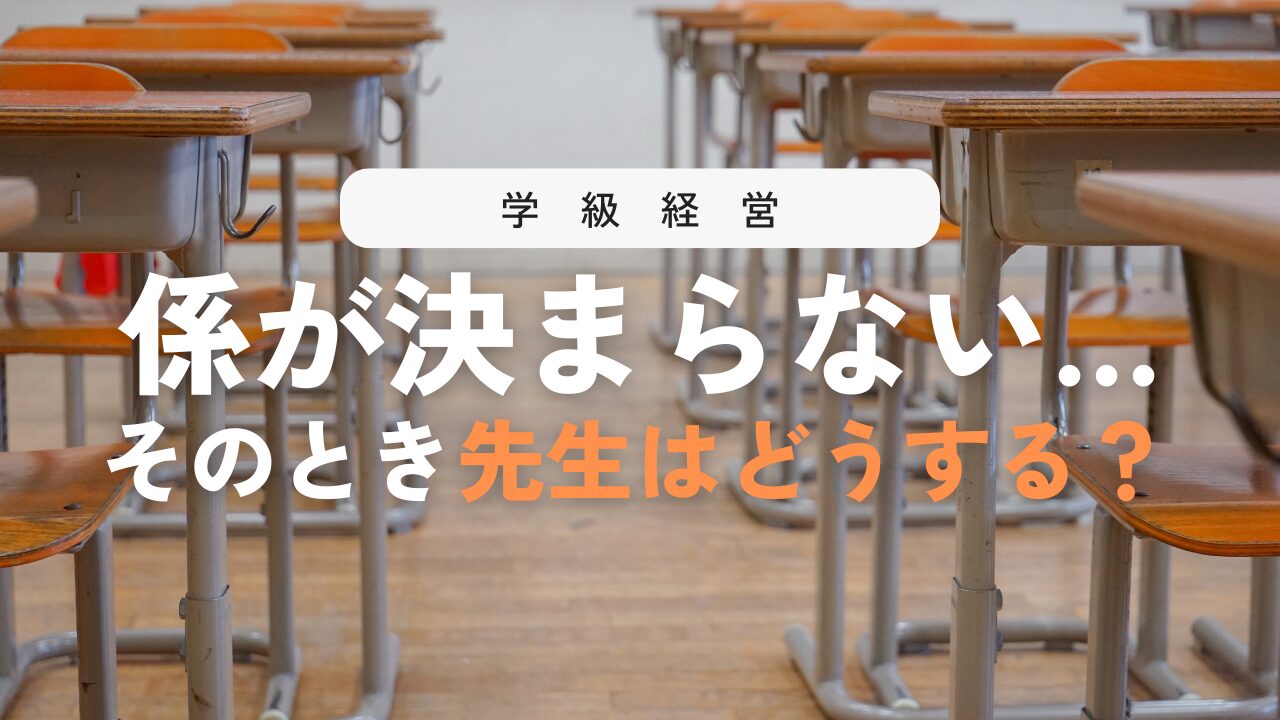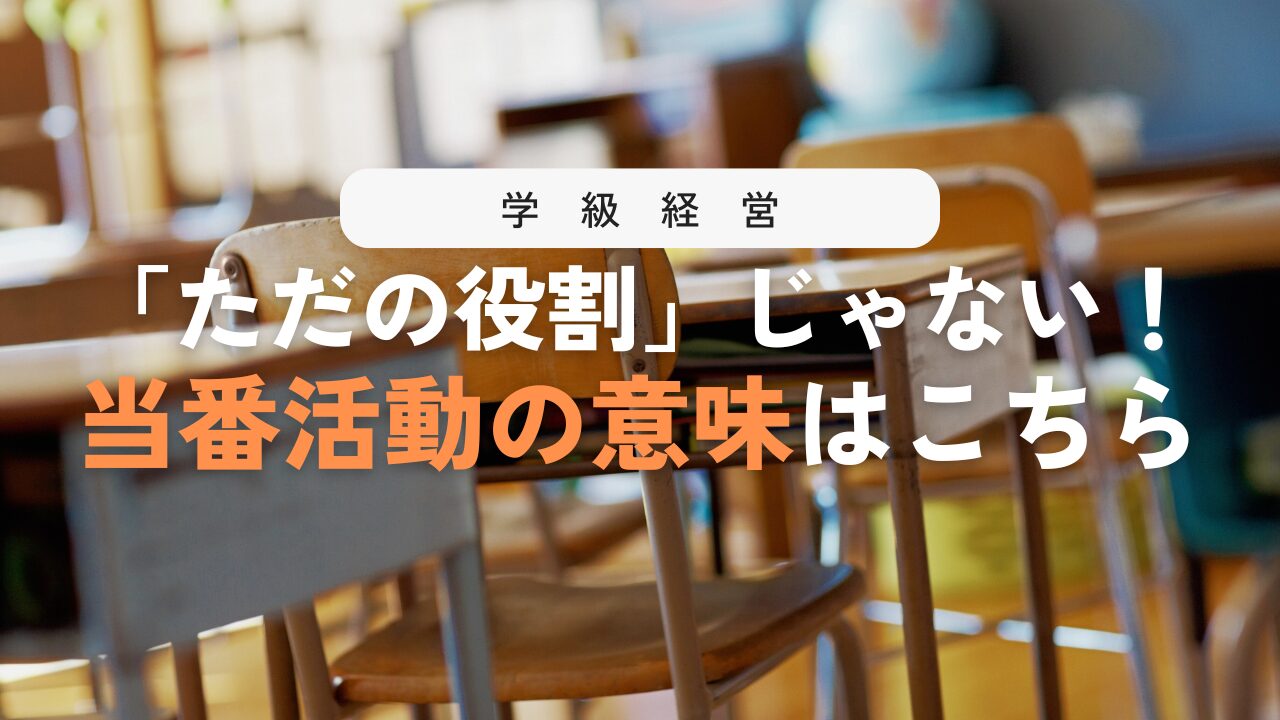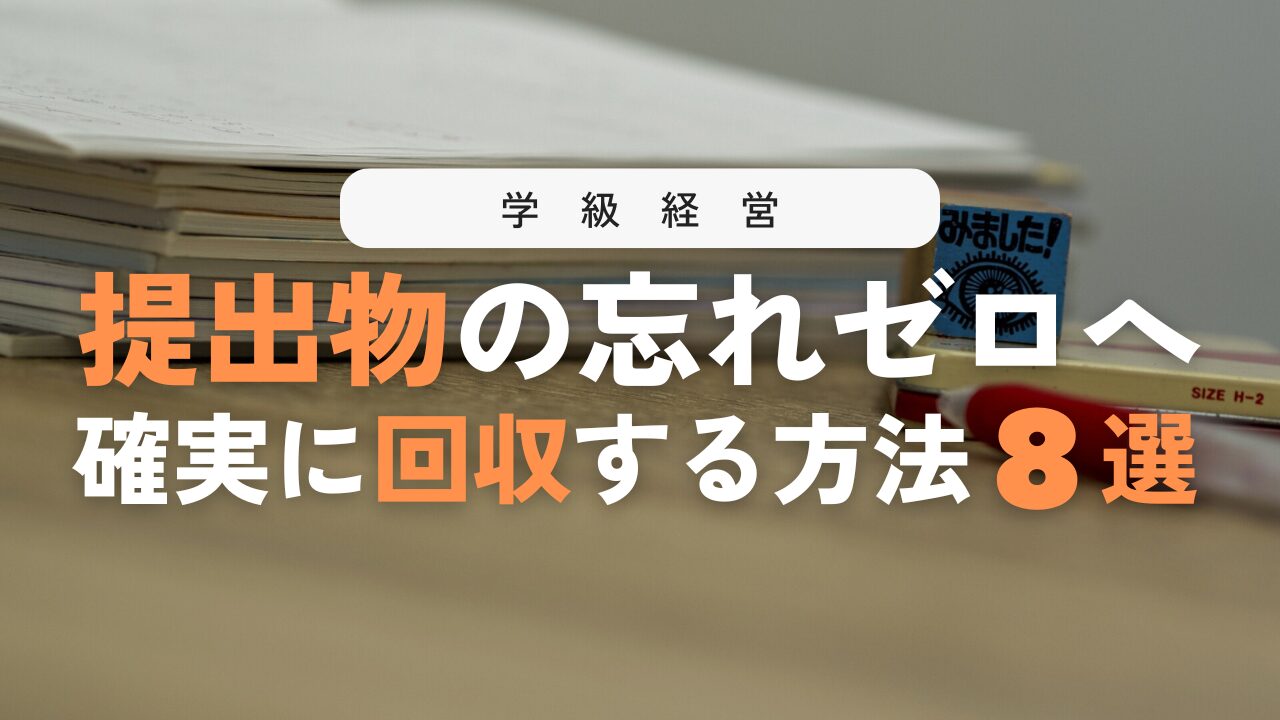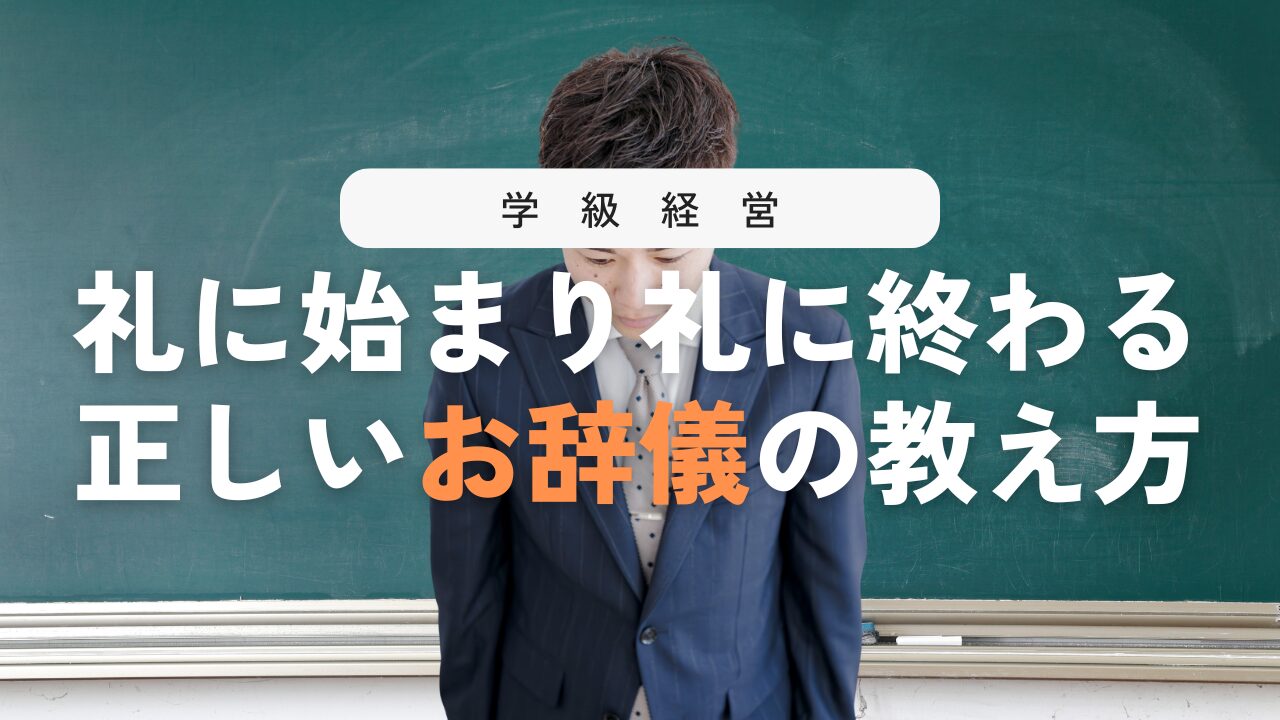【直伝】子どものおしゃべりをストップ!教室を静かにさせる指導法7選!
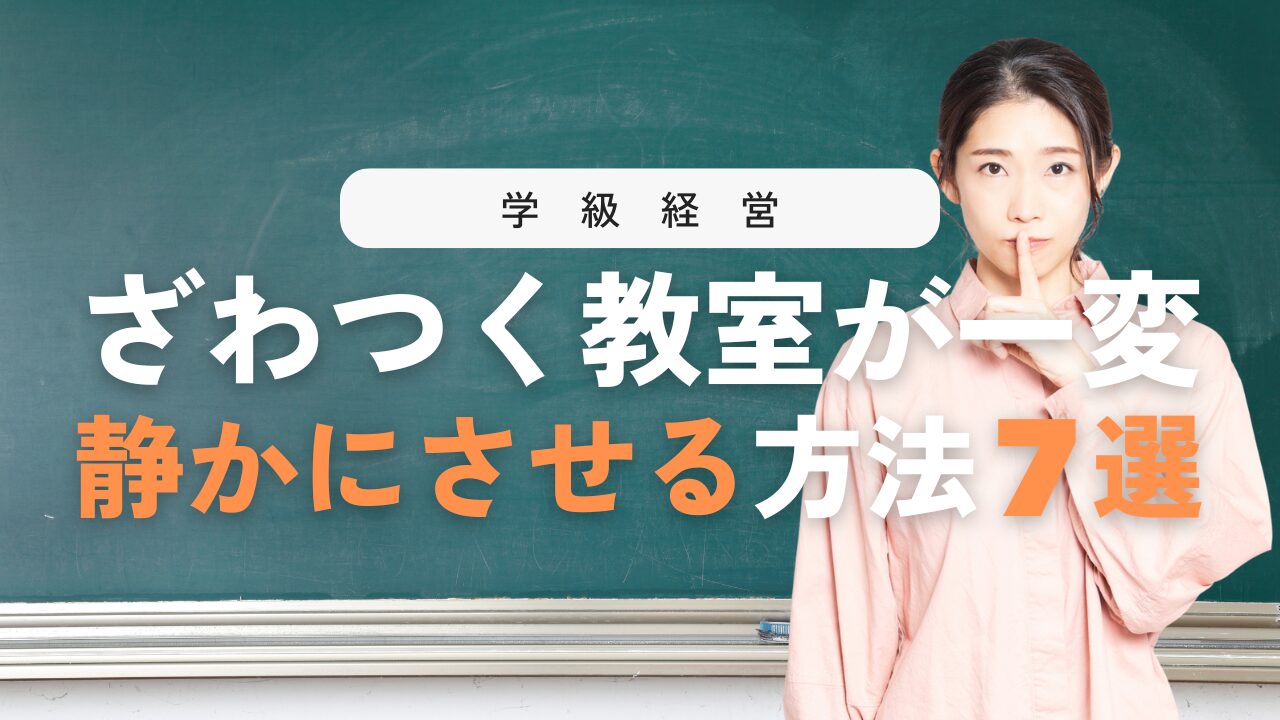
どうも、まっつーです。
教室で過ごす毎日の中で、「どうしてこんなにザワザワするの?」「何度言っても静かにならない…」と頭を抱えたことはありませんか?
「静かにしなさい!」と何度言っても、すぐにざわつきが戻ってしまったり、注意したことで全体の空気がピリッと重くなってしまったりすることもあります。
今回の記事は、「静かにしなさい」だけに頼らない、子どもたちの心に届いておしゃべりを止める7つの実践的な指導法をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 「静かにしなさい!」と言っても効果が感じられない
- 落ち着いた雰囲気で授業や活動を進めたい
- 子どもたちとの信頼関係を崩さずに指導したい
この記事を読めば、今日からすぐに使える声かけや指導のアイデアが見つかり、子どもたちが“自分の意思で静かにしよう”と思えるような学級づくりができるようになります!
この記事を書いた人↓

静かにする=無音になる…ではない

「静かにする」という言葉を聞くと、「物音を一切出さない」「息をひそめる」など、まるで無音の状態をつくり出すような印象を受けるかもしれません。
辞書などで調べると、「静か」の意味について次のように示されています。
- 耳ざわりな音や声を立てないようにすること
- 行動や動作を控めにして、目立たないようにすること
- 心や気持ちを落ち着けること
- (性格がおとなしく、口数が少ないさま)
ここで注目してほしいのは、必ずしも子どもの言動から音をすべて排除することを意味しているわけではないという点です。
子どもたちを静かにするように指導する前に、まず「静かにするとは、どういうことなのか?」を丁寧に説明することが必要があります。
耳ざわりな音や声を立てないようにすること
「耳ざわりな音や声を立てないようにすること」とは、たとえば授業中に学習とは無関係な話題でおしゃべりをしたり、鉛筆や教科書などで机をたたいてわざと音を出したりするような、周囲の集中を妨げる音声を控えるという意味です。
こうした音は、本人には気にならなくても、周囲の子どもにとっては学習の集中を妨げる「雑音」となってしまいます。
「先生の声が聞こえにくい」「考えていたことが分からなくなった」「隣の子のせいでイライラする」など、そんな思いを抱える子も少なくありません。
だからこそ、周囲の集中を守る行動という理解が必要なのです。
つまり、「みんなが気持ちよく学べるように、必要以上に音を立てないようにしよう」という思いやりの姿勢をもつ必要があるのです。
行動や動作を控えめにして、目立たないようにすること
「行動や動作を控えめにして、目立たないようにすること」とは、たとえば授業中に体を大きく揺らしたり、頻繁に落ち着かない様子で席を立ったりといった動きを控えることを意味します。
こうした行動は本人に悪気がなくても、どうしても周囲の目を引いてしまい、学級全体の集中力が途切れてしまう原因になります。
学習中においては、発言している子や黒板の前で発表している子、あるいは先生の話や板書などに自然と注目が集まるべきです。
そうした“注目されるべき相手”に意識が向くことで、子どもたちは内容をしっかり理解したり、互いの意見に耳を傾けたりすることができるのです。
つまり、「今、何が大切にされるべき時間なのか?」を理解し、その場にふさわしいふるまいを選択できる力を身につけることが大切なのです。
心や気持ちを落ち着けること
「心や気持ちを落ち着けること」とは、たとえば人の話をしっかり聞くために、自分の中のざわざわした気持ちや興奮を一度静めて、穏やかな状態をつくることを意味します。
子どもたちは日々さまざまな感情を抱えて学校で生活しています。
「休み時間の遊びが楽しかった」「ささいなことで友達とケンカした」「不安な気持ちを引きずっている」など、心の揺れをそのまま授業に持ち込むと、話を聞いていても頭に入らなかったり、落ち着いて考えることができなかったりするのです。
だからこそ、授業の始まりや活動の切り替え、あるいは行事や集会の前などに「心を整えて次の活動に向かう準備をする」ことに大きな意味があります。
この「心を落ち着ける」力は、生まれつき備わっているものではなく、繰り返しの経験と丁寧な声かけの中で育まれていくものです。

先生が「静かにしなさい!」と声をかけることがありますが、それは決して子どもたちに“無音”の状態を求めているわけではありません。
「動かないように」「音を出さないように」と無理に抑えつけようとしているのではなく、「今はどんな場面で、どのような行動をとることがふさわしいのか?」を子どもたち自身に考えさせ、気づかせていこうとしているのです。

今までは「音を出しちゃいけない!」って言われてる気がして、正直イヤだったけど、そうじゃないってわかって少し気が楽になったよ。
「静かにしなさい!」で通用するの!?

「静かにしなさい!」
これは学校現場でも家庭でも、よく耳にする注意の言葉です。
多くの大人はこの言葉で、子どもたちに「今は話すべきでない」「周りに迷惑をかけている」「気持ちを切り替えてほしい」といったメッセージを伝えようとしています。
つまり、「静かにしなさい」という一言には、「場面に合ったふるまいをしてほしい」という大人の願いが込められていますが、その願いが子どもたちに本当に届いているのかどうかは、別の問題です。
この言葉の持つ効果とその限界について、詳しく見ていきましょう。
一時的には効果があることも
まず、事実として、「静かにしなさい」と言われて子どもたちがピタッと静かになる場面はあります。
特に、注意された瞬間に驚いて声を止めるケースが多いです。これは、突然の大きな声や厳しい口調に対する「反射的な反応」です。
また、普段から先生との信頼関係がしっかりと築かれている場合や、学級のルールとして「先生の話すときは静かにする」が定着している場合には、「あ、今は静かにしなきゃ」と子どもたちが気づくきっかけになることもあります。
このように、短期的・即時的な効果は一定程度見られることもあります。
しかし、本当に“意味のある静けさ”ではなく、子ども自身で状況を判断して行動を整える力や、学びに向かう姿勢につながっていなければ、静かな状態を持続させることは極めて難しいでしょう。
長期的な効果には限界がある
「静かにしなさい」と何度注意しても、時間が経つとまたざわつき始める、という経験がある先生や保護者の方も多いのではないでしょうか?
これは、「静かにしなさい」という言葉が、なぜその場面で必要なのかを子どもが理解していないまま、強制的に“押さえつけられている”だけだからです。
言い換えれば、「叱られたから黙ったけれど、心では納得していない状態」が続いているのです。
また、注意の言葉が頻繁になると、子どもたちは「また怒られた」「うるさく言われた」といった感情だけが残り、本来伝えたかった“場にふさわしい行動の意味”が届かなくなることもあります。
さらに、強い口調の注意に慣れてしまった子どもは、「怒られない限り静かにしなくてもいい」という受け止め方をしてしまい、自分で行動を調整する力が育ちにくくなるという悪循環に陥ることもあるのです。

子どもたちを静かにさせるには、どうすればいいの?

本当に子どもたちに身につけてほしいのは、「注意されたから静かにする」ことではなく、「今は静かにした方がいい理由を理解して、自分の意思で行動を変える力」です。
子どもを静かにさせる指導法7選

子どもを静かにさせたいと思ったとき、つい「静かにしなさい!」「大きな声を出すのをやめなさい!」と強い口調で注意してしまいがちです。
もちろん、状況によってはそのような言葉が必要になることもありますが、毎回同じような声かけだけでは、子どもが慣れてしまったり、逆効果になったりすることもあります。
そこで大切なのが、注意の仕方に“バリエーション”を持っておくことです。
子どもの年齢や性格、場面の雰囲気、その子の心の状態などによって、声のかけ方や対応の仕方を柔軟に変えることで、より穏やかに、効果的に子どもの行動を整えることができるようになるでしょう。
ここでは、子どもを静かにさせる指導法を7つご紹介します。
- 静かにする理由を伝えたり、考えさせたりする。
- 視線を送る。
- 黙ることで気づかせる。
- 名前を呼ぶ。
- 静かにできている子を褒める。
- 小さな声で話す。
- 子どもの言い分を聞く。
①静かにする理由を伝えたり、考えさせたりする
「静かにしなさい!」と注意するだけでは、子どもたちは一時的に口を閉じるかもしれません。
しかし、それは“叱られたから静かにした”だけであって、「なぜ静かにしなければいけないのか?」という根本的な理由が伝わっていなければ、すぐにまた騒がしくなる可能性があります。
だからこそ大切なのは、次の2点です。これは“対話”としての関わりです。
- 「静かにする理由」を伝えること
- 「静かにする理由」を子ども自身に考えさせること
このように問いかけてみると、子どもたちは自分の行動を客観的に見直すきっかけになります。
また、「静かにすると友達の発表がよく聞こえて、良いところがもっと分かるよ」など、静かにすることによって得られる“メリット”を伝えるのも効果的です。
②視線を送る
先生の強い味方になるのが「視線」です。大きな声で注意しなくても、子どもに「あなたを見ていますよ」という視線を送るだけで、行動が変わることがあります。
決して睨みつけたり威圧的な目を向けたりすることではありません。
視線を感じた子と目が合ったときに、ほんの少しうなずく、ほほえむ、目元をやわらかくする…それだけでも、子どもは「見守られている」と感じます。
また、周囲の子も「先生がこっちを見ているよ」と教えてあげることもあります。
この方法を効果的にするためには、日頃から子どもをよく観察し、日常の中で小さな変化に気づいて声をかける姿勢が欠かせません。
③黙ることで気づかせる
授業中に騒がしさが増したとき、つい「静かにしなさい!」と声を張り上げたくなりますが、途中で話すのやめて、あえて黙ってみてください。
しばらく沈黙が続くと、周囲の子どもたちが気づき始めます。
「あれ?先生、なんで黙ってるの?」「何かおかしいぞ…」と、話をちゃんと聞いていた子がざわつき始めるのです。
そして、自分たちがうるさかったことに気づき始めた子たちが、「先生が話したいんだよ!」と声をかけてくれることもあります。
この「黙って伝える」方法は、子どもに“自ら気づく力”を育てるという意味で、非常に教育的な手法です。

普段から話すときは早口ではなく、「ちょっと間を取る」「言葉を溜める」などのリズムを取り入れておくと、子どもたちは耳を傾ける習慣が育ちます。
④名前を呼ぶ
実践的な方法のひとつに、「子どもの名前を呼ぶ」というシンプルな声かけがあります。
たとえば、授業中におしゃべりをしている子がいたときに、「○○さん」と穏やかな口調で名前を呼びかけるだけで、その子の意識をこちらに向けることができます。
このとき、叱るためではなく「あなたのことを見ているよ」「今の状況に気づいてね」とやさしく促すように名前を呼ぶことが大切です。
自分の名前を呼ばれた子は、「あ、見られていたんだ」と気づくと同時に、「今はおしゃべりする場面ではなかった」と自分の行動を振り返るきっかけを得ることができます。
また、このような呼びかけは、周囲の子どもたちにも「先生は一人ひとりをしっかり見ている」という安心感を与え、学級全体に落ち着きをもたらす効果もあります。
⑤静かにできている子を褒める
おしゃべりをしている子に注意を向けがちですが、注目すべきは“静かにできている子”です。
このような声かけをすると、まわりの子どもたちも「私も褒められたい!」という気持ちから、行動を見直し、よりよい方向に変えていくようになります。
また、注意をしても効果が出にくい子ほど、静かにできたほんの一瞬を見逃さずに褒めることが大切です。
「今、静かにできていたね!すごい!」というように、具体的な行動に焦点を当てて言葉をかけることで、「またやってみよう」という意欲を引き出すことができます。
⑥小さな声で話す
大きな声を出すのではなく、逆に小さな声で話しかけることで、子どもたちは耳を澄ますようになります。
まるで内緒話のように、「今からすごく大事な話をしますね……聞こえますか?」とささやくように語りかけると、子どもたちは自然と静かになっていきます。
この方法には、副次的な効果もあります。それは、先生との「特別なやり取り」をしているような感覚が生まれ、子どもたちのワクワク感や親密さが高まるという点です。
特に低学年では、「先生が私たちにだけに話しかけてくれている」という体験が、心の距離を一気に縮めてくれます。
⑦子どもの言い分を聞く
おしゃべりが多い子にも、何かしら理由があります。「友達とケンカしてイライラしていた」「前の授業がうまくいかずモヤモヤしていた」など、一人ひとりに違った背景がある場合があります。
そんな時、「どうしておしゃべりをしてしまったの?」と優しく声をかけて、理由を聞いてみてください。
決して、「なんでまた騒ぐの!」「いい加減にして!」といった決めつけではなく、「そうか、そういう気持ちがあったんだね」と一度、受け止めることが大切です。
そのうえで、「今はどうすればいいかな?」「あと何分静かにできそう?」と見通しを与えることで、子ども自身が行動を調整しようとする力を育てることができます。
まとめ
今回は、「静かにしなさい」だけに頼らない、子どもたちの心に届いておしゃべりを止める7つの実践的な指導法について紹介しました。
- 「静かにすること=無音になること」ではなく、思いやりや集中を守るための行動であるということ
- 強く叱るよりも、子ども自身が「なぜ静かにした方がいいのか?」を考える機会をつくることが大切であること
- 「視線」「沈黙」「褒める」「名前を呼ぶ」など、子どもに合わせた7つの具体的な関わり方を持っておくと、指導にゆとりが生まれること
今回の記事を読んで、ただ注意するのではなく、子どもたちに気づかせ、育てるための関わり方の引き出しを増やすことができたのではないでしょうか。
「静かにしなさい!」は、つい使いたくなる便利な言葉ですが、それだけでは子どもたちの行動は根本的には変わりません。
本当に大切なのは、「今はどう行動すればいいのか?」を子ども自身が理解し、自分の意志で選べるように導くことです。
子どもたちへの優しい声かけやあたたかな眼差しが、教室の空気を和らげ、学びやすい環境づくりにつながります。そんな関わりを意識していきましょう。