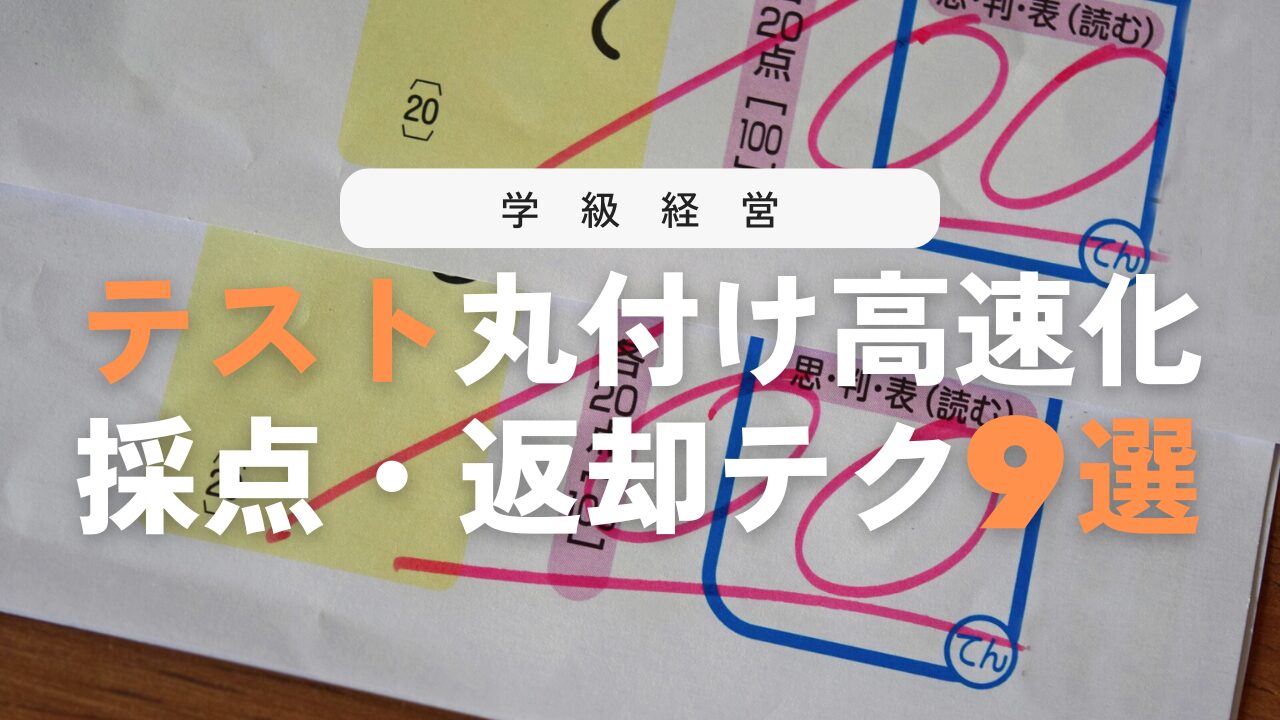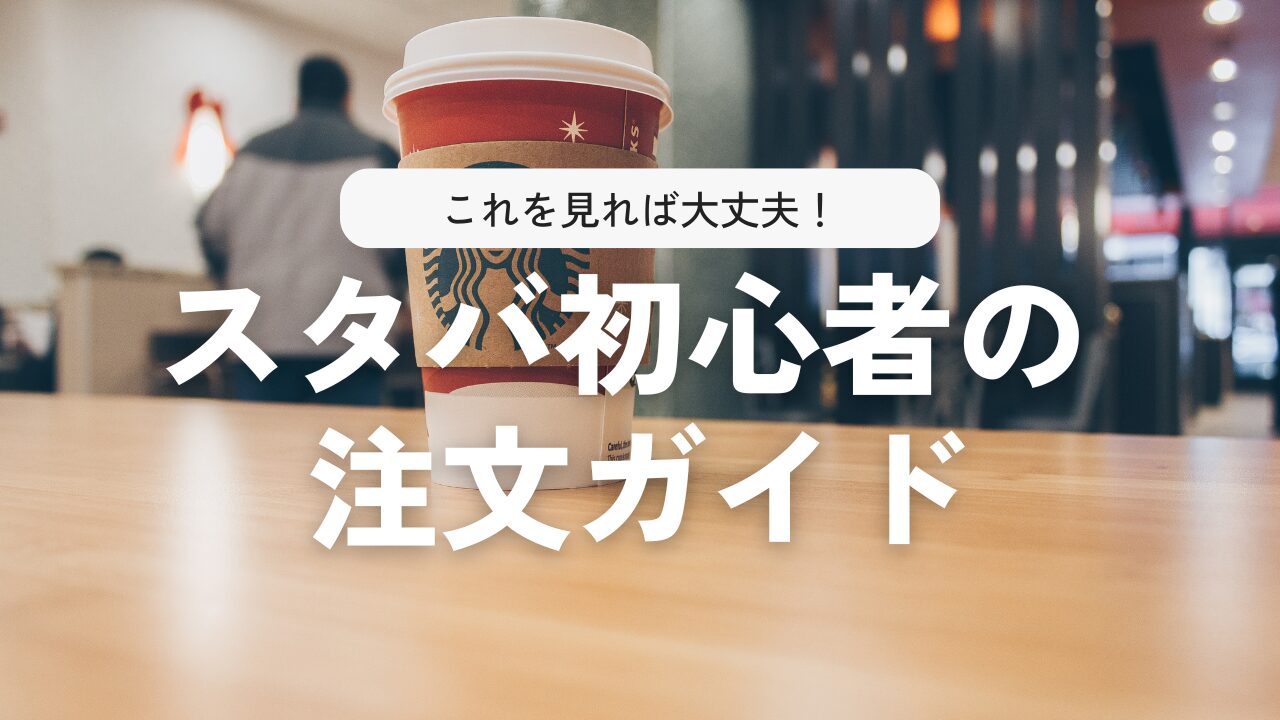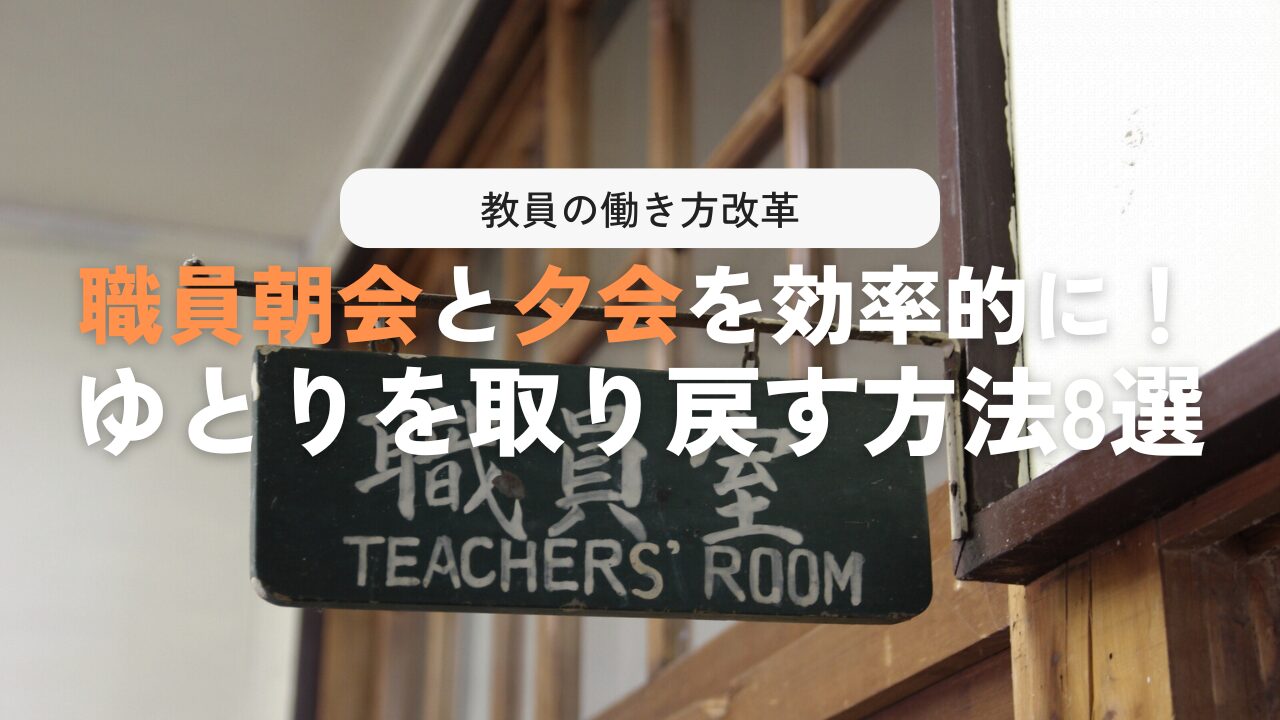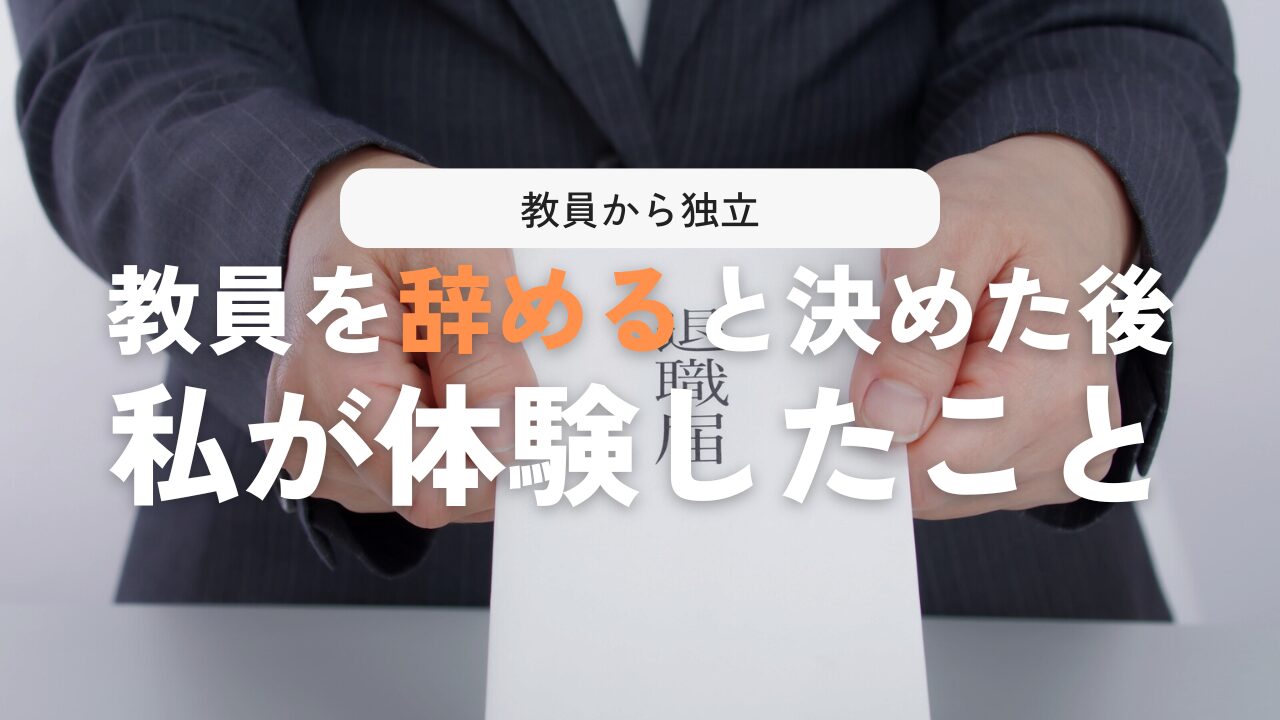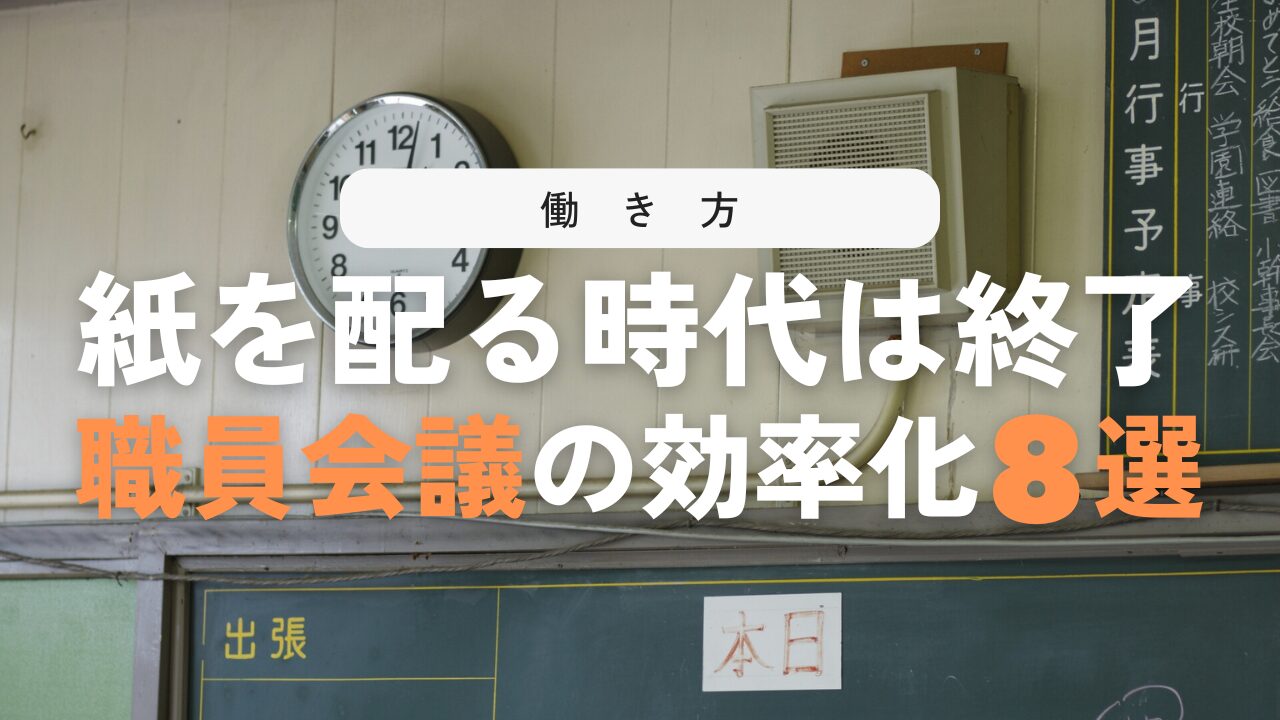【必見】個人事業主になる教員に必要なお金の基礎知識
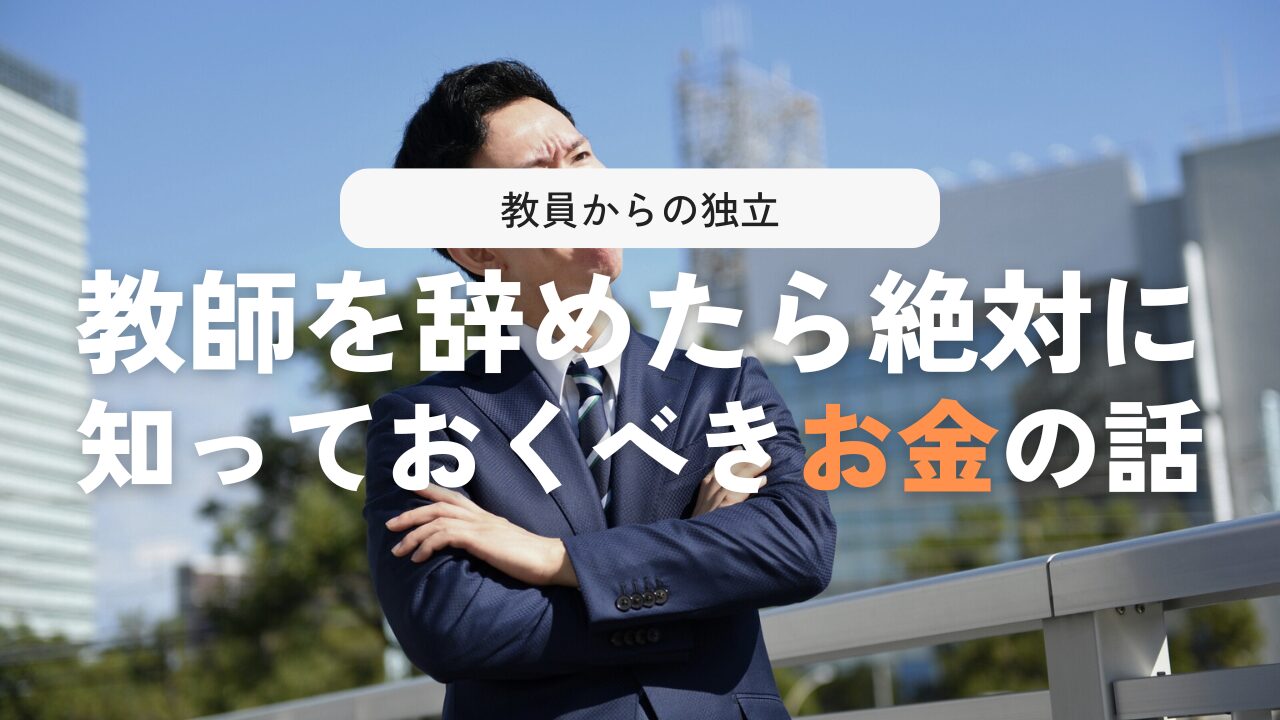
どうも、まっつーです。
教員を途中で退職、あるいは教員から個人事業主への転職を考えた際に、「個人事業主になりたいけど、お金の仕組みがよくわからない…」「学校の事務さんに経理を全部任せていたから、自分はできるのだろうか?」と、そんな疑問や不安を持っていませんか?
給与所得者であれば、毎月の給料やボーナスが自動的に支払われ、安定した収入を確保することができるため、お金の管理も比較的簡単です。
しかし、個人事業主になると、働き方の自由を手に入れると同時に、収入が不安定になるリスクも伴います。
そのためには、お金に関する正しい基礎知識を身につけることが重要です。
今回の記事は、個人事業主として絶対に知っておくべきお金の基礎知識(売上・経費・所得・控除・税金・確定申告など)をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 個人事業主になった(なりたい)から、お金について学びたい
- お金のことをなんとなく知っているけど、曖昧で正確には分からない
- 「売上」「経費」「所得」「所得控除」「課税所得」「確定申告」など、何を意味するのか知りたい
この記事を読めば、個人事業主になるための基本的な知識を身につけ、自分で売上や税金の計算などのお金の管理を安心して行うことができるようになります。
この記事を書いた人↓

- 売上とは何か?
- 経費とは何か?
- 所得とは何か?
- 所得控除とは何か?
- ①基礎控除(すべての人が使える控除)
- ②配偶者控除(配偶者がいると税金が安くなる)
- ③配偶者特別控除(配偶者の収入が少ないと税金が安くなる)
- ④扶養控除 (養っている家族がいると税金が安くなる)
- ⑤ひとり親控除(ひとり親の税金が安くなる)
- ⑥寡婦控除(夫と離婚や死別した女性の税金が安くなる)
- ⑦勤労学生控除(働く学生の税金が安くなる)
- ⑧社会保険料控除 (健康保険や年金を払うと税金が安くなる)
- ⑨小規模企業共済等掛金控除(将来の備えで税金が安くなる)
- ⑩生命保険料控除 (生命保険に加入していると税金が安くなる)
- ⑪地震保険控除(地震保険に入ると税金が安くなる)
- ⑫医療費控除(医療費が高かったら税金が安くなる)
- ⑬障害者控除(障害がある人や扶養している家族がいると税金が安くなる)
- ⑭寄付金控除(寄付をすると税金が安くなる)
- ⑮雑損控除(災害や盗難にあったとき税金が安くなる)
- 税額控除(計算した税金から直接引ける控除)
- 課税所得とは何か?
- 所得税とは何か?
- 復興特別所得税とは何か?
- 住民税とは何か?
- 個人事業税とは何か?
- 消費税とは何か?
- 社会保険(健康保険・年金・介護保険・雇用保険・労災保険)とは何か?
- 確定申告とは何か?
- まとめ
売上とは何か?
売上とは、お店や会社、または個人が商品を売ったりサービスを提供したりして、お客さんからもらったお金の合計のことです。1年間の売上の総額を「年商」といいます。
売上は、ただ「どれだけお客さんからお金を受け取ったか」 を表すものです。
塾の先生なら授業料、ブロガーなら広告収入やアフィリエイト収入が売上にあたります。
塾講師の売上とは?
あなたが塾の先生をしているとします。
生徒に授業をすると、お金(授業料)を受け取ります。
この生徒からもらう授業料の合計が売上です。
例えば、1回の授業料が5000円の場合…
- 1日に4人の生徒を教えたら、5000円 × 4人 = 2万円の売上
- 1か月(20日間)働いたら、2万円 × 20日 = 40万円の売上
授業をする回数や生徒数が増えれば、売上が増えていくという仕組みです。
ブロガーの売上とは?
ブロガーの売上は、広告収入やアフィリエイト収入から生まれます。
例えば、あなたがブログに広告を貼っているとすると…
- 広告が1回クリックされるごとに30円の収入になる
- 1日に1000回クリックされたら、30円 × 1000回 = 3万円の売上
- 1か月続けば、30000円 × 30日 = 90万円の売上
また、ブログで商品を紹介したとすると…
- 1個売れるごとに1000円の報酬をもらえる
- 1か月に50個売れたら、1000円 × 50個 = 50000円の売上
このように、ブログで発生する広告収入900000円や紹介報酬50000円の合計950000円が、ブロガーの売上になります。
※売上と似たような言葉で「収入」があります。売上はメインの事業によって得たお金や物品のことです。それに対して、収入はメイン事業によって得たお金や物品の他に、事業の仮定で副次的に得たお金や物品も含まれます。雑収入がない場合は、売上=収入と考えてよいでしょう。
経費とは何か?
経費とは、お店や会社、または個人が仕事をするために使うお金のことで、売上を得るために必要な支出のことです。
塾の先生なら授業をするために必要なお金、ブロガーならブログを運営するためにかかるお金が経費にあたります。
つまり、仕事をするうえで欠かせない支出はすべて経費になります。
塾講師の経費とは?
塾講師として生徒に授業をするためには、さまざまな準備が必要です。
- 教材費(生徒に配るプリント、問題集、参考書)
- 文房具代(ノート、ペン、ホワイトボード、マーカー)
- 通信費(オンライン授業をするためのWi-Fi代)
- 交通費(生徒の家へ行く家庭教師の場合、電車やバス代)
- 場所代(自分で塾を開いている場合、教室の家賃)
これらはすべて、授業をするために必要なお金だから経費です。
ブロガーの経費とは?
ブログを書くには、いろいろな道具やサービスが必要になります。
- サーバー代・ドメイン代(ブログを運営するために必要な費用)
- パソコン・スマホ代(記事を書くための作業用デバイス)
- カメラ・編集ソフト代(ブログ用の写真や画像を作るため)
- 取材費(ブログのネタ探しのために行ったカフェやイベントの費用)
- 広告費(ブログを多くの人に見てもらうための宣伝費)
これらはすべて、ブログを運営するために必要なお金だから経費です。
所得とは何か?
※ここでは事業所得について説明していますが、所得には の種類があります。
所得とは、お店や会社、または個人が得たお金(売上や収入)から、仕事に必要な経費などを引いた後に残るお金のことです。
所得(事業所得) = 売上 - 経費
塾の先生なら授業で得たお金から教材や交通費などを引いた額、ブロガーなら広告収入からブログ運営にかかった費用を引いた額が所得です。
塾講師の所得とは?
塾講師として仕事をした月の売上が400000円だっとします。
しかし、授業をするために教材費や教室の家賃費などの経費が100000円かかります。
所得 = 売上 - 経費の計算式に当てはめると…
売上400000円 - 経費100000円 = 所得300000円
つまり、1か月で300000円が自分の手元に残るお金(所得)になります。
ブロガーの所得とは?
ブロガーとして仕事をした広告収入(売上)が90万円だったとします。
しかし、パソコン代(分割)や取材費などの経費が35万円かかりました。
所得 = 売上 - 経費の計算式に当てはめると…
売上90万円 - 経費35万円 = 所得55万円
つまり、1か月で55万円が自分の手元に残るお金(所得)になります。
所得控除とは何か?
所得控除とは、税金を計算するときに、所得から差し引くことができる決まった金額のことです。例えば、医療費がたくさんかかったり、家族を養っていたりすると、その分だけ税金を減らしてもらえます。所得控除が大きいほど、支払う税金も少なくなります。
例えば、所得額が500万円で所得控除額が80万円の場合、所得税額は「(500万円 ー 80万円) × 20% ー 427500円」で41万2500円です。
もし、所得控除80万円の適用がなければ、税額は「500万円 × 20% ー 42万7500円」で57万2500円なので、所得控除により57万2500円 ー 41万2500円 = 16万円の税負担が軽減されます。
計算方法の詳細については、「所得税は何か?」の項目で再度説明します。
では、節税対策ができる所得控除にはどんなものがあるのか、所得控除15種類と税額控除を紹介します。
①基礎控除(すべての人が使える控除)
基礎控除とは、すべての個人事業主が共通して受けられる控除で、48万円(納税者本人の合計所得金額が2400万円以下の場合)が控除されます。
例えば、あなたの1年間の所得が300万円だったとします。
基礎控除の48万円を引くことで、課税所得は252万円になります。
税金はこの課税所得に対して計算されるので、基礎控除があることで税金が安くなるのです。
②配偶者控除(配偶者がいると税金が安くなる)
結婚していて、配偶者(夫や妻)が一定の条件を満たす場合は、配偶者控除を受けることができます。
この控除を受けるには、配偶者の年間所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である必要があります。
※一般的に所得税が発生する「103万円の壁」は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円 = 103万円が根拠になっています。
専業主婦(夫)や、パートで働いている場合に適用されることが多いです。
この条件を満たしていると、最大38万円の控除を受けることができます。
なお、年間所得が1000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はありません。
③配偶者特別控除(配偶者の収入が少ないと税金が安くなる)
前述の配偶者控除は、 配偶者(夫または妻)の年間所得が48万円以下の場合に受けられる控除ですが、もし配偶者の収入が48万円を超えていても条件を満たせば、配偶者特別控除を受けることができます。
この控除を受けるには、配偶者の年間所得が133万円以下(給与のみの場合は給与収入が201万円以下)である必要があります。
この条件を満たしていると、配偶者控除と同様に最大38万円の控除を受けることができます。
なお、年間所得が1000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はありません。
④扶養控除 (養っている家族がいると税金が安くなる)
扶養控除とは、養っている家族がいる場合に使える控除です。
例えば、親や子どもを扶養している場合、その家族の所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)なら、控除を受けることができます。
控除額は、扶養する人の年齢によって異なり、家族を養っているほど税金が安くなる仕組みになっています。
⑤ひとり親控除(ひとり親の税金が安くなる)
ひとり親控除は、 子どもを育てているひとり親の人が受けられる控除です。
控除額は35万円で、所得税が減るため税金の負担を軽くできます。
ただし、年間所得が500万円以下で婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明な人で、生計を共にする子どもがいる場合に適用されるなど、一定の条件に該当する必要があります。
⑥寡婦控除(夫と離婚や死別した女性の税金が安くなる)
寡婦控除とは、夫と離婚または死別し、再婚していない女性が一定の条件を満たした場合に、税金の負担を軽くするために受けられる控除です。
この制度を利用すると、所得税の計算時に27万円を所得から差し引くことができます。
⑦勤労学生控除(働く学生の税金が安くなる)
勤労学生控除とは、働きながら勉強を頑張る学生の税金を減らす制度で、27万円が所得から引かれます。
例えば、年収130万円の学生が控除を受けた場合…
- 給与所得控除(55万円)を引く → 130万円 ー 55万円 = 75万円
- 基礎控除(48万円)を引く → 75万円 ー 48万円 = 27万円
- 勤労学生控除(27万円)を引く → 27万円 ー 27万円 = 0円
このように、アルバイトの収入が130万円以下の学生は、勤労学生控除を活用すれば所得税がゼロになることがわかります。
勤労学生控除を受けるためには…
- 高校・大学・専門学校などに在籍している学生であること
- アルバイトなどの「働いて得た収入」があること
- 年間の「合計所得金額」が75万円以下(給与所得控除55万円を差し引くと、130万円 ー 55万円 = 75万円になるため)であること
- アルバイト以外の収入(投資の利益や家賃収入など)が10万円以下であること
が条件となります
⑧社会保険料控除 (健康保険や年金を払うと税金が安くなる)
個人事業主は、国民健康保険や国民年金に加入します。
これらの支払った保険料は、すべて社会保険料控除の対象になります。
つまり、1年間に支払った健康保険や年金の全額を、そのまま所得から差し引くことができるのです。
⑨小規模企業共済等掛金控除(将来の備えで税金が安くなる)
小規模企業共済等掛金控除とは、事業をしている個人事業主や会社の役員が、将来のために積み立てる共済や年金の掛金を支払うとその金額がまるごと所得控除され、税金が安くなる制度です。
会社員は、退職時に退職金を受け取ることができる場合が多いですが、個人事業主やフリーランスには、一般的な退職金制度がないため、自分で備える必要があります。
小規模企業共済(個人事業主や法人役員が将来のために積み立てる共済)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金を支払うと、その支払った金額がすべて所得から差し引かれるので、税金が安くなります。
⑩生命保険料控除 (生命保険に加入していると税金が安くなる)
あなたが生命保険や介護保険、個人年金保険に加入しているなら、生命保険料控除を受けることができます。
この控除では、支払った保険料に応じて最大12万円が控除されます。
- 生命保険料控除(最大4万円)
- 介護医療保険料控除(最大4万円)
- 個人年金保険料控除(最大4万円)
「保険に入っているだけで、税金が安くなる」という嬉しい仕組みなので、加入している保険の種類を確認し、しっかり控除を活用しましょう。
⑪地震保険控除(地震保険に入ると税金が安くなる)
大きな地震が発生すると、家が倒壊したり、火災が発生したりして、大きな損害を受けることがあります。
こうしたリスクに備えるために「地震保険」に加入している人は多いでしょう。
地震保険料控除とは、1年間に支払った地震保険料を所得控除として計上し、税の負担を軽減できる制度です。
控除額は最大5万円になります。
⑫医療費控除(医療費が高かったら税金が安くなる)
もし1年間に10万円以上の医療費を支払っていた場合、医療費控除を使うことができます。
例えば、病院にかかった費用や、処方された薬代、歯の治療費、妊娠・出産費用などが対象です。
さらに、自分だけでなく家族の医療費も合算できるので、年間の医療費が多かった人は、しっかり申告しましょう。
控除できる金額は(支払った1年間医療費 - 保険金などで補填される額)- 10万円で、上限は200万円になります。
ただし、所得金額が200万円未満の人の場合は、10万円ではなく「所得金額×5%の額」になります。
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
⑬障害者控除(障害がある人や扶養している家族がいると税金が安くなる)
障害を持つ本人やその家族を養っている人は、障害者控除を受けることができます。
控除額は 27万円・40万円・75万円の3段階があり、重度の障害があるほど控除額が大きくなる仕組みになっています。
⑭寄付金控除(寄付をすると税金が安くなる)
寄付金控除とは、特定の団体や自治体に寄付をすると、その分税金が安くなる仕組みです。
特定の団体とは、国、都道府県・市区町村(ふるさと納税も含む)、日本赤十字社、災害義援金(震災関連の寄付など)、政党・政治資金団体、公益財団法人・公益社団法人・学校法人、認定NPO法人のことです。
これらの団体への寄付は、確定申告をすることで税金の負担を減らすことが可能になります。
寄付金控除の種類
寄付金控除には、大きく分けて2つの種類があり、どちらを選択するかで税金の軽減額が変わります。
- 所得控除(寄付金控除)…寄付した金額の一部を「所得」から差し引くことで、結果的に支払う税金が少なくなる制度です。特に国や自治体、日本赤十字社などへの寄付が対象になります。
- 税額控除(寄付金特別控除)…寄付した金額の一定割合を、支払うべき所得税から直接差し引く制度です。認定NPO法人や政党、公益社団法人への寄付が対象となります。
ふるさと納税も寄付金控除の対象
ふるさと納税は、全国の自治体に寄付をすると、そのお礼として特産品などがもらえる制度です。
そして、寄付した金額のうち2000円を超える部分が寄付金控除の対象になります。
ただし、ふるさと納税には控除の上限額があるため、年収や家族構成によって控除額が異なります。
参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
⑮雑損控除(災害や盗難にあったとき税金が安くなる)
雑損控除とは、災害や盗難などで資産に損害を受けたときに経済的な負担を減らすための制度です。
雑損控除の計算方法は2つあり、どちらか多いほうの金額が控除されます。
- 計算式1:差引損失額(損害額 + 災害関連の支出額 - 受け取った保険金) - 総所得金額等 × 10%
- 計算式2:災害関連の支出額 - 5万円
例えば、台風で自宅が損壊し、150万円の修理費がかかった場合…
- 損害額:150万円
- 火災保険で補償された金額:50万円
- 総所得金額:500万円
- 災害関連の支出(原状回復費用):40万円
上記のお金が発生したと仮定すると…
- 計算式1:(150万円 + 40万円 - 50万円) -(500万円 × 10%)= 90万円
- 計算式2:40万円 - 5万円 = 35万円
多い金額のほうが適用されるので、控除額は90万円となります。
参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
税額控除(計算した税金から直接引ける控除)
税額控除とは、計算された所得税の金額から直接差し引くことができる制度です。
例えば、所得額が500万円、所得控除額が80万円で税額控除5万円の場合、所得税額は「(500万円 ー 80万円) × 20% ー 42万7500円 ー 5万円」で36万2500円です。
もし、税額控除5万円の適用がなければ、税額は「(500万円 ー 80万円) × 20% ー 42万7500円」で41万2500円なので、税額控除により41万2500円 ー 36万2500円 = 5万円の税負担が軽減されます。
税額控除の種類には、株式の配当金等を受け取った場合に受けられる配当控除、海外で得た所得に対して受けられる外国税額控除、住宅ローンを利用して家を購入した人がローン残高に応じた額を10年間受けられる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などがあります。
課税所得とは何か?
「課税所得」とは、税金を計算するときのもとになるお金のことです。収入から経費を引いた所得から、さらに所得控除を引いた後の金額が課税所得になります。この金額に応じて、どれくらいの税金を払うかが決まります。
課税所得 = 所得(事業所得) - 所得控除
前述の通り、「所得」とは、売上から経費を引いた後に残るお金のことであり、「所得控除」は、税金を減らすために引くことができる金額のことです。
例えば、あなたの1年間の売上が600万円だったとします。
仕事にかかった経費が200万円なら、所得は600万円 - 200万円 = 400万円になります。
しかし、400万円すべてに税金がかかるわけではありません。
ここから、前述の基礎控除や扶養控除などの所得控除を引きます。
もし、あなたが受けられる所得控除が100万円だった場合…
所得400万円 - 所得控除100万円 = 300万円
この300万円が税金を計算するときの課税所得になります。
課税所得の金額に応じて、所得税や住民税が決まるのです。
所得税とは何か?
所得税とは、働いて得たお金にかかる税金のことです。所得が多い人ほど、たくさん税金を払う仕組みになっています。教員の場合は、給料からあらかじめ引かれますが、個人事業主は1年分をまとめて確定申告で申告し、自分で国に納める必要があります。
所得税額 =(課税所得金額 × 税率)ー 控除額
売上や給料などの収入があっても、そのまま税金がかかるわけではなく、そこから必要な経費や所得控除を引いた後の金額(課税所得)に対して課税されます。
そして、日本の所得税は「累進課税制度」という仕組みをとっているため、稼げば稼ぐほど税率も上がるという特徴があります。
下記は、所得税額を簡単に求めることができる速算表です。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
ここでのポイントは、全額に一律の税率がかかるわけではないということです。
例1:あなたの課税所得が150万円だった場合、上記の速算表を見ながら「所得税額 =(課税所得金額 × 税率)ー 控除額」の計算式に当てはめると、150万円 × 5% ー 0円 = 7万500円が払うべき所得税の金額になります。
例2:あなたの課税所得が300万円だった場合、上記の速算表を見ながら所得税額 =(課税所得金額 × 税率)ー 控除額の計算式に当てはめると、300万円 × 10% ー 9万7500円 = 20万2500円が払うべき所得税の金額になります。
例3:あなたの課税所得が800万円だった場合、上記の速算表を見ながら所得税額 =(課税所得金額 × 税率)ー 控除額の計算式に当てはめると、800万円 × 23% ー 63万6000円 = 120万4000円が払うべき所得税の金額になります。
「超過累進税率」とは、課税所得のすべてに一律の税率がかかるのではなく、ある金額を超えた部分に対してのみ、高い税率が適用されるという計算方法です。そのため、「税率が上がると急に税金が高くなる」ということはありません。
所得税の納付期限は、毎年3月15日までです。
前年(1月1日~12月31日)の収入を計算し、翌年2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、その際に確定した税額を支払います。
ただし、期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日まで延長されます。
※所得税は、経費として計上することができません。
復興特別所得税とは何か?
「復興特別所得税」とは、東日本大震災の復興財源を確保するために設けられた税金です。2011年に発生した大震災により、多くの地域が甚大な被害を受けました。その復興を支援するために、2013年から2037年までの25年間、所得税に上乗せする形で徴収されることが決められています。具体的には、所得税額に対して2.1%が加算される形で計算されます。
復興特別所得税 = 基準となる所得税 × 2.1%
合計で支払う税額 = 所得税 × 102.1%
例えば、あなたの所得税が50万円だった場合、復興特別所得税は…
50万円 × 2.1% = 10500円
つまり、所得税50万円に対して、復興特別所得税10500円が加算され、合計51万500円を納めることになります。
この税金は、特別な手続きは必要なく、所得税を納めるときに復興特別所得税も加算して納めることになります。
復興特別所得税の納付期限は、所得税と同じ3月15日です。
確定申告をする人は、毎年2月16日から3月15日までに申告し、3月15日までに納税する必要があります。
ただし、期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日まで延長されます。
※復興特別所得税は所得税の一部として扱われるため、経費として計上することができません。
住民税とは何か?
「住民税」とは、住んでいる地域の行政サービスを支えるための税金です。例えば、学校の運営や子どもたちの教育、道路の整備や公共施設の維持、消防・救急・ごみ処理などの生活サービスなどが、この税金によってまかなわれています。住民税は 「市町村民税(または特別区民税)」と「都道府県民税(または道府県民税)」 の2つで構成され、市区町村と都道府県の両方に納める税金ということです。
住民税 = (課税所得 × 10%)+ 5000円
住民税には、「所得割」と「均等割」の2種類があります。
①所得割・・・前年の所得(売上-経費)をもとに計算される税金のことで、税率は一律10%(市町村民税6%+都道府県民税4%)です。
②均等割・・・所得に関係なく、一律でかかる税金のことで、令和6年度(2024年)からの金額は、年間5000円(市町村3000円+都道府県1000円+森林環境税1000円)となっています。
例えば、あなたの課税所得が300万円の場合…
- 所得割 → 300万円 × 10% = 30万円
- 均等割 → 5000円
住民税の合計 = 30万円 + 5000円 = 30万5000円となり、あなたが払うべき住民税の金額になります。
個人事業主の住民税の納付方法には、「普通徴収」という方法があります。
これは、自治体から送られてくる納税通知書に従って、自分で納める方法です。
住民税の支払いは、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めることができますし、一括で支払うことも可能です。
毎年5月~6月頃になると、市区町村から「住民税の納税通知書」が送られてきます。
そこに記載された金額を、銀行やコンビニ、インターネットで支払うという流れです。
ちなみに、給与所得者である教員などの場合、市区町村が住民税の金額を勤務先に知らせ、毎月の給料から住民税を天引きし、自治体へ納めてくれます。
このように、勤務先を通じて住民税を支払う仕組みのことを「特別徴収」といいます。
特別徴収なら、自分で納付の手続きをする必要がないので、払い忘れる心配がなく、手間もかかりません。
※住民税は、経費として計上することができません。
個人事業税とは何か?
「個人事業税」は、特定の業種で個人事業を営む人が都道府県に納める税金です。すべての個人事業主にかかるわけではなく、対象となる業種(法定業種) に当てはまる人だけが支払うことになります。また、個人事業税には 「事業主控除」 という特別な控除があり、年間の所得が290万円以下であれば税金はかかりません。
個人事業税 =(所得 - 事業主控除290万円)× 税率(3%~5%)
すべての個人事業主が個人事業税を払うわけではなく、次の条件に当てはまる場合に支払う必要があります。
① 法定業種に該当する事業を行っている
個人事業税がかかるのは、法律で決められた「法定業種」に当てはまる事業をしている人です。
法定業種は全部で70種類あり、第1種事業(37業種)、第2種事業(3業種)、第3種事業(30業種)の3つのグループに分けられています。
また、税率は事業の種類によって3~5%と異なります。
そのため、個人事業主は自分の事業がどのグループに入るのかをしっかり確認しておくことが大切です。
例えば、飲食業、美容業、製造業、運送業、不動産業、専門職などがあります。
ライターや漫画家、作曲家、スポーツ選手は原則として個人事業税の対象外ですが、事業の形態によっては課税される場合があります。
② 所得が290万円を超えている
個人事業税には 事業主控除という制度があり、年間の所得(売上-経費)が290万円以下であれば税金はゼロになります。
反対に、所得が290万円を超えた場合は個人事業税が発生します。
例えば、あなたが飲食店を経営していて、所得が400万円だった場合…
- 所得400万円 - 事業主控除290万円 = 課税所得110万円
- 課税所得110万円 × 税率(飲食店)5% = 個人事業税5万5000円
あなたが支払う個人事業税は5万5000円となります。
個人事業税は確定申告をした後、8月頃に都道府県から送られてくる納税通知書に従って支払います。
具体的な納付期限は、住んでいる都道府県が決定するため、納税通知書を確認しましょう。
※個人事業税は、事業を継続するために必要な支出であるため、経費として計上することが可能です。
消費税とは何か?
「消費税」とは、商品を買ったり、サービスを受けたりしたときにかかる税金のことです。個人事業主は、お客さんから消費税を預かり、それを国に納めることになります。ただし、全ての個人事業主が消費税を納めるわけではなく、一定の条件を満たした人だけが対象になります。
次のどれかに当てはまる個人事業主は、消費税を納める義務があります。
- 2年前(前々年)の売上が1000万円を超えている人
- 特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)における売上が1000万円を超える人
- インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録している人
このように、消費税を納める義務がある人を「課税事業者」と呼びます。
反対に、消費税を納める義務がない人を「免税事業者と呼びます。
消費税は、毎年3月31日までに確定申告と一緒に納める」のが基本です。
ただし、期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日まで延長されます。
また、前年の消費税が48万円以上の人は、中間納税が必要になります。
消費税の計算方法
消費税を計算する方法には、一般課税と簡易課税の2つの方法があります。
一般課税では、売上の消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて納める方法です。
納める消費税額(一般課税方式) = 売上の消費税 - 仕入れの消費税
簡易課税は、売上にかかる消費税の一部だけ納める方法です。業種によって「みなし仕入率」というものが決められており、経費の計算を簡単にできます。例えば、サービス業(税率50%)なら、売上の消費税の50%分を仕入れとして計算し、その残りを納めればOKになります。
納める消費税額(簡易課税方式) = 売上にかかる消費税 ×(1-みなし仕入率)
消費税の税率
現在の消費税の税率は、10%と8%の2種類あります。
- 標準税率(10%)…ほとんどのモノやサービスに適用
- 軽減税率(8%)…食品(酒類・外食を除く)や定期購読の新聞
飲食店で食事をすれば10%の消費税がかかりますが、お弁当を買って持ち帰る場合は8%になります。
例えば、1年間の売上が1000万円で仕入れた経費に500万円かっかった場合、一般課税の計算方法だと…
- 1年間の売上が1000万円(消費税10%で計算 → 消費税100万円)
- 仕入れや経費に500万円かかった(消費税10%で計算 → 消費税50万円)
- 納める消費税 = 100万円 - 50万円 = 50万円
つまり、事業でかかった経費の消費税を差し引いた金額50万円を納めることになります。
これを仕入税額控除といいます。
※課税事業者は、消費税を仕入税額控除として扱うため経費にはできません。
※免税事業者は、消費税を含めた金額を経費にする税込経理方式と、消費税部分を分離して記帳する税抜経理方式のどちらかを選択できます。一般的には、税込経理方式を選ぶことで、消費税を含めた金額をそのまま経費として処理することができます。
社会保険(健康保険・年金・介護保険・雇用保険・労災保険)とは何か?
個人事業主は「健康保険(国民健康保険)」と「年金(国民年金)」に加入しなければなりません。また、40歳以上になると「介護保険」への加入も義務になります。さらに、個人事業主は雇用保険や労災保険に原則加入できないため、失業した場合や仕事中の事故で保障を受けられないというデメリットがあります。
個人事業主が加入できる健康保険
個人事業主が加入できる健康保険には大きく分けて、①〜④の4種類があります。
※健康保険料は私的な支出であり、事業とは関係ないので経費にはできません。ただし、社会保険料控除(所得控除)として認められます。
①国民健康保険
国民健康保険(国保)は、すべての個人事業主が必ず加入する公的医療保険です。
都道府県や市区町村が運営し、前年の所得に応じて保険料が決まります。
所得が高いと保険料も高くなり、保険料は全額自己負担です。
家族を扶養する仕組みがないため、家族全員分の保険料を払う必要があります。
②国民健康保険組合(国保組合)
国民健康保険組合(国保組合)とは、特定の業種(建設業・飲食業・美容業・芸術関係など)に従事する個人事業主向けの健康保険です。
例えば、フリーランスのデザイナーやライターは 「文芸美術国民健康保険組合(文美国保)」 に加入できる場合があります。
所得に関係なく、基本的に保険料が一律であるため、高収入の人ほどお得です。
業種ごとに設けられた組合に加入する必要があり。加入条件や保険料は組合ごとに異なります。
③退職前の健康保険を「任意継続」
健康保険の任意継続とは、会社を辞めて個人事業主になった場合、退職前の健康保険を最長2年間継続できる制度です。
ただし、保険料は全額自己負担(会社負担分も支払う)になるため、負担が増えることに注意しましょう。
保険料は退職時の標準報酬月額に応じて決まります。
④家族の健康保険の「被扶養者」になる
配偶者や親が会社員で健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば被扶養者として保険料なしで加入できます。
これは個人事業主にとって最も負担の少ない選択肢です。
ただし、年間所得130万円未満(従業員101人以上の企業なら106万円未満)であることや、配偶者および親の年収の2分の1未満であることなどが条件です。
個人事業主が加入できる年金制度
日本の公的年金制度は 「二階建て」 の仕組みになっています。
※年金は私的な支出であり、事業とは関係ないので経費にはできません。ただし、社会保険料控除(所得控除)として認められます。
1階部分:国民年金(基礎年金)
国民年金はすべての日本国民(20歳以上60歳未満)が加入する義務がある年金制度です。
すなわち、個人事業主は国民年金(基礎年金)に加入することになります。
保険料は一律(令和6年度は月額16980円)です。
個人事業主は2階建ての厚生年金が無いことにより、老後に受け取れる年金が少なくなるため、自分で対策を取る必要があります。
2階部分:厚生年金(会社員や公務員)
厚生年金は 会社員や教員(公務員)が加入する年金制度です。
会社が半分負担してくれるため、個人の負担は軽くなります。
厚生年金に加入すると、国民年金の上に「上乗せ」して年金をもらえる仕組みになっており、老後に受け取れる年金が多くなります。
個人事業主の年金額を増やす3つ方法
- 付加年金…国民年金に月400円プラスして支払うことで、将来の年金を増やせる制度
- 国民年金基金…厚生年金のように国民年金に上乗せして支払うことができる制度で、支払う金額によって将来の受け取る年金が確定する「確定給付型」 なのが特徴
- iDeCo(個人型確定拠出年金)…個人事業主がお金を積み立てて、それを運用しながら将来のために増やしていく年金制度
介護保険
介護保険制度とは、自分が年をとって介護が必要になったときに備えて、みんなでお金を出し合う仕組みのことです。
この制度のおかげで、介護が必要になったときに自己負担を1~3割に抑えてサービスを受けることができます。
40歳になったら自動的に加入することになっているので、個人事業主であっても必ず介護保険料を払うことになります。
介護保険料の支払い方法は、「40歳以上65歳未満」と「65歳以上」 で異なります。
40歳以上65歳未満の個人事業主
この年代の介護保険料は、健康保険料と一緒に払う仕組みになっています。
個人事業主の場合は、国民健康保険料に上乗せされる形で請求されるため、毎年市区町村から送られてくる保険料の通知を確認しましょう。
- 会社員(給与所得者)…介護保険料は給料や賞与から天引きされ、会社と折半するため負担が軽い
- 個人事業主…介護保険料は全額自己負担となり、40歳以上の家族全員分を世帯主が支払う
65歳以上の個人事業主
65歳以上になると、介護保険料は年金から天引きされる仕組みになります。
年金を受け取っていない人は、納付書での支払いや口座振替で納めることになります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業したときや働けなくなったときに生活を支えるための保険です。会社員は毎月給料から雇用保険料を引かれ、会社も一部負担することで、失業したときに「失業手当」をもらうことができます。ただし、教員(公務員)の場合は、雇用保険法の適用の対象外となっているため、退職しても失業手当をもらうことができません。
個人事業主は雇用保険に入ることができません。
なぜなら、雇用保険は「雇われている人=労働者」のための制度だからです。
個人事業主は「自分で仕事をしている」ため、そもそも「失業」という概念がないことになります。
たとえ仕事がなくなって収入がゼロになったとしても、会社員のような 「解雇」や「倒産」 とは違うので、失業手当を受け取ることはできません。
ただし、個人事業主が従業員を雇う場合は、その従業員のために雇用保険へ加入する義務があるため、その点は注意が必要です。
労災保険
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中にケガをしたとき、病気になったとき、死亡したときに補償を受けるための保険です。例えば、教員や会社員が仕事中に事故で骨折した場合、労災保険から治療費が出たり、仕事ができない間の給料が補償されたりします。
通常、個人事業主は労災保険に入ることはできません。
なぜなら、雇用保険と同様に、労災保険は「雇われている人=労働者」のための制度だからです。
しかし、例外的に「一人親方や特定の業種の個人事業主は、労災保険の特別加入制度に入ることができる」いうルールがあります。
確定申告とは何か?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、それにかかる税金を報告する手続きのことです。教員やサラリーマンの場合は、勤務先が給料から税金を引いて納めてくれますが、個人事業主は自分で税金を計算し、納める必要があるのです。
確定申告をすることで、すでに支払った税金が多すぎた場合は還付金(払いすぎた税金の返金)を受け取ることができ、逆に税金が足りない場合は不足分を納めなければなりません。
日本では、申告納税制度という仕組みを採用しており、納税者自身が税金の計算から申告・納税までを行うことになっています。
そのため、会社員や教員など年末調整を受けている人や、一定の収入以下で確定申告の義務がない人を除き、収入を得ている人は所得に応じて確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
もし申告を忘れたり、期限を過ぎたりすると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが科せられる可能性があります。
確定申告の期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
ただし、期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日まで延長されます。
確定申告が必要な個人事業主
個人事業主は、1年間の所得が48万円を超えた場合、確定申告をしなければなりません。
ただし、所得が48万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
また、医療費控除などの控除を受けたい場合は、所得が48万円以下でも確定申告をした方が有利になるケースがあります。
ちなみに、給与所得がある教員などが許可申請が通った上で副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし、住民税の申告は、副業の所得が20万円以下でも必要な場合があります。
確定申告のやり方(基本の流れ)
確定申告の流れは、大きく分けて①〜⑤の5つのステップです。
①どの申告方法を選ぶか決める
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告を選ぶと、最大65万円の控除を受けられるほか、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたりするなど、さまざまなメリットがあります。しかし、帳簿(複式簿記による記帳)をつける必要があるため、白色申告よりも手続きが複雑になります。
白色申告とは、手続きが簡単な確定申告の方法です。青色申告と違って、特別な事前申請が不要で、帳簿も簡単な形式でOKなため、手間をかけずに確定申告を済ませたい人向けの制度です。ただし、節税のメリットが少ないため、事業を継続して行う場合は、青色申告を選んだほうが有利になるケースが多いです。
※青色申告で確定申告を行う場合は、「開業届」と「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
②確定申告書を作成する
確定申告書を作成する方法は、大きく分けて4つあります。
- 確定申告書作成コーナー(国税庁のWebサイト)を使う…国税庁が提供している「確定申告書作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力するだけで簡単に確定申告書を作成できます。この方法は、無料で利用でき、申告書を自動で計算してくれるため、多くの人にとって使いやすい選択肢です。
- 確定申告ソフトを使う…確定申告ソフトを使えば、入力するだけで確定申告書が自動で作成されるため、会計に詳しくない人でも簡単に確定申告ができます。特に「マネーフォワード クラウド」や「freee会計」といったソフトは、クレジットカードや銀行口座と連携できるため、経費の管理がとても楽になります。
- 手書きで作成する…税務署やコンビニで申告書を入手し、自分で記入して提出する流れです。ただし、計算ミスや記入ミスが起こりやすいため、初心者にはあまりおすすめできません。
- 税理士に依頼する…専門家である税理士に任せることで、正確に申告できるだけでなく、節税のアドバイスをもらうこともできます。ただし、税理士への依頼には費用がかかるため、費用対効果を考えて選ぶ必要があります。
③税務署に提出する
確定申告書が完成したら、以下の3つの方法で税務署に提出します。
- e-Tax(電子申告)で提出する…インターネットを使って確定申告書を税務署に提出できるオンラインサービスです。自宅からでも簡単に申告ができるため、国税庁も推奨している方法です。特に、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxでの申告が必須条件なので、青色申告をする人はこの方法を選びましょう。
- 郵送で提出する…確定申告書は「信書」に該当するため、通常の宅配便(ヤマト運輸や佐川急便など)では送れません。郵便局を利用する必要があります。
- 税務署へ直接持参する…確定申告期間中は、税務署内に専用の申告窓口が設けられており、申告書に不備がないか確認してもらうことができるため、初めて確定申告をする人には安心な方法です。
締め切りは毎年3月15日なので、それまでに提出しましょう!
ただし、期限日が土日祝日にあたる場合は翌営業日まで延長されます。
④所得税を納める(還付金の確認)
確定申告をすると、1年間(毎年1月1日から12月31日まで)の所得に対して支払うべき所得税が決まります。
この計算の結果、「税金が足りない」と判断された場合には、決められた期限までに税金を納める必要があります。
所得税の納付には、以下の4つの方法があります。
- 現金で納付する…金融機関(銀行や郵便局)や税務署の窓口で、現金を支払う方法です。支払い後に「領収証書」が発行されるため、記録を残したい人にはおすすめです。
- コンビニ払い…QRコードやバーコード付きの納付書があり、30万円以下の税額であれば利用できます。
- 振込・口座振替で納付する…銀行振込や「振替納税(税務署が登録した口座から自動引き落としする仕組み)」を利用して納税する方法です。
- クレジットカードで納付する…「国税クレジットカードお支払サイト」を利用すると、クレジットカードで所得税を支払うことができます。
- スマートフォンアプリで納付する…電子マネーを利用して、所得税を支払うことができます。
確定申告をした結果、「税金を払いすぎていた」と判断されると、還付金(払いすぎた税金)が戻ってきます。
還付金の受け取り方法は、次の3つの方法があります。
- 指定した銀行口座への振り込み…確定申告書に振込先の口座を記入しておくと、そこに還付金が振り込まれます。
- 公金受取口座への振り込み…公金受取口座とは、マイナンバーと紐付けた銀行口座のことです。事前に登録しておけば、還付金を自動的に振り込んでもらえます。
- ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局で受け取る…還付金の通知書(国税還付金振込通知書)を持参すると、ゆうちょ銀行や郵便局で現金を受け取ることができます。
⑤書類の保管
確定申告をした後の書類は、すぐに捨てたり、なくしたりしてはいけません。
確定申告書の控えだけではなく、 見積書、請求書、領収書、レシートなど、お金の流れを証明するすべての書類を保管する必要があります。
電子データで受け取った書類も同様に、パソコンや外付けハードディスク、クラウドに保存ようにしましょう。
保存期間は、確定申告の種類によって異なります。
- 青色申告をしている人…7年間
- 白色申告をしている人…5年間
また、消費税の仕入税額控除を受ける場合(課税事業者の場合)は、7年間の保存が必要になります。
※書類を保管しておく理由は、税務調査が入ったときに、「この支出は何ですか?」と聞かれたときに証拠がないと、不利な扱いを受ける可能性があるからです。
まとめ
今回は個人事業主が知っておくべき「お金の基礎用語」について紹介しました。
- 売上…商品やサービスを提供して得たお金の総額
- 経費…仕事をするために必要な支出
- 所得…売上から経費を引いた後に残るお金
- 所得控除…税金を計算する前に所得から差し引ける金額
- 所得税…所得に対してかかる税金
- 復興特別所得税…東日本大震災の復興のために、所得税に上乗せされる税金
- 住民税…住んでいる地域の行政サービスを支えるための税金
- 個人事業税…特定の業種の個人事業主が支払う税金
- 消費税…商品やサービスの提供に対してかかる税金
- 社会保険(健康保険・年金・介護保険・雇用保険・労災保険)…病気やケガ、老後、失業などのリスクから生活を守るための公的な保険制度
- 確定申告…1年間の所得と税金を計算し、税務署に報告する手続き
これらの知識をしっかり身につければ、個人事業主としてスムーズにお金の管理ができるはずです。
個人事業主は、税金の仕組みを理解していないと、無駄に多く払ってしまったり、申告ミスでペナルティを受けたりするリスクがあります。
せっかく独立して自由な働き方を手に入れるなら、正しいお金の知識を身につけて経営していきましょう!