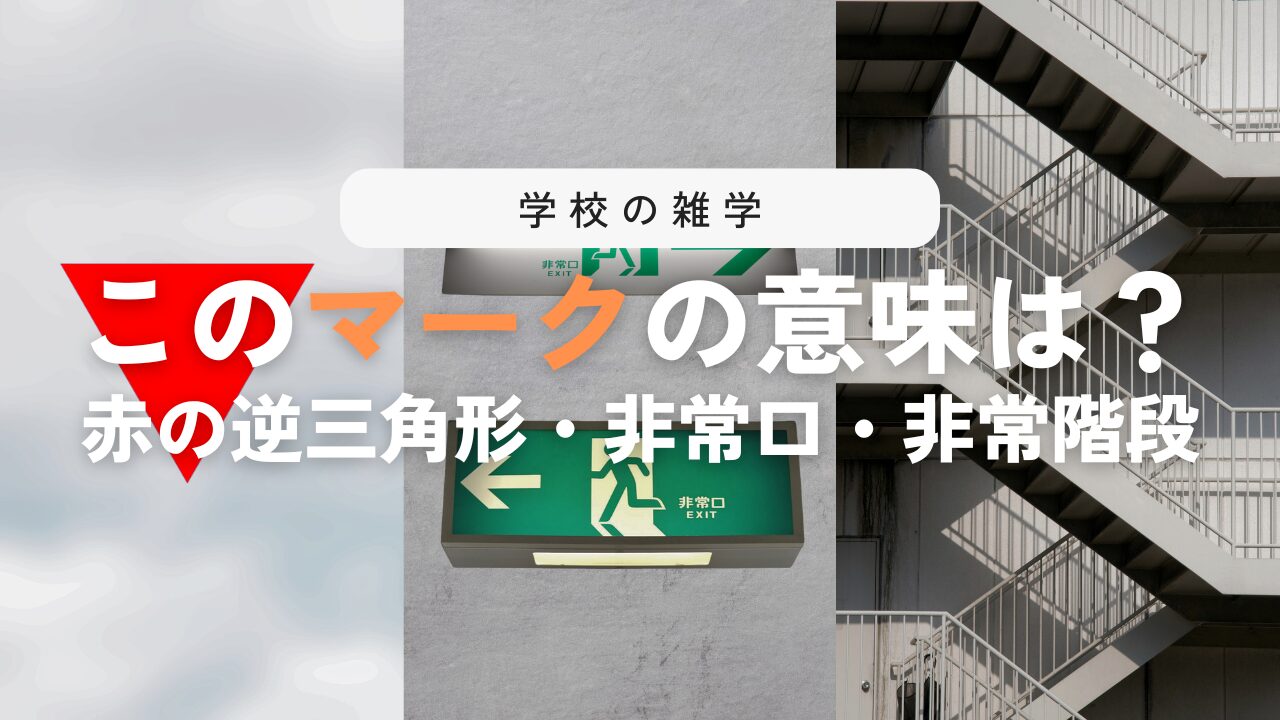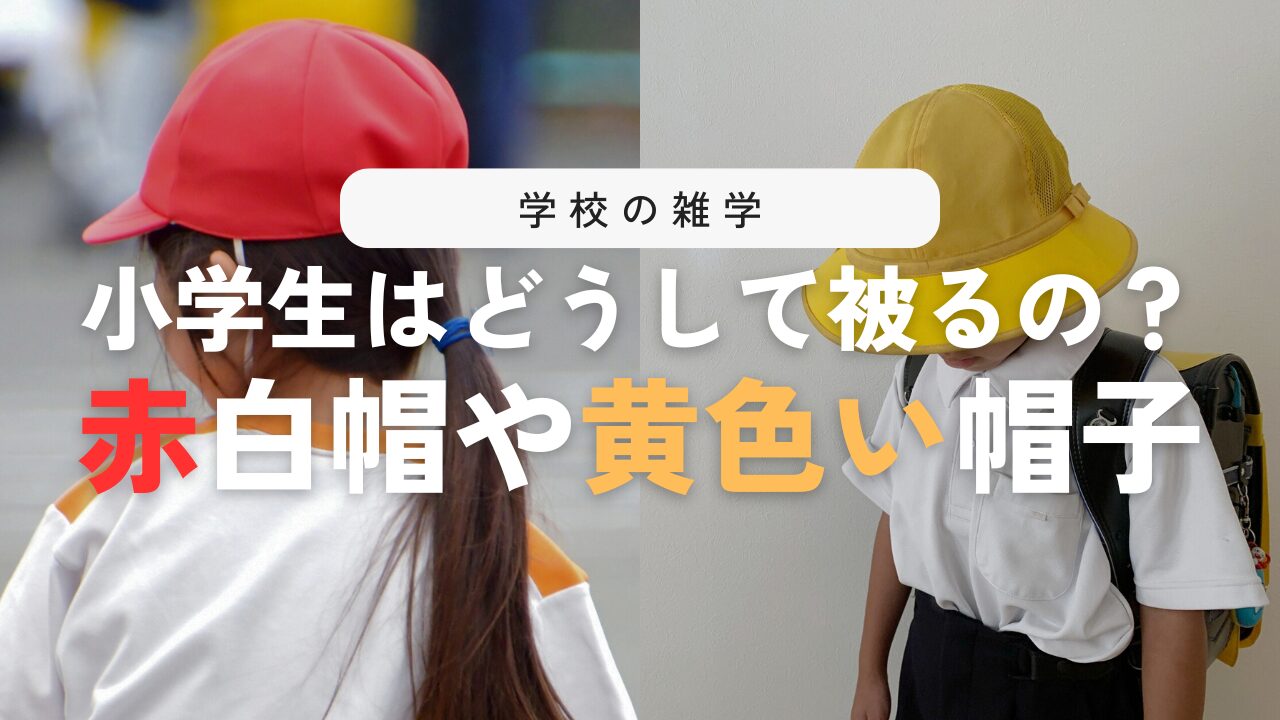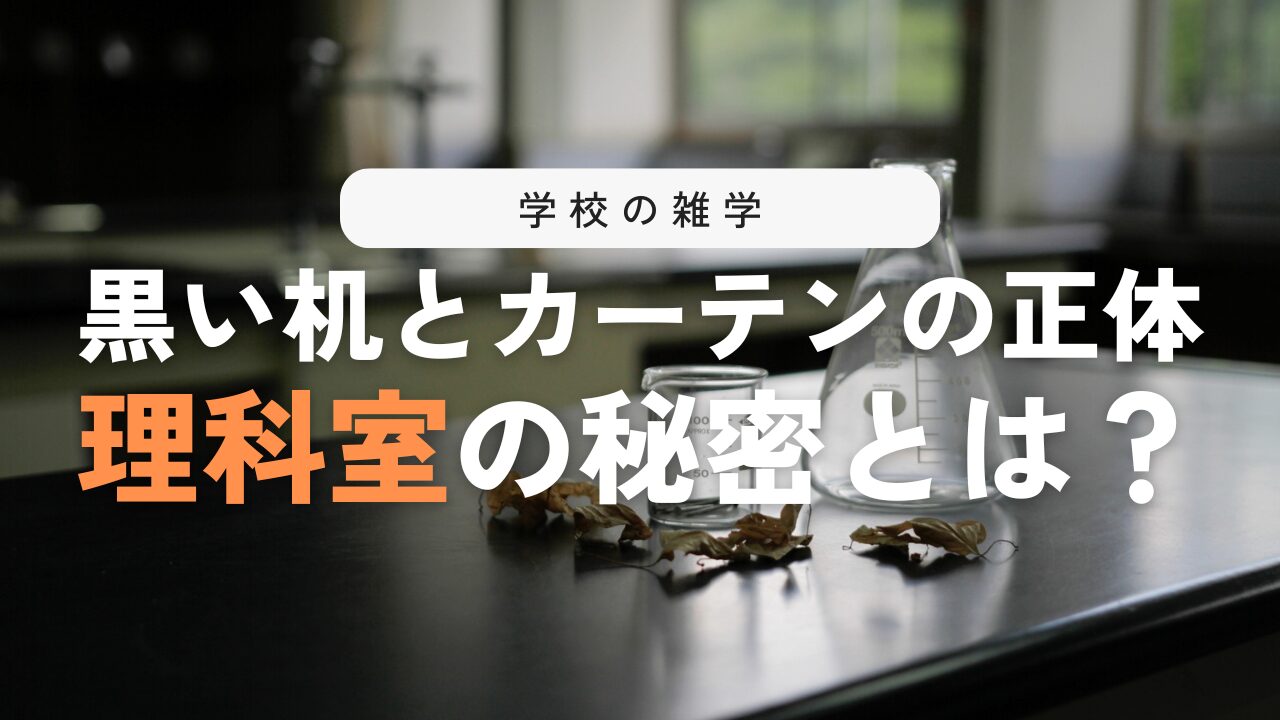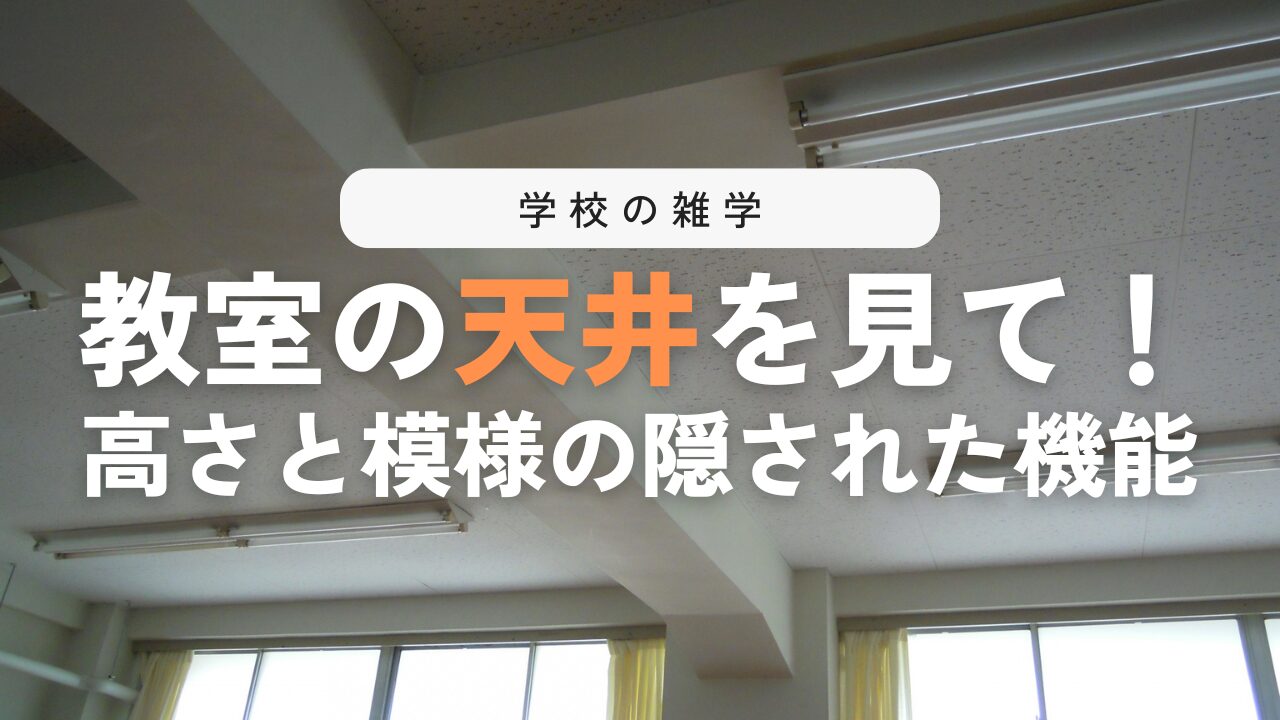【学校の雑学⑦】なぜ学校のチャイムはキンコンカンコンなのか?ルーツを徹底調査
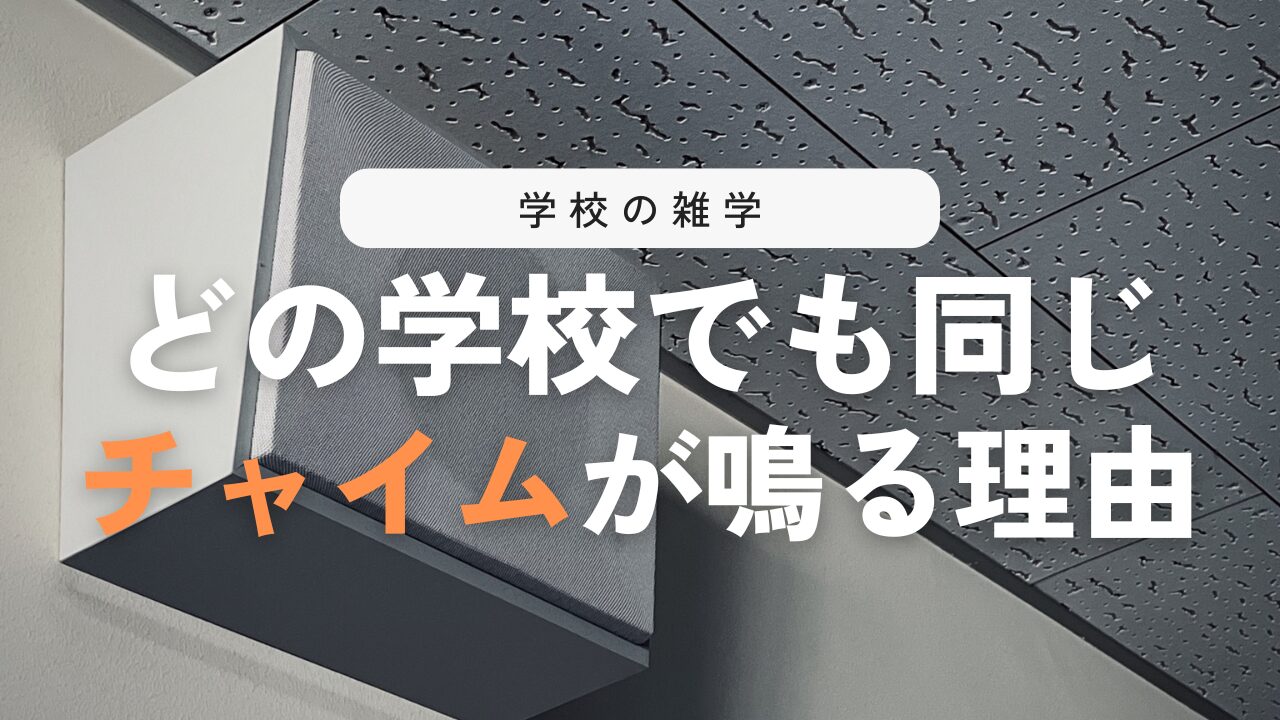
どうも、まっつーです。
学校に響く「♪キーン コーン カーン コーン♪」というチャイムの音。
この学校のチャイムは「いつから使われるようになったのか?」「どうして全国どこの学校でも、同じようなメロディーが使われているのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
今回の記事は、そんな学校チャイムの意外なルーツと日本での広がり、そしてノーチャイム制という新しい流れをわかりやすく解説します!
この記事を書いた人↓

学校チャイムのルーツはロンドンの鐘の音

「♪キーン コーン カーン コーン♪」でおなじみの音は、日本のほとんどの学校で、授業の始まりや終わりを知らせるチャイムです。
実はこの音、ロンドンにある世界的な時計台「ビッグベン」の鐘の音が由来になっているのです。
このチャイムの正式名称は、ウエストミンスターの鐘と言います。
ロンドンのテムズ川沿いにある「ウエストミンスター宮殿(英国国会議事堂)」に設置された巨大な時計塔ビッグベン(現在の正式名:エリザベスタワー)で鳴り響いている鐘の音から生まれたメロディーです。
鐘の音を構成する4つの音階を組み合わせたこの旋律は、もともと1927年にイギリスで作曲されたもので、ウエストミンスター寺院の礼拝堂で使われる「鐘の合図」として採用されたものでした。
日本で最初にビッグベンの鐘の音を採用した学校
では、どうしてイギリスの鐘の音が、日本の学校で使われるようになったのでしょうか?
そのきっかけをつくったのが、1950年代の東京にある中学校の先生でした。
第二次世界大戦が終わった直後の日本の学校では、「ジリリリリ…」とけたたましく鳴るベルが使われていました。
しかしその音は、空襲警報などを思い出させる戦時中の音でもあり、子どもたちにとっては怖さや緊張を連想させるものでした。
「せっかく平和な時代になったのだから、もっと心地よく、子どもたちが前向きな気持ちになれるような音に変えたい」と考えたのが、東京都大田区にある大森第四中学校の国語教師・井上尚美(いのうえしょうび)先生でした。
彼は知人である技術者加藤一雄さんに相談し、当時すでにオルゴールなどで知られていたウエストミンスターの鐘のメロディーをもとに、学校用のチャイムとして開発を依頼しました。
こうして完成した新しいチャイムは、1956年(昭和31年)に大森第四中学校で初めて正式に導入され、その心地よい音色が子どもたちにも先生たちにも受け入れられました。
大森第四中学校のホームページには、次のように記載されています。
本校は、昭和31年に全国で初めて始業と終業を知らせるチャイムを取り入れました。それまでのカネを鳴らしながら廊下を歩いて回る方法から、時計と連動して設定した時間になるとウエストミンスターの鐘の音を模したあの聞きなれたチャイムが流れる方法の発祥の地が本校なのです。現在も、本校には当時の装置が残っています。(今は使用はしていませんが、手動でチャイムの音を聞くことができます。)
そして、日本全国の小学校・中学校・高校へと一気に広がっていきました。
昔の学校にはチャイムがなかった?

現在の学校では、「チャイムが鳴ったら席に着く」「チャイムが鳴ったら授業が終わる」という生活が当たり前ですが、実は明治時代の学校にはチャイムそのものが存在していなかったのです。
その時間を知らせるため、チャイムの代わりに使われていたのが「報時鼓(ほうじこ)」という太鼓です。
1871年(明治4年)には京都府が各学校に報時鼓を設置し、校舎の高い位置(望火楼など)から太鼓を鳴らして、校内や地域に時を知らせるようにしていました。
また、木の板を叩く方法や手動ベル(振鈴:しんれい)、西洋式の金属ベルなどが用いられていました。
管理用務員さんがベルを鳴らし、授業の区切りなどを木の板を木づちで歩きながら叩いて合図することが多かったようです。
そして1923年(大正12年)、京都の開智小学校では、卒業生の寄贈によって京都で初めて自動電気時報装置(いわゆる電鈴)が導入されました。
これにより、管理用務員さんが毎回手で音を鳴らす必要がなくなり、「機械で時間を知らせる時代」が始まったのです。
学校にチャイムが導入された意味
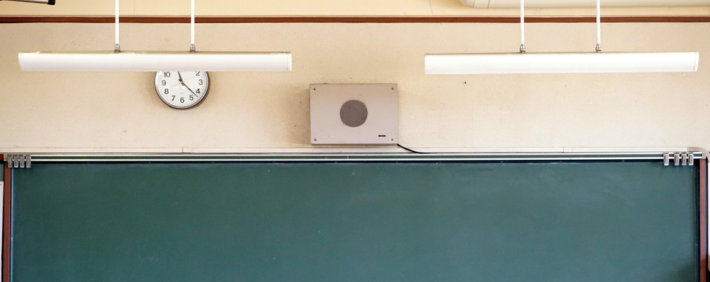
学校にチャイムは、授業の始まりや終わりを知らせる「時間の合図」というだけではありません。
「時間を守る」「行動を合わせる」「集団の中で規律を持つ」といった、社会の中で生きるために必要な力を、子どもたちに自然に身につけさせるための教育的な仕組みでもあるのです。
江戸時代の寺子屋では、子どもたちは自分の都合に合わせて来て、自分のペースで手習いをしていました。
ところが、明治時代に入り、みんなが同じ時間に集まって、同じ内容の授業を受けるという近代的な学校制度が導入されると、「時間を共有する」ことが重要になっていきました。
その中で、チャイムは学校の“時間の区切り”をつくり、子どもたちに「今は集中する時間」「今は休む時間」といった切り替えを自然に促してきました。
つまり、チャイムとは「ただの音」ではなく、「子どもたちの学校生活リズムを整えるための音」なのです。
ノーチャイム制への変化!?

「ノーチャイム制」とは、授業の始まりや終わりを知らせるチャイムを鳴らさない学校のしくみのことです。
近年、全国の学校で少しずつ広がっており、子どもたちが自分で時計を見て行動する力を育てることをねらいとしています。
先生たちは、時間の使い方や行動の意味について子どもたちに問いかけながら指導しています。
チャイムがないことで、授業中の集中が途切れにくくなったり、「そろそろ授業が始まる時間だね」と子どもたち同士で声をかけ合ったりするなど、良い変化も出ています。
ただし、時間の感覚に不安がある子には、やさしい声かけやサポートが必要になることもあるため、学校や学級ごとの工夫が必要です。
まとめ
今回は、学校チャイムの意外なルーツと日本での広がり、そしてノーチャイム制という新しい流れについて紹介しました。
- 今や当たり前になっている「♪キーン コーン カーン コーン♪」という学校チャイムの音には、イギリス・ロンドンのビッグベンがルーツであるという歴史があること
- 戦後の日本で「ジリリリ…」というベルの音をやめ、子どもたちが安心して学べる“心地よい音”として導入されたのが、ウエストミンスターの鐘だったこと
- 近年ではそのチャイムすら鳴らさない「ノーチャイム制」を導入する学校も増え、自分で時計を見て行動する力や、友だちと声をかけ合って過ごす社会性を育てていること
この記事を読んだことで、「学校チャイム」という当たり前に聞こえてくる音に、教育的なねらいと時代を超えた工夫が詰まっていることが見えてきたのではないでしょうか。
私たちはつい「音が鳴ったから動く」ことに慣れてしまいますが、本当に大切なのは、「自分で時間を意識して行動する力」を育てていくことです。
だからこそ、学校現場ではチャイムの有無に関わらず、「子どもたちがどうやって時間を感じ、どうやって動くか?」を丁寧に支えていくことが求められています。
ぜひ、今回の記事をきっかけに、学校のチャイムについて「これにはどんな意味があるのだろう?」と、子どもたちと一緒に考える時間をつくってみてください。