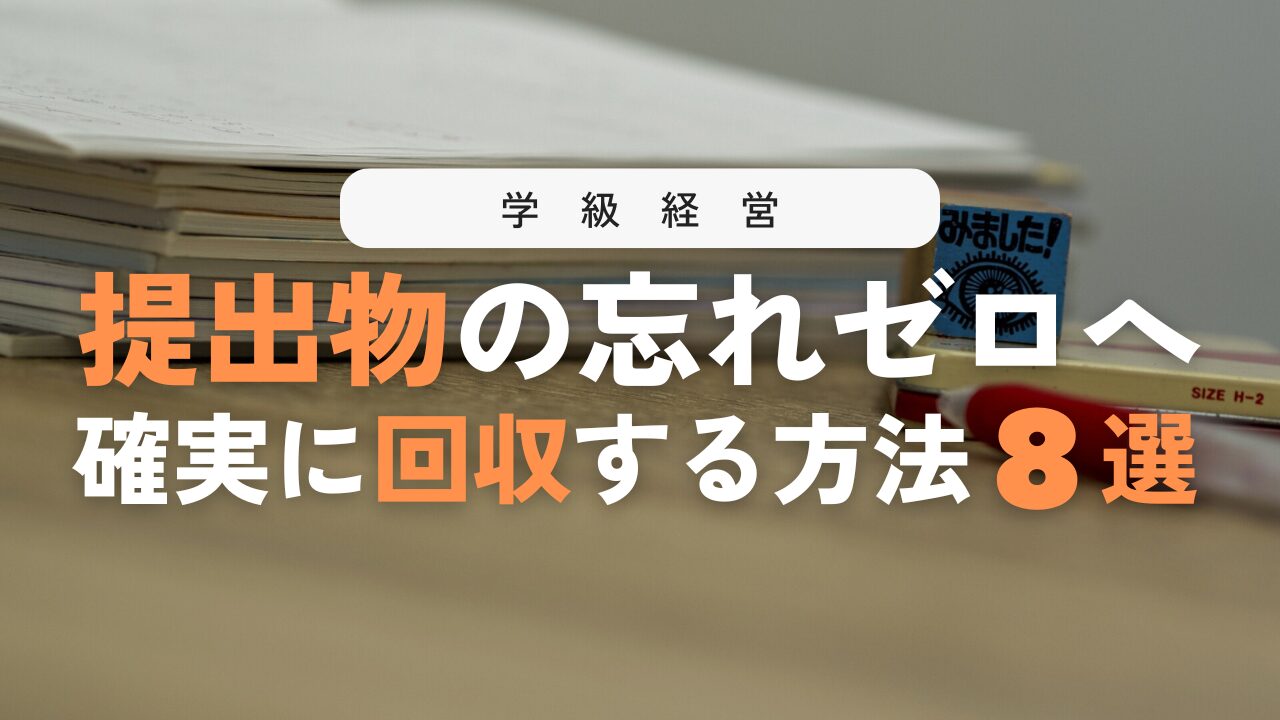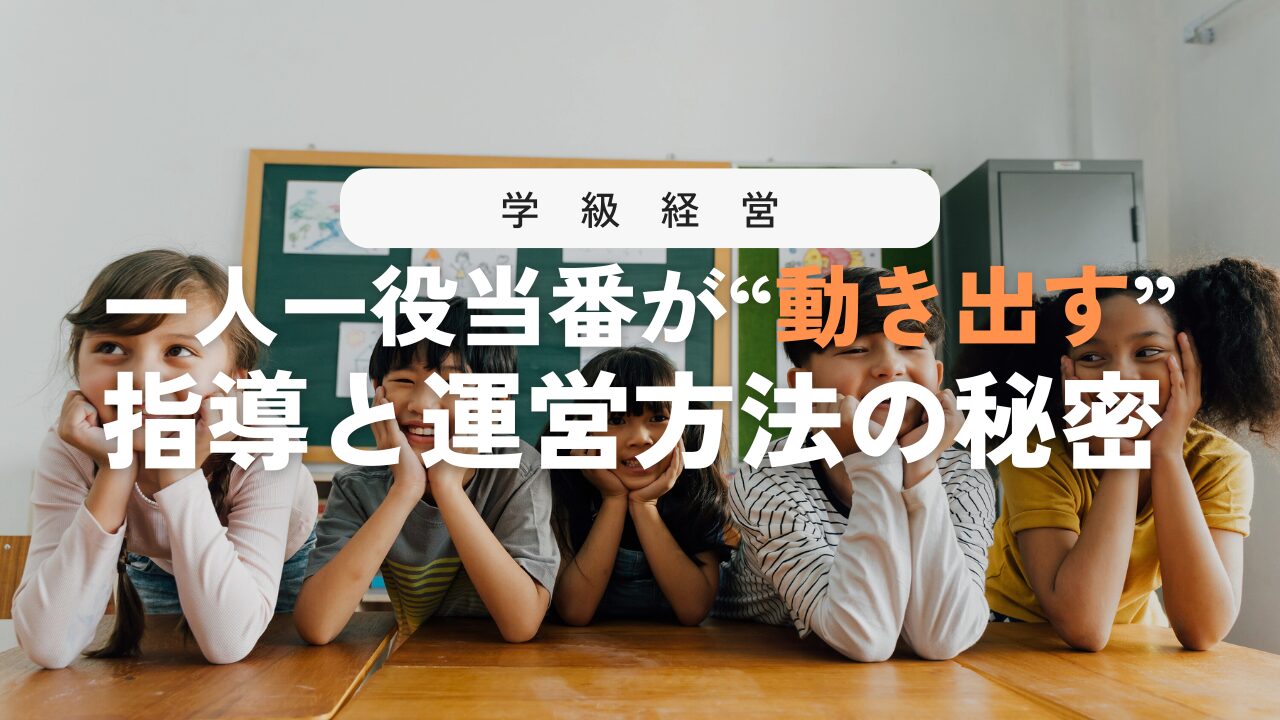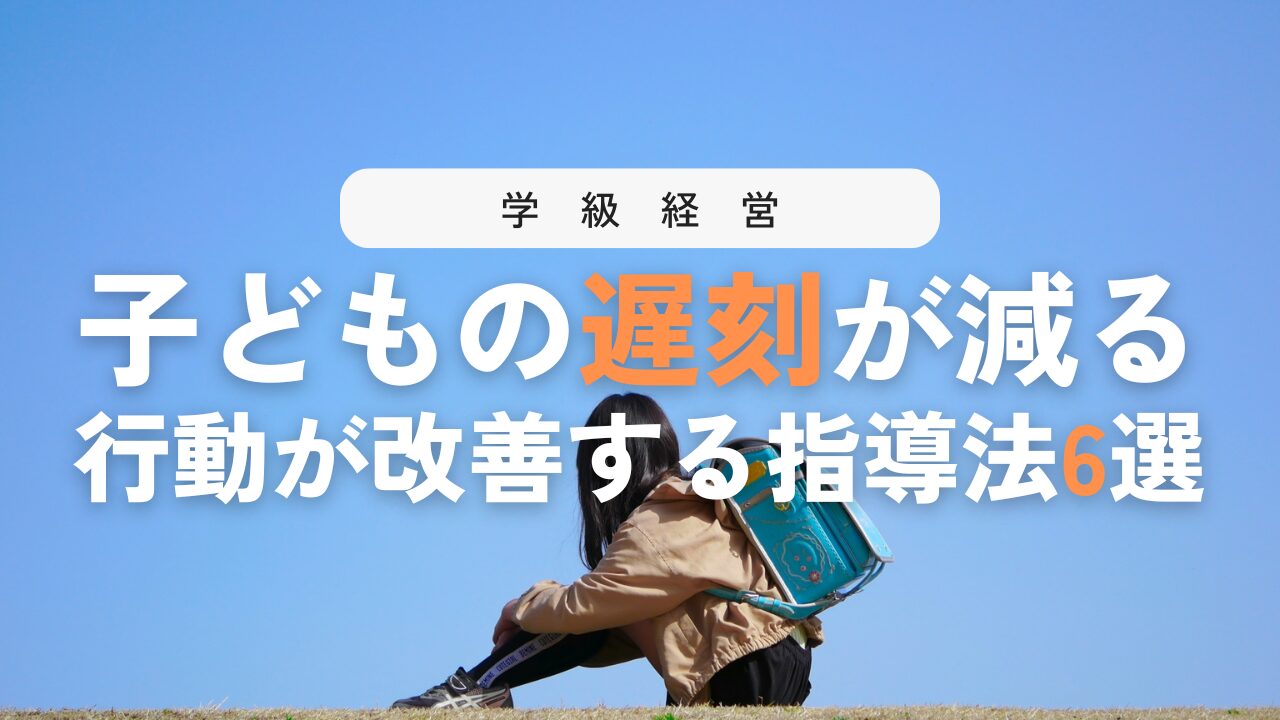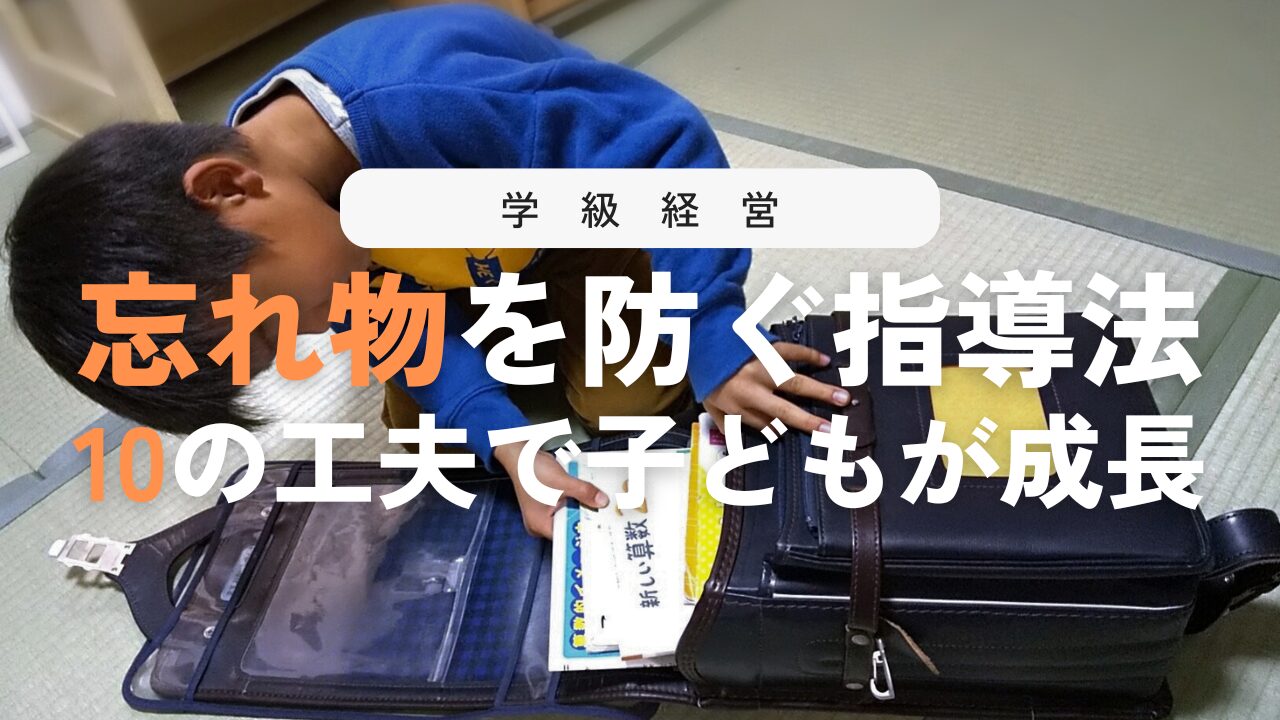【注目】帰りの会で気持ちよく締めくくる!スムーズな進め方と8つの実践例
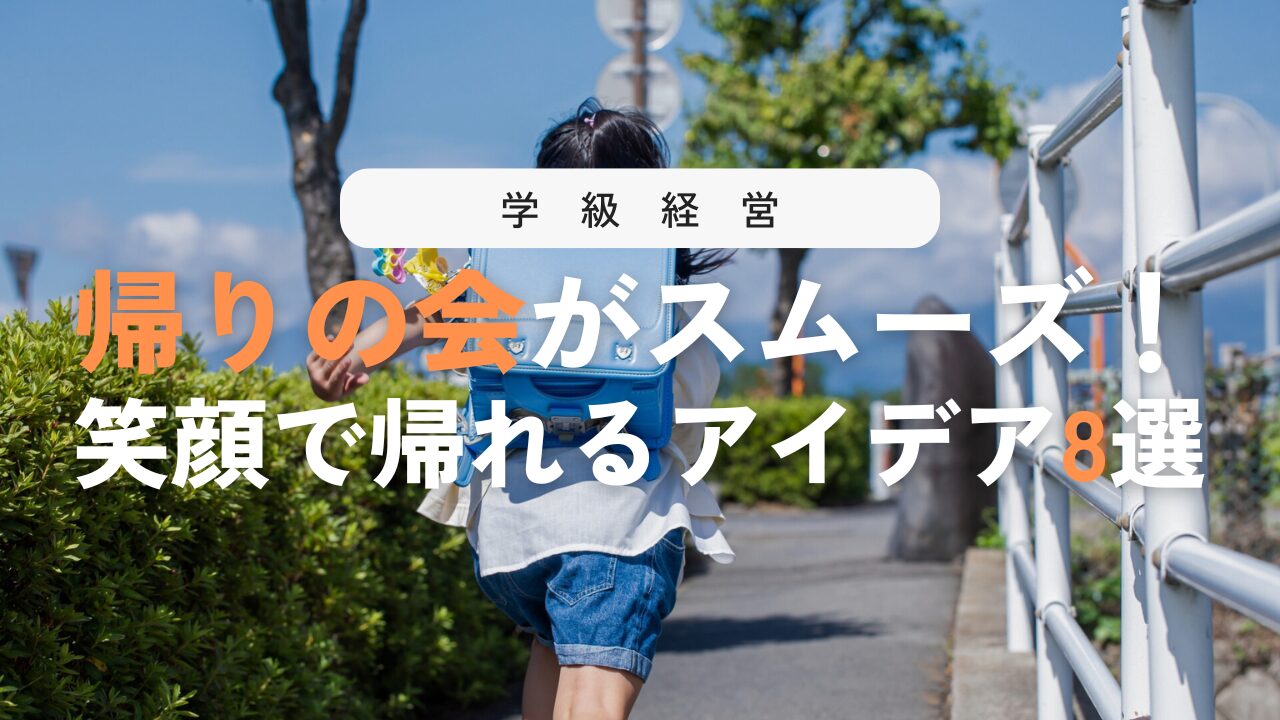
どうも、まっつーです。
学級経営を進める中で、「帰りの会をもっと意味のある時間にしたい」「子どもたちが笑顔で帰れるようにしたい」と考えたことはありませんか?
また、「帰りの会をどう進めればいいかわからない…」「帰りの会に時間がかかって、子どもたちの下校が遅くなってしまう」と悩んでいるかもしれません。
今回の記事は、帰りの会の目的や円滑に進める方法、具体的なプログラム事例8選をわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 帰りの会をもっと効果的にしたいと考えている
- 子どもたちが前向きに帰れる工夫が知りたい
- 帰りの会がスムーズに終わって、早く帰ることができるようにしたい
この記事を読めば、帰りの会が子どもたちにとって意味のある時間になり、笑顔で下校させることができる方法がわかります。
この記事を書いた人↓

帰りの会をする目的とは?

帰りの会とは、1日の学校生活を振り返り、学級全体でその日の出来事を整理し、次の日に向けて気持ちを整えるための時間です。
この時間には、子どもたちの心を整え、学級全体で「明日も学校に登校しよう!」という雰囲気をつくるという3つの目的があります。
- 今日一日をふり返るため
- 明日への準備のため
- 安心感と達成感を共有するため
今日一日をふり返るため
帰りの会は、その日一日を振り返る充実した時間にすることができます。
子どもたちは授業や活動を通じて学んだことや達成したこと、また改善が必要なことをみんなで共有することで、自分の成長に気づくことができます。
たとえば、「体育でチームワークを発揮できた」「音読で大きな声でスラスラと読めた」「友達と協力して掃除ができた」といった成功体験は、自己肯定感を高め、次の目標に向かう意欲につながります。
反対に、うまくいかなかったことや反省点も、次のステップへのヒントとして捉えることができます。
こうして、一日を振り返ることで、子どもたちは自分の成長を実感し、さらに前向きな気持ちで過ごせるようになります。
明日への準備のため
次の日を迎えるための準備も、帰りの会の大切な目的の一つです。
子どもたちが安心して学校生活を送るためには、次の日の予定や持ち物をしっかり確認することが欠かせません。
たとえば、「明日は社会科の町探検があるから楽しみだ」「算数の新しい単元が始まるけど、どんな学習をするのだろう?」と次の日の活動への期待感を高めることができます。
また、「明日は体育だから体操服を忘れないようにしよう」「図工で絵の具を使うから準備しておこう」といった具体的な学習用具の確認をすることで、次の日の見通しが立ち、安心して登校できるようになります。
安心感と達成感を共有するため
帰りの会は、一日を気持ちよく締めくくり、安心して帰るための時間でもあります。
子どもたちが「みんなで頑張った」「一緒に成長できた」と感じられる場にするプログラムを取り入れると良いでしょう。
たとえば、「今日のいいね!」といった成果や努力を称え合うプログラムを取り入れることで、安心感と達成感が得られます。
こうした小さな成功体験の積み重ねは、子どもたちの自己肯定感を育むとともに、「また明日もがんばろう!」という前向きな気持ちを引き出します。
また、クラスメイトとの絆も深まり、学級全体が温かくて安心できる雰囲気に包まれるでしょう。

子どもが安心した気持ちで一日を終えられると、家に帰ってから「今日は学校でこんな良いことがあったんだよ」と、うれしそうに保護者に話すことができるね♪
効果的に帰りの会を進めるための7つのポイント
帰りの会がしっかりと機能している学級は、 子どもたちが安心して一日を締めくくりやすくなり、 次の日に向けて気持ちよく帰ることができるようになります。
反対に、目的があいまいで流れが悪い帰りの会になってしまうと、子どもたちの集中力や意欲が低下し、学級全体の雰囲気にも影響を与えてしまいます。
効果的な帰りの会にするためには、いくつかのポイントを意識することが大切です。
ここでは、帰りの会をより実りある時間にするため、次のような7つのポイントについて詳しく説明していきます。
- 目的を明確にする。
- シンプルで分かりやすいプログラムにする。
- 時間内に終わる。
- 進行役を子どもたちに任せる。
- 子どもたちのアイデアを取り入れる。
- 季節やイベントに合わせて内容を工夫する。
- ショートバージョンも考えておく。
①目的を明確にする
帰りの会は、単なる一日の終わりの手続きではなく、次の日に向けて気持ちを整える時間です。
そのため、「なぜ帰りの会をするのか?」をはっきりと意識させるために、子どもたちは前述した「帰りの会の3つの目的」を伝えましょう。

どのように話せば、子どもたちには伝わるかな?

どうして帰りの会をするのかというと、3つの目的があるからなんだよ。
1つ目は「今日一日をふり返るため」です。学校でさまざまな活動した中で、うれしかったことやがんばったことを思い出してみよう。そうすることで、自分の成長に気づけたり、次にどうがんばればいいかが見えてくるよ。
2つ目は「明日への準備のため」です。明日の予定や持ち物を確認すると、「もっと学習をがんばろう」「忘れずに持っていこう」など、気持ちの準備もできて、安心して学校に来られるし、楽しい気持ちで一日を始められるようになるんだ。
3つ目は「嬉しい気気持ちをわかち合うため(安心感と達成感を共有するため)」です。クラスのみんなで取り組んだことをお互いに認め合うと、温かい気持ちになるよね。それに「今日もみんなでがんばった!」って気持ちで帰ると、「また明日もがんばろう!」って思えるようになるんだよ。
子どもたちの学年や実態に合わせて、わかりやすい言葉を選んで伝えるようにすると良いでしょう。
②シンプルで分かりやすいプログラムにする
帰りの会は、時間が限られていることが多いため、シンプルで分かりやすいプログラムにすることが大切です。
基本的な流れとしては、「一日のふり返り」「先生からの話(明日の予定や持ち物の伝達)」「帰りのあいさつ」などが一般的ですが、あれこれ詰め込みすぎると、子どもたちが焦ったり疲れを感じたりする原因になります。
毎日続けるものだからこそ、無理なく継続できるプログラムを心がけることが必要です。
時間があれば、基本的なプログラムに加えて、子どもたちの実態や学級の雰囲気に合わせて柔軟に調整することもポイントになります。
③時間内に終わる
帰りの会は、あくまで一日の最後の活動であり、時間内に終わることが前提です。
もし、帰りの会が長引いてしまうと、下校時刻が遅くなったり、習い事に間に合わなくなったり、クラブ活動や委員会活動に遅刻したりして、子どもたちが慌ただしい気持ちで帰ることになってしまいます。
急いで帰ろうとした結果、思わぬ事故に巻き込まれてしまう可能性も考えられます。
時間管理に気を配り、子どもたちが落ち着いて下校できるように心掛けましょう。
④進行役を子どもたちに任せる
帰りの会は、先生がすべて進行するのではなく、子どもたち自身で進めることが大切です。
具体的には、日直当番を進行役にすると、子ども一人ひとりに経験できる機会が生まれ、責任感やリーダーシップが育まれます。
また、先生が出張などで不在の場合でも、子どもたち自身で帰りの会を進められるようになれば、学級の安定感も高まります。
進行役を任せる際には、進行の流れや話し方について事前に指導し、自信を持って取り組めるようにサポートしましょう。

補助の先生が入っているときでも、安心して子どもたちに帰りの会の進行を任せることができるね!
⑤子どもたちのアイデアを取り入れる
帰りの会の内容は、先生が一方的に決めるのではなく、子どもたちの意見やアイデアを反映することも大切です。
たとえば、「明日の目標」や「今日の良かったこと」を子どもたちが考える機会をつくると、自分たちが主体的に参加しているという意識が高まり、やる気も引き出されます。
また、「今日のありがとう」や「友達へのメッセージ」など、子どもたちが選んだポジティブな話題を取り入れることで、学級全体が温かい雰囲気に包まれます。
⑥季節やイベントに合わせて内容を工夫する
帰りの会は、季節や学校行事に合わせて内容を工夫することもできます。
たとえば、音楽の授業で扱ったお気に入りの歌を歌う、学芸会の台詞を言う、運動会のの応援合戦の練習をするなど、その時期ならではの内容を取り入れると、子どもたちは家に帰ってからも自主的に練習に励むようになります。
下校の直前に活動するため、子どもたちの記憶に残りやすく、学校を離れてもすぐに思い出せるメリットがあります。
⑦ショートバージョンも考えておく
帰りの会の後、すぐにクラブ活動や委員活動が始まったり、職員会議や研修会、出張などの予定が入ったりしている場合があるため、ショートバージョンの帰りの会もあらかじめ準備しておきましょう。
たとえば、「先生からの話(明日の予定や持ち物の伝達)」「帰りのあいさつ」の2つだけに絞った簡単なプログラムを用意しておけば、短時間でもしっかりと締めくくることができます。
これにより、慌てずに冷静に対応でき、先生は落ち着いた気持ちで子どもたちを下校させることができます。
帰りの会のプログラム事例8選
帰りの会のプログラムは、学校や学級によって異なりますが、基本的な流れは共通しています。帰りの会でよく行われるプログラムの事例は、次の8通りです。
- 帰りのあいさつ
- 今日のいいね!(一日のふり返り)
- 係や当番からの連絡
- 先生からの連絡
- 今日の目標のふり返り
- 日直当番によるスピーチ
- ふり返りカードの記入
- 歌を歌う
勤務する学校で確保できる時間や学級の実態に応じて取捨選択しながら、帰りの会のプログラムを考えてみましょう。
①帰りのあいさつ
帰りの会は、一日をしっかりと締めくくる時間なので、「さようなら」といったあいさつは、感謝の気持ちやお互いへの思いやりを育む大切な機会になります。
全員で声をそろえてあいさつを交わすことで、学級全体に一体感が生まれ、子どもたちが明るい気持ちで下校できるようになります。
また、あいさつは基本的な礼儀でもあり、日常生活で大切なコミュニケーションの一つです。
②今日のいいね!(一日のふり返り)
「今日のいいね!」は、一日の良かったことやがんばったことを振り返る時間です。
このような、ポジティブな出来事をみんなで共有します。
自分のがんばりやクラスメイトの良いところに気づくことで、自己肯定感や仲間への尊敬の気持ちが育まれます。
また、こうしたふり返りは、次の日へのやる気にもつながります。
- 日直当番が「今日のいいね!はありますか?」と聞きます。
- 「今日のいいね!」を言いたい人は挙手をします。
- 日直当番が「Aさん」を指名します。
- 指名されたAさんは、「Bさんが失くした消しゴムを探してくれました」と報告し、「Bさん、いいね!」と言いながら、Bさんに向けて腕を伸ばし、手でのジェスチャーをします。
- その後、全員で「Bさん、いいね!」と声を合わせ、Bさんに向かって腕を伸ばし、手でのジェスチャーをします。
※自分の場合は、自分に向かって「わたし(C)、いいね!」と言って、手でのジェスチャーをします。その後、全員で「Cさん、いいね!」と声を合わせ、Cさんに向かって腕を伸ばし、手でのジェスチャーをします。
③係や当番からの連絡
帰りの会は、係や当番からの連絡を共有する時間として設定できます。
たとえば、「今週の給食当番だった◯班の人は、給食の白衣を持ちましたか?来週の給食当番は◯班です。」「明日は図書室で借りた本の返却日なので持ってきてください」といった具体的な連絡事項を伝える場です。
自分の役割をしっかりと伝える経験は、責任感やリーダーシップを育む良い機会です
また、こうした連絡を通じて、お互いに協力する大切さやコミュニケーションの力も自然と身についていきます。
先生が連絡事項として伝えることもありますが、子どもたちが自分たちのクラスをより良くするために、自発的に動く力を育てていきましょう。
④先生からの連絡
帰りの会では、先生からの大切な連絡も欠かせません。
たとえば、「明日は社会科見学があるので、リュックサックの中にお弁当と水筒、しおりを忘れずに入れてきてください」「来週の◯曜日に習字をしますので、習字セットの準備しましょう」といった明日の予定や持ち物の確認です。
こうした具体的な連絡があると、子どもたちも安心して次の日の準備ができます。
先生は連絡帳に書いた内容を、黒板あるいはホワイトボード、大型ディスプレイで示しながら説明することで、子どもたちは視覚的に理解できるようになります。
⑤今日の目標のふり返り
朝の会で「今日の目標」を設定した場合は、帰りの会ではふり返りをする時間を取りましょう。
たとえば、「今日はみんなで協力して掃除をしよう」「元気よくあいさつをしよう」といった目標がどの程度達成できたかをみんなで確認します。
目標に向かって取り組んだ結果を振り返ることで、達成感や成長の実感が得られ、次の日へのモチベーションが高まります。
もし改善すべき点があれば、「明日は掃除用具の担当を決めてから掃除しよう」「相手の目を見てあいさつするように心がけよう」など、新たな目標を設定するきっかけにもなります。
⑥日直当番によるスピーチ
日直当番によるスピーチは、自己表現力や人前で話す力を育てる絶好のチャンスです。
テーマは自由に設定してもよいですが、「今日がんばったこと」「今日うれしかったこと」「今日の気づき」など、話しやすい内容から始めると良いでしょう。
自分の考えや感情を伝える練習を通じて、自信や表現力が育まれます。
また、クラスメイトの話を集中して聞く力や相手を尊重する態度も同時に育てることができます。
スピーチの最後には、「よくがんばったね!」と全員で拍手するなど、互いに認め合う文化をつくることも大切です。
⑦ふり返りカードの記入
ふり返りカードは、一日の活動や感じたことを記録する時間です。
たとえば、「今日の楽しかったこと」「もっとがんばりたいこと」「友達に感謝したこと」など文章で書けるようにすると、自己反省や自己肯定感が育ちやすくなります。
また、毎日続けることで、子どもたち自身が成長を実感できるようになり、次の日への意欲も高まります。
記入後は、学級全体で共有する(書いた内容を発表したり、一人一台端末で情報を共有する)時間を設けると、お互いの頑張りを認め合う良い機会にもなります。
⑧歌を歌う
帰りの会で歌を歌うことは、気持ちをリフレッシュさせたり、教室の雰囲気を明るくしたりして、気分良く下校することができる効果があります。
たとえば、季節の歌やみんなが好きな曲、行事に合わせた歌などを取り入れると、自然と子どもたちの表情が明るくなります。
音楽は感情を表現する力や協調性を育む大切な要素であり、一緒に歌うことでクラスの一体感も高まります。
まとめ
今回は、帰りの会の目的や円滑に進める方法、具体的なプログラム事例8選について紹介しました。
- 帰りの会は、「今日一日をふり返る」「明日への準備」「安心感と達成感の共有」という3つの目的があり、子どもたちが前向きな気持ちで1日を締めくくれる大切な時間であること
- 効果的に帰りの会を進めるためには、シンプルで分かりやすいプログラムにすることや、子どもたち自身が主体的に進行できる環境を整えること
- 「日直当番によるスピーチ」や「今日のいいね!」などを取り入れることで、学級全体の一体感や充実感が高まること
この記事を読んだことで、帰りの会が「ただの下校前の時間」から、「心の成長と仲間意識を育む大切なひととき」に変わるヒントが得られたのではないでしょうか。
帰りの会は、子どもたちがその日一日を「がんばった」「楽しかった」と感じ、「また明日も学校に行きたい!」と思えるような時間にすることが重要です。
今日から、子どもたちと一緒に、笑顔で前向きな帰りの会を始めていきましょう!