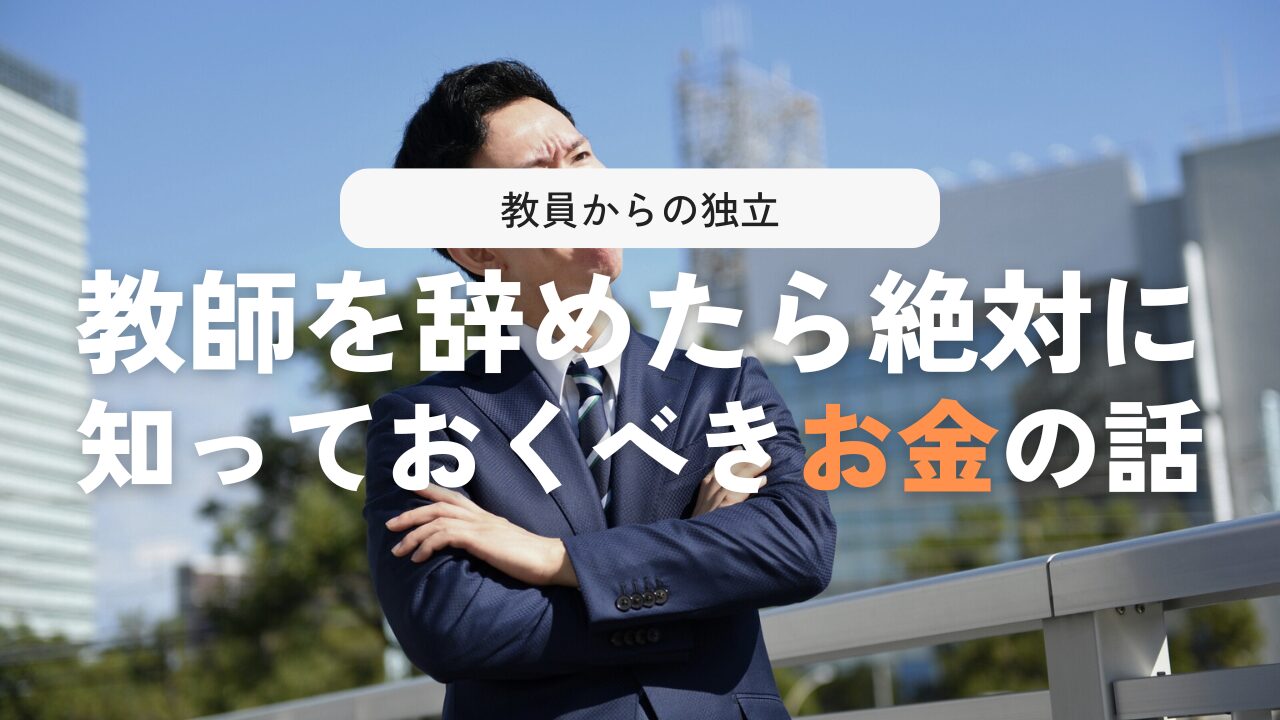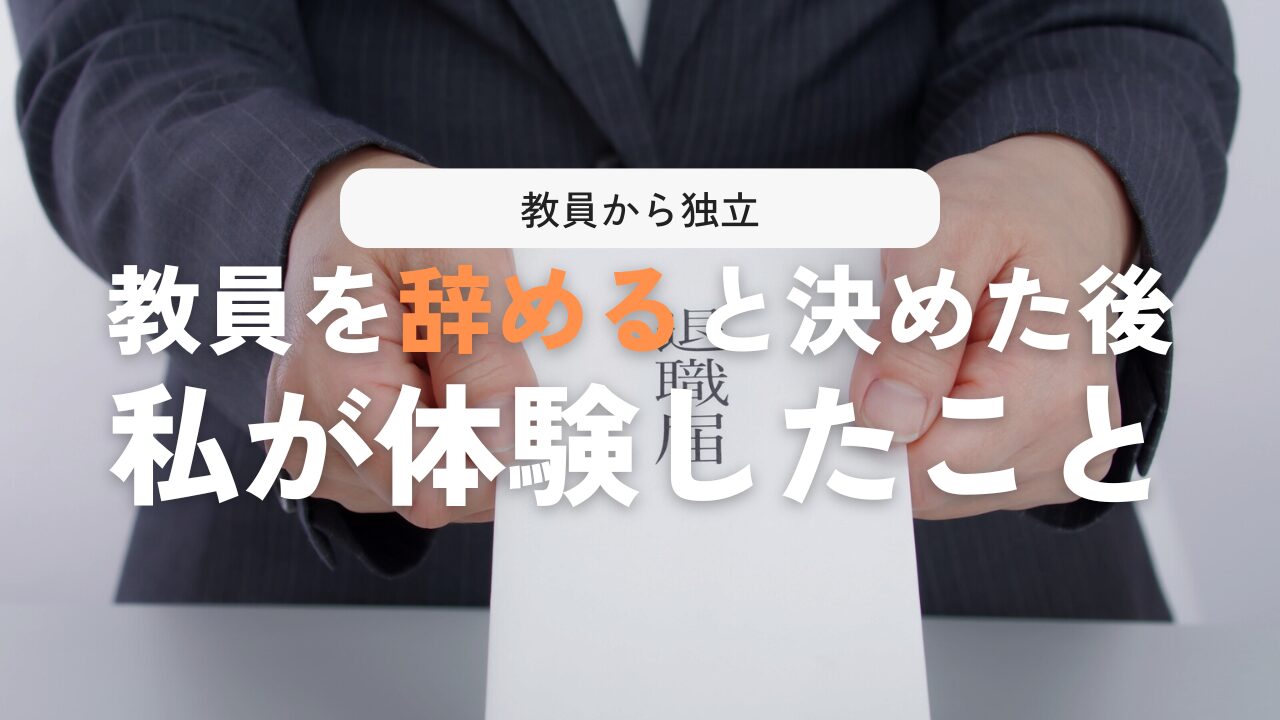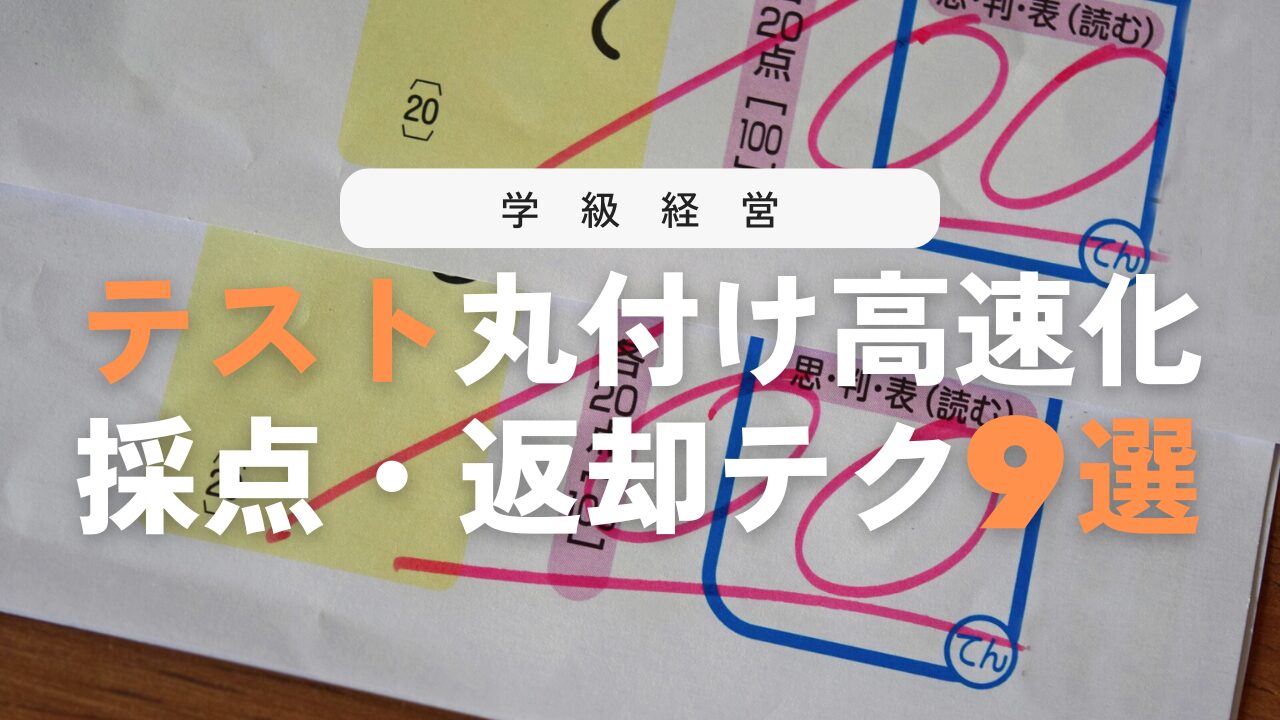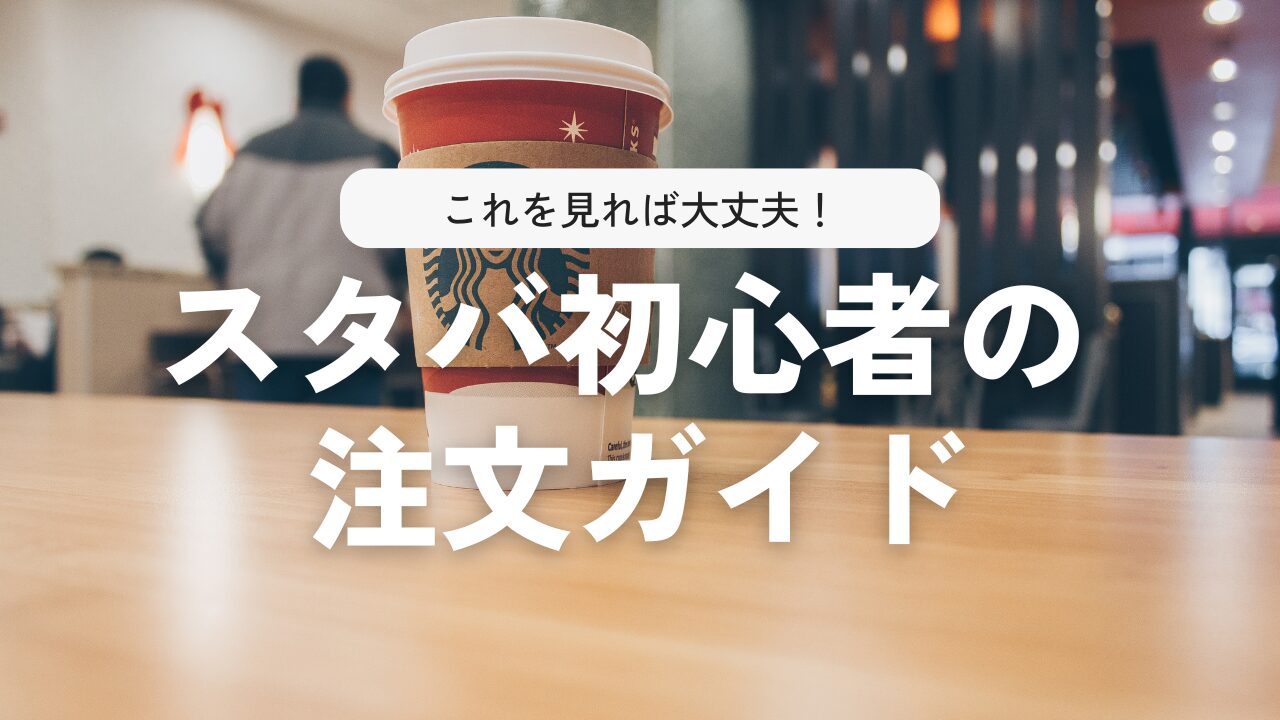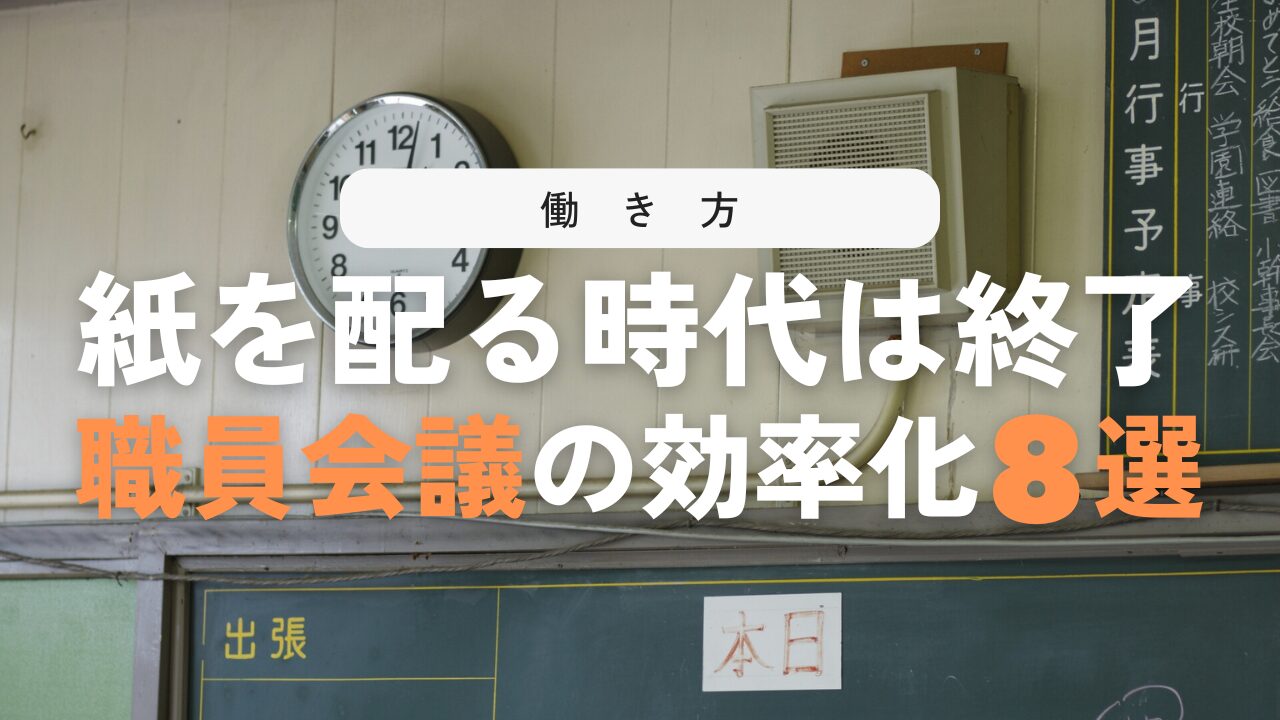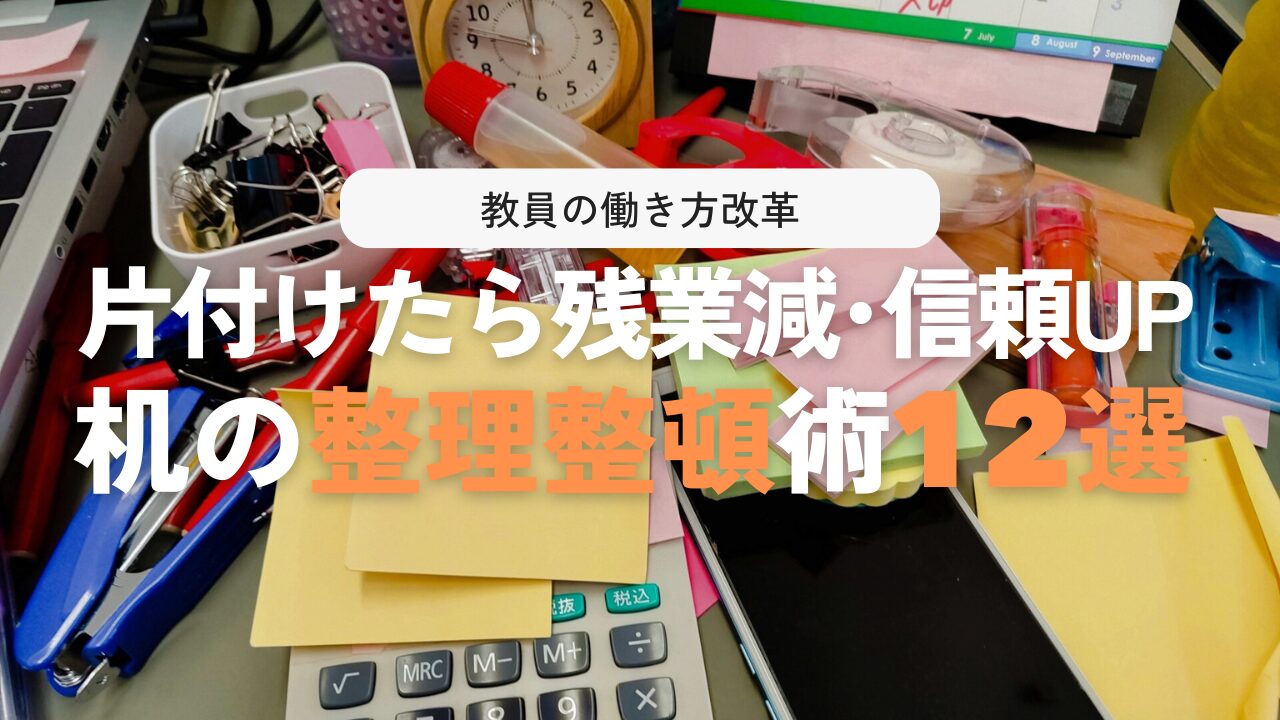教員vs個人事業主!決定的な差とは?

どうも、まっつーです。
教員からの転職や退職を考え、自分の力でお金を稼ぎたいと思った時に、「給料がもらえる安定した仕事と、個人事業主の自由な働き方ではどちらがよいのか?」とお悩みではないでしょうか?
「教員を辞めたら収入はどうなる?」「自由に働けるって本当?」と、不安や疑問が次々に浮かんでくるのは当然のことです。
実際に踏み出す前に、それぞれの働き方の特徴をしっかり理解しておくことがとても大切です。
今回の記事は、給与所得者である教員と個人事業主の根本的な違いをわかりやすく解説します!

この記事は以下のような人におすすめ!
- 教員の仕事は安定しているが、やりがいや自由度を考えると個人事業主も気になる
- 自分には教員と個人事業主のどちらの働き方が向いているのか知りたい
- 教員の仕事に限界を感じ、自分の力でお金を稼げるようになりたい
この記事を読めば、教員と個人事業主それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、自分に合った働き方を考えられるようになります!
この記事を書いた人↓

給与所得者である教員と個人事業主の違い
学校の先生として働いて給与を支払ってもらえる給与所得者(教員や会社員)と、自分で仕事をする個人事業主には、大きな違いがあります。
「給与所得者」とは、学校や会社などで働き、お給料をもらって生活している人のことです。教員を含む公務員や会社員など、多くの人が給与所得者に当てはまります。
「個人事業主」とは、自分で仕事をしてお金を稼ぐ人のことです。会社や学校などに雇われず、自分の力で仕事をして収入を得ます。例えば、お店を経営する人、フリーランスで働く人、農業をする人などが個人事業主に当てはまります。
どちらも働いてお金を得るという点では同じですが、収入の安定性、税金の計算方法、社会保険、仕事の自由度、退職後の違いがあります。
収入の安定性の違い
仕事を選ぶとき、収入の安定性はとても大切なポイントです。
どんなにやりがいのある仕事でも、毎月の収入が不安定だと生活が苦しくなります。
特に、教員のように給料が決まっている人と、個人事業主のように自分で稼ぐ人では、収入の安定性に大きな違いがあります。
教員の収入は毎月決まっているので安定している
教員は給与所得者なので、毎月決まったお給料をもらうことができます。
たとえ景気や業績が悪くなっても、学校が急になくなることはほとんどなく、一定の収入が保証されているのが大きなメリットです。
特に、公立学校の教員は公務員なので、雇用が守られており、収入が減る心配はほぼありません。
また、教員にはボーナス(賞与)が支給されることが多く、年に2回、まとまったお金を受け取ることができます。
ボーナスがあることで、貯金をしたり、大きな出費に備えたりしやすくなります。
さらに、教員は勤務年数が増えるごとに昇給する制度があるため、長く働けば働くほど収入が増える仕組みになっています。
このように、教員の収入はとても安定していて、計画的に生活しやすいという特徴があります。
- 毎月給料が支払われる
- ボーナス(賞与)がある
- 昇給制度がある
個人事業主の収入は不安定で変動が大きい
一方、個人事業主は仕事の成果によって収入が変わります。
仕事がたくさんあれば収入も増えますが、仕事が少なければ収入が大きく減ってしまいます。
例えば、お客さんが減ったり、市場の状況が悪くなったりすると、一気に収入が下がる可能性があります。
また、個人事業主にはボーナスがありません。
毎月の売上がそのまま収入になるため、安定した収入を得るためには自分でしっかり計画を立てて働く必要があります。
仕事がない月は収入がゼロになることもあり、そういうときに備えて貯金や資金の管理がとても重要になります。
さらに、個人事業主は自分の力で収入を増やすことができる反面、すべてが自己責任です。
- 毎月支払われる給料がない
- 仕事の成果によって収入が変わる
- ボーナス(賞与)がない
- 自己責任
税金の違い
お金を稼ぐと、税金を納める必要があります。
しかし、教員のような給与所得者と個人事業主では、税金について大きく異なります。
給与所得者である教員は勤務先で税金の処理をしてくれるため、あまり意識することはありませんが、個人事業主はすべて自分で管理しなければなりません。
税金を納める仕組みの違い
給与所得者である教員は、給料をもらうときに税金がすでに引かれています。
給料明細を見れば分かるように、「所得税」や「住民税」などが差し引かれた状態で手取りの給料が支払われます。
これは、勤務先が代わりに計算し、税金を納めてくれるからです。
そのため、教員は自分で税金を計算したり、支払ったりする手間がほとんどありません。
一方、個人事業主は、自分で税金を計算し、納める必要があります。
収入がいくらあるのか、経費がどのくらいかかったのかを自分で記録し、1年分をまとめて税務署に申告します。
この手続きを「確定申告」といい、毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
確定申告をしないと、税金を納めないことになり、ペナルティ(罰則)があるので注意が必要です。
所得の計算方法の違い
税金を計算するためには、まず「所得(収入から必要な控除や経費を差し引いた後の金額)」を求めます。
教員の場合、所得は「給与所得控除」で計算されます。
これは、仕事に必要な経費をあらかじめ考慮して、収入から一定の金額を差し引く制度です。
実際にどれくらいの経費がかかったかを計算する必要はなく、収入に応じて自動的に控除額が決まります。
一方、個人事業主の場合、所得は「売上 − 経費」で計算します。
つまり、仕事で得た収入(売上)から、仕事に必要な支出(経費)を引いた金額が所得になります。
経費には、事務用品の購入費、交通費、家賃など、事業に関わるさまざまな支出が含まれます。
そのため、個人事業主は経費をしっかり管理し、できるだけ所得を少なくすることで税金を減らす工夫が必要になります。
税金の計算の手間の違い
教員は、勤務先が税金を計算してくれるため、手続きが簡単です。
毎月の給料から自動的に税金が引かれるため、自分で税額を計算する必要がありません。
さらに、年末には「年末調整」という仕組みがあり、払いすぎた税金が戻ってくる場合もあります。
この手続きも学校の事務の人が行ってくれるので、教員は特別な準備をする必要がありません。
しかし、個人事業主はすべて自分で計算しなければならず面倒です。
収入と経費を記録し、確定申告の時期に税務署へ申告する必要があります。
また、税金を減らすための節税対策(青色申告の活用など)も考える必要があるため、税金の知識がないと損をしてしまう可能性があります。
社会保険の違い
私たちは病気やケガをしたときの医療費、老後の生活費、万が一のときの保障など「社会保険」という仕組みで支えられています。
しかし、教員のような給与所得者と個人事業主では、加入できる社会保険の種類や負担する金額が大きく異なります。
加入する健康保険の違い
教員は以下の健康保険に加入します。
- 公立学校の教員…公立学校共済組合
- 私立学校の教員…日本私立学校振興・共済事業団
- 国立大学の教員…文部科学省共済組合
健康保険は医療費を安く(基本的に3割負担)する制度です。
これらの保険は、勤務先である自治体や学校が自動的に手続きをしてくれるため、教員は特別な手続きをしなくても健康保険に加入できます。
一方で、個人事業主は国民健康保険に加入します。
これは、会社や自治体に雇われていない人が加入する制度です。
個人事業主は、国民健康保険の手続きをすべて自分で行う必要があり、支払う保険料も自分で計算しなければなりません。
健康保険の支払いの違い
教員が加入する健康保険は、勤務先が保険料の半分を負担してくれます。
そのため、教員は実際に払う金額が少なくて済みます。
さらに、健康保険には傷病手当金という制度があり、病気やケガで長期間働けなくなったときに、給料の約3分の2が最長1年6か月間支給されます。
このように、教員の健康保険は手厚い保障があるのが特徴です。
一方、個人事業主が加入する国民健康保険には、勤務先の負担がないため、保険料をすべて自分で支払う必要があります。
そのため、教員よりも負担が大きくなります。
さらに、個人事業主の国民健康保険には傷病手当金がないため、病気やケガで仕事ができなくなっても、収入が補償されることはありません。
もし働けなくなった場合の生活費は、自分で貯金しておく必要があります。
年金の違い
教員は厚生年金に加入するため、老後にもらえる年金が多くなります。
厚生年金は、勤務先が保険料の半分を負担してくれるため、個人の負担が少ないのに、将来的にもらえる年金額は多くなるというメリットがあります。
一方、個人事業主が加入するのは国民年金のみです。
国民年金は保険料をすべて自分で負担する必要があります。
また、国民年金は厚生年金よりも受け取れる額が少ないため、老後の生活費を年金だけでまかなうのは難しいことが多いです。
そのため、個人事業主は老後に備えて、貯蓄やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を利用して、資産を増やす工夫が必要になります。
失業時の違い
会社員は雇用保険に加入しているため、万が一仕事を辞めることになった場合でも、失業手当(失業保険)を受け取ることができます。
また、雇用保険には育児休業給付金などもあり、出産や育児のために一時的に仕事を休む場合でも、一定の収入が補償される仕組みがあります。
しかし、公立学校の教員の場合は原則として雇用保険の対象外であり、失業手当も支給されません。
個人事業主も同様に、雇用保険に加入できません。
もし収入が途絶えた場合は、自分で貯めておいたお金で生活をするしかないため、しっかりと資金計画を立てる必要があります。
仕事の自由度の違い
仕事を選ぶとき、自由に働けるかどうかはとても大切なポイントです。
毎日決まった時間に働くのがいいのか、それとも自分の好きな時間に働けるほうがいいのか、人によって理想の働き方は違います。
教員のような給与所得者と個人事業主では、仕事の自由度に大きな違いがあります。
働く時間の自由度の違い
教員は、勤務時間が決められています。
朝の始業時刻が決まっており、基本的に終業時刻までは学校にいなければなりません。
授業や会議、行事など、1日のスケジュールもほぼ決まっているため、自由に働く時間を選ぶことはできません。
さらに、授業の準備や成績処理、保護者対応など、勤務時間外にもしなければならない仕事が多く、実際には長時間労働が大きな問題になっています。
一方で、個人事業主は自分で働く時間を決めることができます。
朝から働くのも、夜に仕事をするのも自由で、自分の生活スタイルに合わせてスケジュールを組むことができます。
例えば、朝ゆっくりして午後から働くことも可能ですし、平日を休みにして土日に働くこともできます。
ただし、自由である分、自分でしっかりスケジュール管理をしないと、だらけてしまったり、逆に働きすぎたりすることもあります。
働く場所の自由度の違い
教員は、勤務する学校が決まっており、基本的には毎日同じ場所で働く必要があります。
どの学校で働くかは、自治体や教育委員会の人事異動で決まるため、自分で勤務地を選ぶことはできません。
引っ越したくてもすぐに異動できるわけではなく、勤務地の自由度は低いのが現実です。
個人事業主は、働く場所を自由に決めることができます。
自宅で仕事をすることもできますし、カフェやコワーキングスペースで仕事をすることも可能です。
さらに、インターネットを活用すれば、旅行先や海外でも仕事ができるため、好きな場所で働きたい人にとっては大きなメリットになります。
ただし、自由な反面、自分で集中できる環境を整えないと、仕事がはかどらなくなることもあります。
仕事内容の自由度の違い
教員の仕事内容は決まっており、大きく変えることはできません。
授業をするのはもちろん、行事の準備、部活動の指導、会議への参加など、さまざまな業務があります。
どんな仕事をするかは学校の方針や教育委員会の指示によって決まるため、自分の好きな仕事だけをすることはできません。
個人事業主は、自分で仕事の内容を決めることができます。
どんな仕事をするか、どんなお客さんと取引するか、すべて自分で選ぶことができます。
例えば、自分の得意な分野だけに集中することもできますし、好きな仕事だけを選ぶことも可能です。
ただし、仕事を選びすぎると収入が安定しなくなるため、バランスを考えながら仕事を受けることが大切です。
休みの自由度の違い
教員の休みは、学校のカレンダーに従うため、自分で自由に決めることはできません。
夏休みや冬休みがありますが、実際には研修や会議があるため、完全に休めるわけではありません。
また、平日に休む場合は「年次有給休暇」を取得して休むことになります。
※夏休みには夏季休暇が5日間取得できます。
個人事業主は、自分の好きなときに休むことができます。
平日に休むこともできますし、長期休暇を取ることも可能です。
ただし、休めばその分収入が減るため、自由に休める反面、しっかり計画を立てることが必要になります。
退職後の違い
仕事をしててお金を稼ぐことができている時は生活費の心配は少ないですが、退職後は状況が大きく変わります。
働かなくなった後、どのような収入があるのか、どのくらいの生活費が必要なのかを考えておかないと、思わぬ経済的な不安に直面することになります。
退職金の違い
教員は、退職するとまとまった金額の退職金を受け取ることができます。
退職金の金額は勤続年数や役職によって異なりますが、長く勤めれば勤めるほど多くの金額を受け取れる仕組みになっています。
特に、公立学校の教員は公務員として扱われるため、退職金の制度がしっかりしており、無事に定年退職を迎えることができれば2千万円以上を受け取れることもあります。
一方、個人事業主には退職金がありません。
会社や自治体に雇われているわけではないため、退職時にまとまったお金をもらえる制度がないのです。
そのため、個人事業主は退職後の生活に備えて、自分で資産を形成しておく必要があります。
具体的には、貯金や投資をしたり、退職金の代わりになる制度(iDeCoや小規模企業共済など)を活用することが重要になります。
年金の違い
前述の通り、教員は厚生年金に加入しているため、老後に受け取れる年金の額が多くなります。
厚生年金は、現役時代の給料に応じて支払う金額が決まり、給料が高いほど多くの年金を受け取ることができ、老後の生活が安定しやすいというメリットがあります。
個人事業主が加入するのは国民年金のみです。
国民年金は、全員が同じ金額を支払い、受け取る年金額も一律です。
そのため、厚生年金に比べて老後に受け取れる年金額が少なくなります。
退職後の収入の違い
教員は、再雇用制度があるため、希望すれば定年後も正規教員や非常勤講師、支援員などとして働くことができる場合もあります。
これにより、完全に仕事を辞めずに、収入を得ながら徐々にリタイア生活に移行することも可能です。
一方、個人事業主は、退職のタイミングを自分で決めることができる反面、仕事を辞めた後の収入がゼロになってしまう可能性があります。
そのため、事業を続けるのか、資産運用で収入を得るのか、あるいは別の仕事をするのかを考えておかなければなりません。
まとめ
今回は給与所得者である教員と個人事業主の根本的な違いについて紹介しました。
| 給与所得者(教員) | 個人事業主 | |
|---|---|---|
| 収入の安定性 | 毎月の給料 ボーナス(賞与) 昇給制度 | 仕事の成果による収入 全て自己責任 |
| 税金の納め方 | 勤務先が税金を納める | 自分で納める |
| 税金の計算方法 | 給与ー給与所得控除=給与所得 | 売上ー経費=所得 |
| 税金の計算の手間 | 勤務先が計算してくれるので簡単 | すべて自分で計算するため面倒 |
| 加入する健康保険 | 健康保険 | 国民健康保険 |
| 健康保険の支払い | 保険料は勤務先と折半 傷病手当金あり | 保険料は全額自己負担 傷病手当金なし |
| 年金 | 厚生年金 保険料は勤務先と折半 | 国民年金 保険料は全額自己負担 |
| 失業した場合 | 公立学校の教員の場合は、雇用保険の対象外で、失業手当は受け取れない ※会社員の場合は、雇用保険に加入できるため、失業手当が支給される | 雇用保険の対象外で、失業手当は受け取れない |
| 働く時間 | 始業時刻から終業時刻まで拘束される | 自由 |
| 働く場所 | 勤務する学校 | 自由 |
| 仕事内容 | 決まっている | 自由 |
| 休日 | カレンダー通り 年次有給休暇を取得する 夏季休暇は5日間 | 自由 |
| 退職金 | 退職金あり | 退職金なし |
| 退職後の収入 | 再雇用制度を活用できる | 収入ゼロ |
どちらを選ぶかは、あなたの価値観次第です!
安定を重視するなら教員、自由を求めるなら個人事業主を選ぶとよいでしょう。
どちらにもメリット・デメリットがあります。
自分の理想の働き方を考えて、後悔しない道を選んでください!